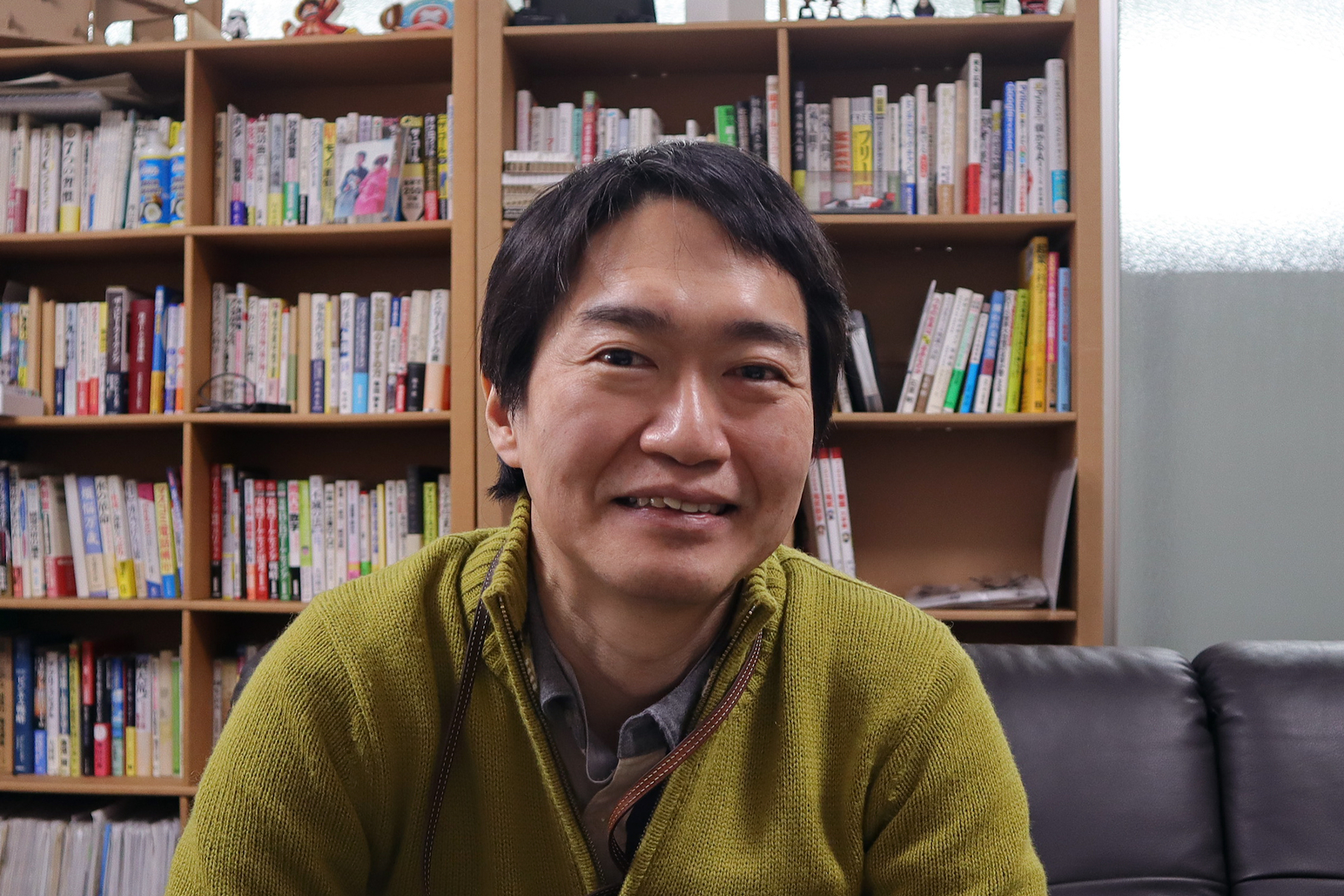
SNSなどを積極利用してB to C事業を拡大
クラウドファンディングの「ネコ神社ハウス」に人気集中
パッケージやディスプレイを事業の根幹に、通販系の事業、海外事業など段ボールを取り巻くさまざまな事業を展開する豊栄産業株式会社。法人向け中心から、独自のアイデアで消費者向け市場を開拓し、大きな成長を図っている。そのひとつがオリジナル段ボール家具やキッズ用品などの通販事業だ。
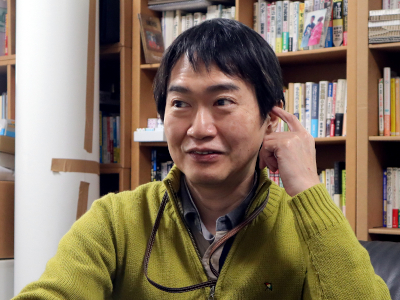
「通販系ではもともとB to Bが中心でしたが、次第にB to Cへのシフトが進み、現在では大手通販サイトに出店するなど、しっかりと根付いてきました。TVのニュース等で報道されたことがきっかけになり、子ども向けの『ままごとダンボールキッチン』『オンリーハウス』などが人気を集めています」
同社はDX時代の到来に合わせ、幅広いデジタルツールを活用したビジネスモデルを実現した。
「DX化と言われるなか、本当にネットを使いこなせているかを自問自答したところ、まだまだ大きな可能性が潜んでいることに気づきました。それならば、より面白いことをやっていこうと社内で検討したのです。SNS等を活用して、広くアピールする方法を探り、FB、Twitter、ブログ等での展開をスタートしました」
2020年には同社初の試みとして、クラウドファンディングを使ったプロジェクトを立ち上げた。
「神社のイメージで作り上げたネコの段ボールハウス『元祖!ネコ神社ハウス』です。すべて初めてづくしの事業でしたが、新型コロナウイルスの影響で景況が悪化しているなか、何も行動を起こさなければ新たな一歩は踏み出せないという思いで進めたものです」
ゼロ以下にならないのなら、とにかくチャレンジしようという気持ちで始めたという。しかし、当初は50万円を目標に設定したものの、注文は2週間でわずか2件だった。
「その後、保護猫カフェを運営する企業とコラボし、収益の一部を猫の殺処分を0にする活動に寄付する『ネコ助け』も込めて支援を募ったところ、その後の2週間で目標額を上回る大きな反響があったのです。一時は、Twitterのトレンドワード6位にランクするほどでした。結果的には360万円超の販売につながりました」
現在は、さらに新たな企画として、ネコ関連の商品開発を進めている。実を結んだのは、果敢な挑戦があったからだ。
「当たって砕けろというように、何かアイデアを思いついたら、チャレンジしてみることが大切です。心の中で温めていたり、口で言うだけでなく、やったらやっただけ懐が広がると思うのです。最初は大変ですが、体験することで器がひとまわり大きくなると実感しています」
事業を分散することで非常時のリスクを抑える
わずか1分で簡単に組み立てられる防災ベッドも
コロナ前は販促ディスプレイが売上の50%以上を占めていたという。しかし、新型コロナウイルスの影響で店舗を訪れる機会が減ったため、販促物への需要が急速に落ち込んだ。
「その一方で、パッケージや段ボール製の飛沫感染防止ついたて(シールド)などが伸び始め、巣ごもり需要によりB to C関連の売上も上昇しました。このような不測の事態が生じたときには、ひとつの分野に集中するよりも、あらかじめ事業分野を分散することが、リスクヘッジのためにも重要だと考えます」
コロナ禍であったため、よい意味で危機感を持って対応したことが、対応をより迅速に進められたのではないかと振り返る。
「何かアイデアを思いついたらすぐ設計に取りかかり、製品化を進められるフットワークの軽さと設計力が当社の強みです。社員約40人のうち、東京と大阪に7人の設計・デザイン担当がいます。お客様のご要望通りスピード感を持って製品にするという工程は、ディスプレイ事業で鍛えられていますから、迅速な対応が可能なのです」
同社では現在、防災系の製品開発も進めているという。
「被災された方にヒアリングするなどの調査をしたところ、ベッドの組立に10分ほどかかるという声がありました。そこで、約1分で簡単に組み立てられるベッドやパーティション、ベビーベッド、トイレなどを開発しています」
災害時の備えとして自治体が備蓄することで、社会にも大きく貢献できる事業だ。
「さまざまな情報があふれる社会のなかで、その一部だけを捉えて惑わされずに、きちんと自分自身で本質を考察してコウドウすることが大切です。つまり『行動』ではなく『考働』です。どんな状況にあっても、動いた中から新しく考察し、前に進むことを考えています」
同社は今後、B to Cの新製品開発を積極的に推し進めていく。アニメやコミック、アイドルなどエンタテインメント系の新たな分野への展開も図っていく方針だ。
























