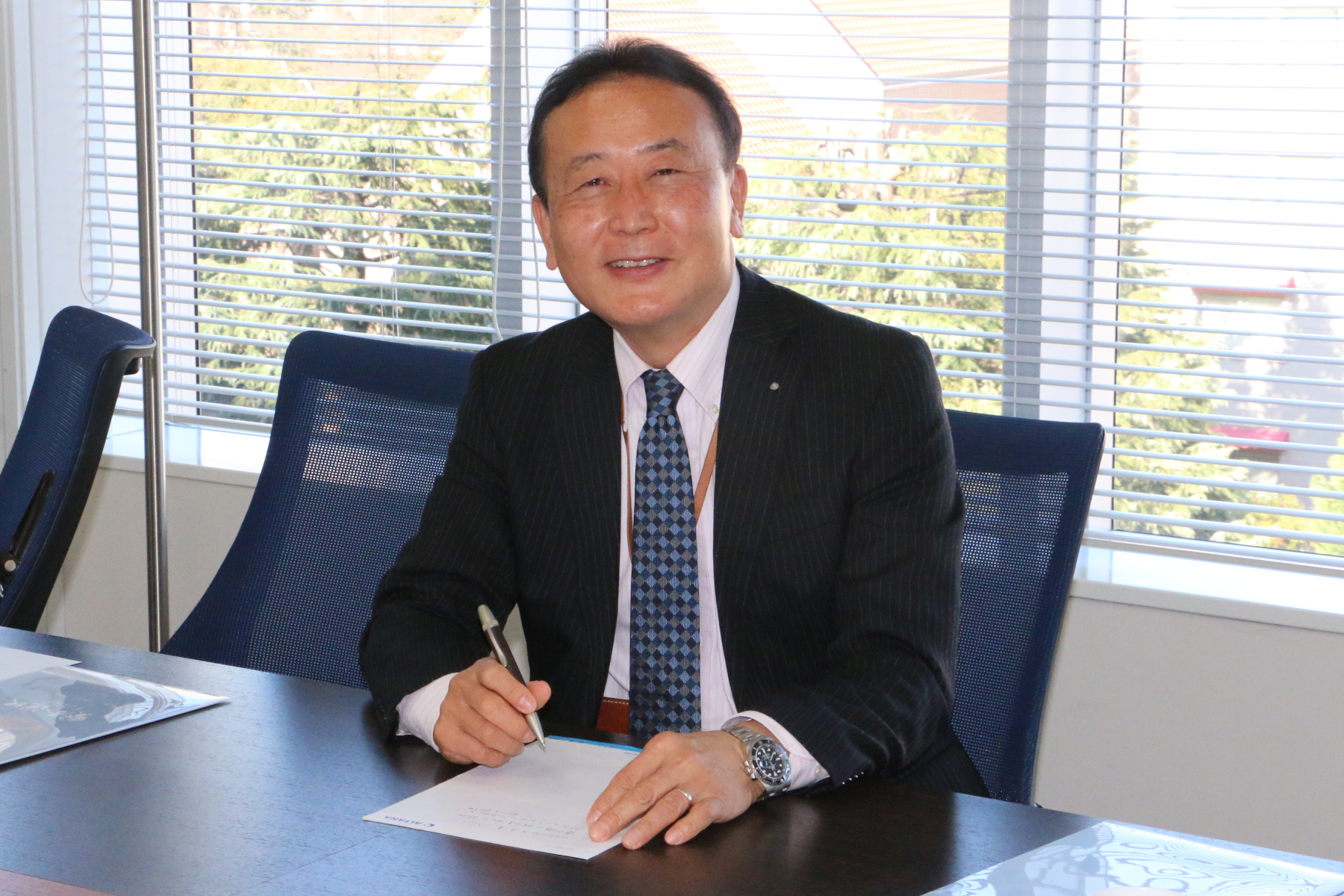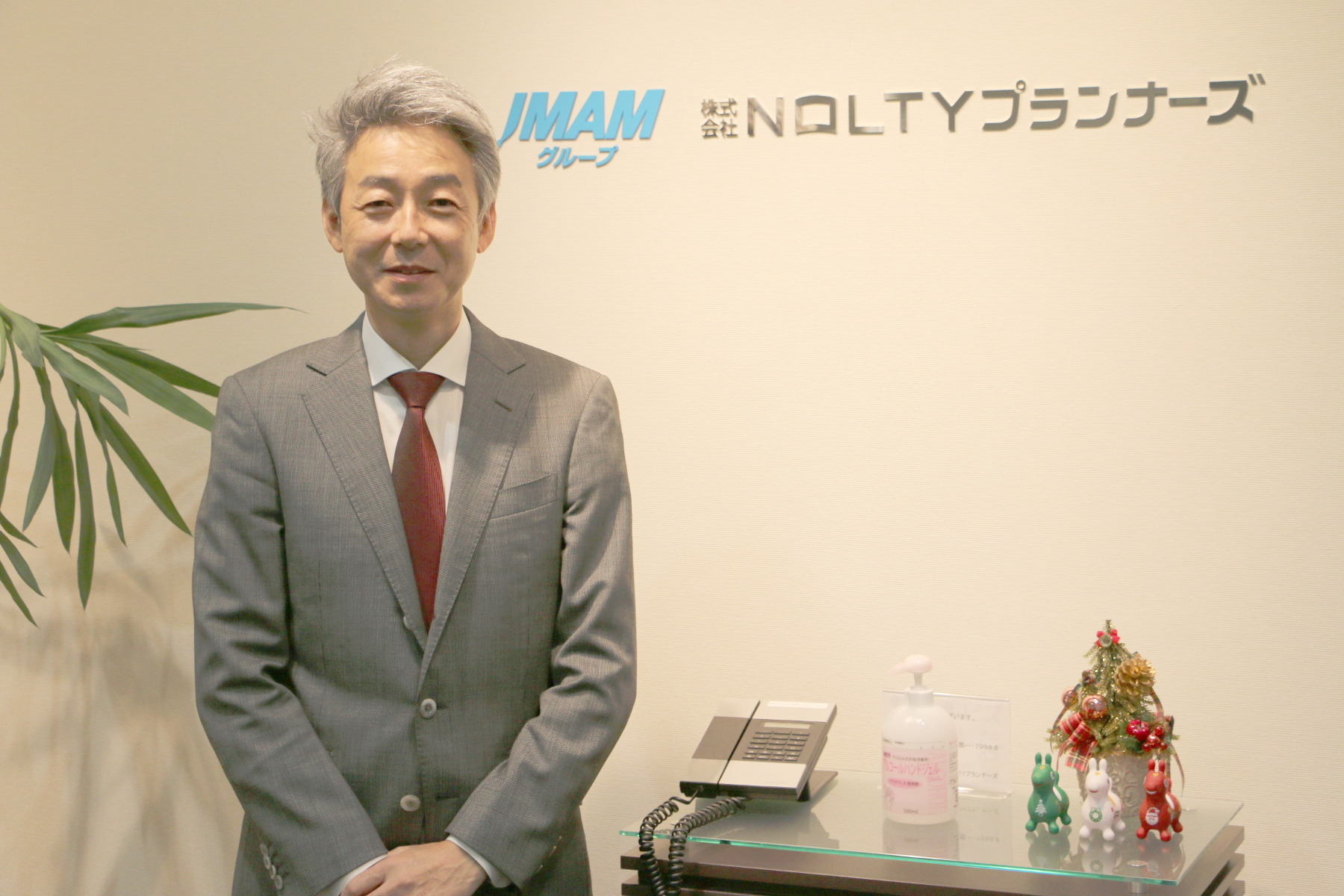インフラを主軸に据えながら
事業領域を拡大してマルチインフラ企業へ
企業単体での躍進はもちろん、グループ企業の増加で成長を続けている株式会社建設技術研究所。2006年には区画整理を主業とする日本都市技術株式会社、2010年に地質調査や砂防・火山・地震防災のコンサルタント企業の株式会社地圏総合コンサルタント、2015年に分析業の株式会社環境総合リサーチ、ビルなどの建築設計を行う株式会社日総建、2017年に建物の設備設計・構造設計、インフラのコンサルタントなどの英国Waterman Group PlcをCTIグループに迎えた。
「今後の経営を中長期で見通したときに、メインを河川・道路などのインフラにしつつも、建築も含めて幅広い業態に拡大することで成長を図ろうという方針です。その手法として、自社で事業を育てると共に、M&Aを推進しています」
CTIグループが目指している方向のひとつはマルチインフラ企業だという。
「マルチインフラとは、河川や道路だけでなく建築・まちづくりなども含め、グループが培った技術ですべてのインフラを包括するものです。さらに、海外展開を図ることでグローバル化し、アクティブ企業を目指す考えです」
公共事業において、新設がいつまでも多くは続かないだろうと同社は見通す。作ったものを維持管理することと、現状に新たな機能や付加価値を与えて再生利用する方向に向かっていくという。
「例えば、ダム再生は、既存のダムをかさ上げしたり、管理方法を変えて治水機能などを向上させることで、災害の発生を抑えようという取り組みです。これは現在の機能に新たな価値を付加するものです。また、道路には自動運転に対応したセンサーを付けるなど、現在の道路や付帯設備に新しい要素を加えることで、多機能道路が実現できます」
最先端の技術として河川管理では水位のモニタリングにAIを活用し、危険水位に達しそうだとAIが判断したら、警告を発する実験も既に行われている。
「ここが建築との大きな違いです。建築は古くなると壊して新しく建てる、スクラップ&ビルドの手法が一般的です。この考えでは、作る、壊すという作業が永遠に続きます。土木の世界は、作ったものをどうやって長持ちさせるかを重視するのです」
同社の事業は約半分が国土交通省など国の省庁。1割が高速道路会社等を含めた民間企業、他が地方自治体だ。今後は民間や地方自治体を含め、多様な顧客をターゲットに掲げて事業分野を拡大する考えを打ち出している。それは、国の事業が縮小傾向になった際のリスクヘッジとしても機能する。
「海外も今後の伸張が期待される分野です。既にCTIグループの株式会社建設技研インターナショナルを中心にアジアへの展開を図っています。今後は英国Waterman Group Plcの技術者とのコラボレーションで拡大を模索しています。まずはアジア、さらにイギリス国内での当社の技術活用、Waterman Group Plc技術を日本に採り入れるなど、さまざまな取り組みを計画しています」
日本と英国には既に長年かけて独自の技術が確立されている。異なる国で双方がどれだけ優位性を保てるかをこれから検証していく計画だ。
「英国では景観を大切にする発想が根付き、ビルの内側だけをリニューアルして付加価値を向上する技術を持っています。日本でも街並みとの親和性など景観に配慮が必要なエリアでは需要が期待できます」
新技術開発と優れた人材の育成に注力
領域が広く深い、社会に貢献できる事業
同社の大きな経営資産は人材と技術力だ。
「建設コンサルタントは工場を持っていません。大切なのはしっかりとした人材育成と、技術開発で新たなシーズを作り出せる力です。業績がやや低迷している時期であっても、まず人材を確保して、社員教育に力を入れました」
それが、業績が上向きになったときに大きな力となり、社員と企業の成長を支えてくれる。
「また、技術も磨かなければいけません。国の事業の発注も価格から技術競争にシフトしてきました。これからは、AIを含めた新技術に対する投資を活性化する必要があります。当社は約10年間で技術投資を倍増させた結果、多くの新規事業を獲得してきました。この取り組みを続けていきます」
しかし、残念なことに土木は理系の学生からの人気がないのだという。
「大きな魅力のひとつは、活躍できる領域が広く、そして深いことです。社会にとって大切なことに取り組んでいると自覚し、誇れる仕事が当社にはあります」
今後、さらに多くの学生が業界を志望し、マルチインフラを通じて一緒に社会の未来を創りあげていくことを同社は望んでいる。