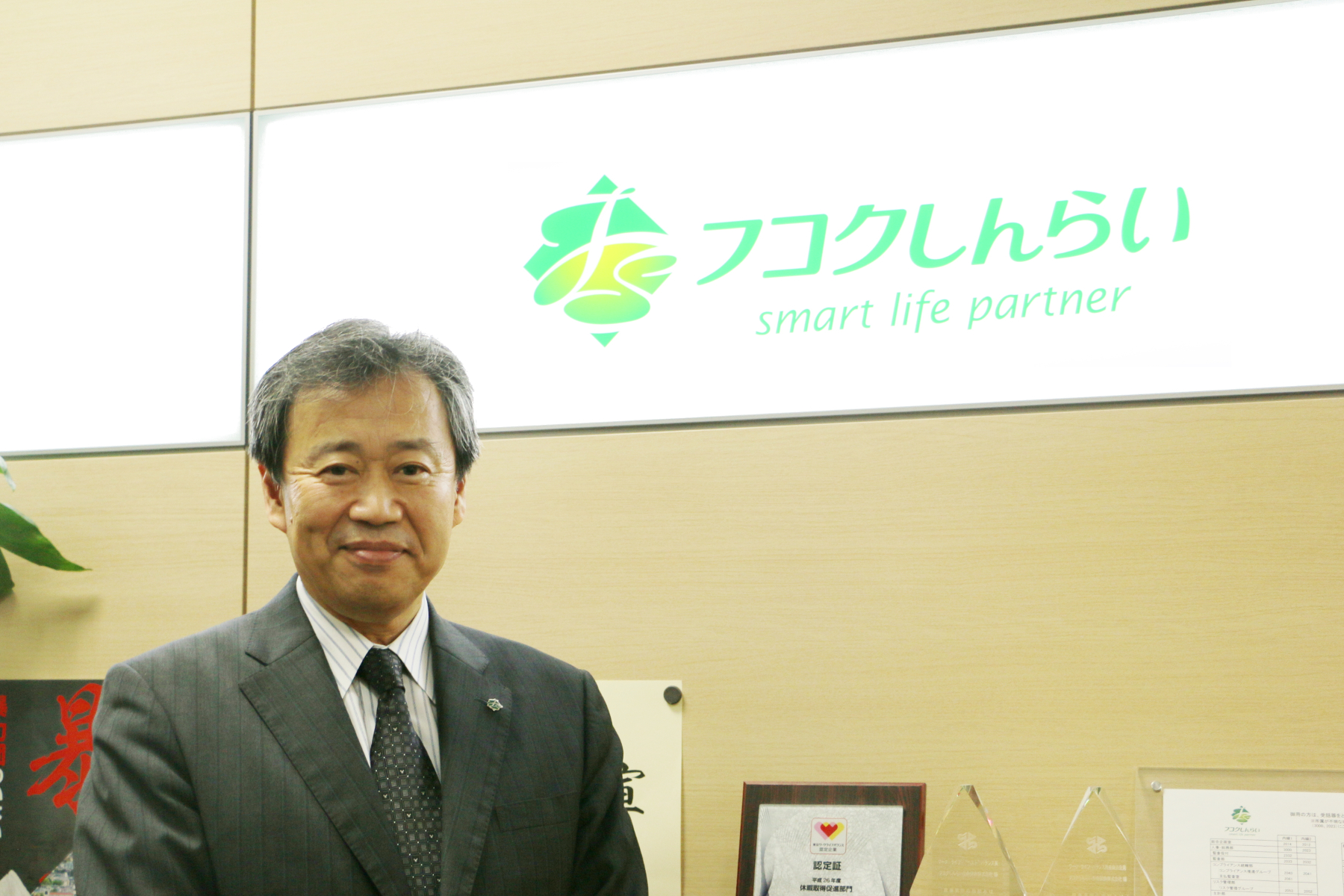ウイルス対策エアフィルターで病院の衛生に貢献
信頼と実績あるフロンティア企業の力を発揮
空調設備機械部、プラント機械部、環境機械部、グローバル事業部の4部門の事業を中心に展開し、成長を続けている進和テック株式会社。なかでも、ホテルや病院をはじめとするビル、工場などの空調用エアフィルターは、同社の取り扱う主力製品のひとつに挙げられる。
「まだ新型コロナウイルスが取り沙汰されていなかった2018年のことです。そこでは今後の病院向けのエアフィルターの今後の方向性について、社内で会議を行いました。今後のトレンドは抗ウイルスか、それとも抗カビか、議論を交わした結果、会社の方針としては「抗カビエアフィルター」を開発することになりました。」
2020年の初頭、中国・武漢で原因不明の肺炎が発生しているというニュースが伝わってきた。
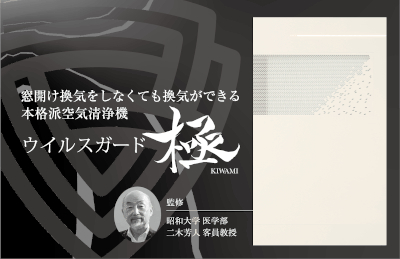
「ウイルスがいずれ日本にも持ち込まれ、感染が広がるかもしれないという情報を受けて、当社も対応策を講じる必要があると考え、上層部を集めて経営会議を開き早急に抗ウイルスフィルターの開発に着手するよう指示を出す予定でした。そこで開発責任者が小声で『実は抗カビエアフィルターの開発を行いながら、こっそりと抗ウイルスエアフィルターの開発実験を行っておりました。来週には正式な試験結果が判明しますが、恐らく他に類を見ない素晴らしい結果が出そうです』と。会議出席者全員が驚きのあまり一瞬の沈黙があり、その後歓声が湧き、開発責任者が褒め称えられたことをはっきりと覚えています。すぐに発売を開始したウイルスを不活性化させるエアフィルターは、従来から取引先だった病院をはじめ、新規の問い合わせや受注も多数あり、現在では多くの施設でご利用いただいております。」
一方ではコロナで大きな影響を受けた業界もある。
「インバウンド需要が一気に消滅してしまいホテル業界は、経費の節減が強いられ、フィルター交換を控えたり、当社への発注が止まったりしたケースもかなりありました。当社は創業以来、赤字になった年はありませんでした。一時は私の代で初めて赤字にしてしまう覚悟をしたのですが、2020年末にはプラスに転じて、苦しい状況ながら、なんとか乗り切れる見通しとなりました。」
同社は以前から、異なる業界と取引していくことで、景況が悪化した業界があっても他の収益でカバーできるという経営方針を示していた。まさに、リスクを回避したバランスのよい企業経営を表している。さらに同社の新型コロナウイルスへの対応は続く。
「時間が経過するとともに、一般的なウイルスに対する効果ではなく、新型コロナウイルスに効果を発揮できるのかが焦点になりました。当社は新型コロナウイルスそのものを使った実証試験を大学との共同研究で進めており、確かな効果があることが判明しています。既に、エアフィルターの濾材に織り込んでいる抗ウイルス剤単体が、新型コロナウイルスを不活性化することは実証されています。現在は、エアフィルターとして利用した際の効果を測っている状況です。」
そこには空調用エアフィルターとしっかり向かい合い、信頼と実績を積んできた企業の姿が見えてくる。
「時代や社会が変化しても、どんな産業であっても、空気中の汚れはなくなりません。当社は長年にわたって対応し続けてきた老舗企業として、どんなご要望にも『お任せください』と答えられる自信があります。」
チャレンジ、チームワーク、ランクアップ
社長就任後に定めたビジョンを全社で実践
2012年に新社長に就任して以降、同社は新たにチャレンジ、チームワーク、ランクアップの3つのビジョンを掲げ、これを実践している。チャレンジの代表例は、海外進出だ。
「マレーシアに工場を新設して海外生産をしています。当初は約90%が日本向けでしたが、現在は約60%を海外向けに提供するまで成長し、世界的にも屈指の規模と生産量を誇る工場になりました。」
チームワークとランクアップは、社内の雰囲気やモチベーションアップに大きく貢献しているという。
「従来は、一人ひとりの社員が個別に働いているという状況でした。例えば、同じ部署で机を並べていても、同じものをそれぞれ別の仕入れ先から異なる金額で仕入れていて、作業員の手配もバラバラの発注でした。チームとしてきちんと情報を共有することで、適正なコストや業務の効率化を図ったのです。さらに、チームにどう貢献したかを評価基準に盛り込み、指導力を向上し、社員全体のランクアップを図ったのです。」
同社のチャレンジは、今後もさらに続いていく。
「空気中の汚れの半分は天然に由来するもの、もう半分は人為的なものと言われています。しかし、誰も汚すことを目的にしているのではなく、豊かで快適な生活を作り上げる課程で、汚してしまっているのです。そこで、私たちは日本の空をきれいにする仕事をしているのです。」
今後はさらに、海外を含め地球規模の環境をきれいにすることが使命だという。同社の活躍の場は、これからも大きく広がる。