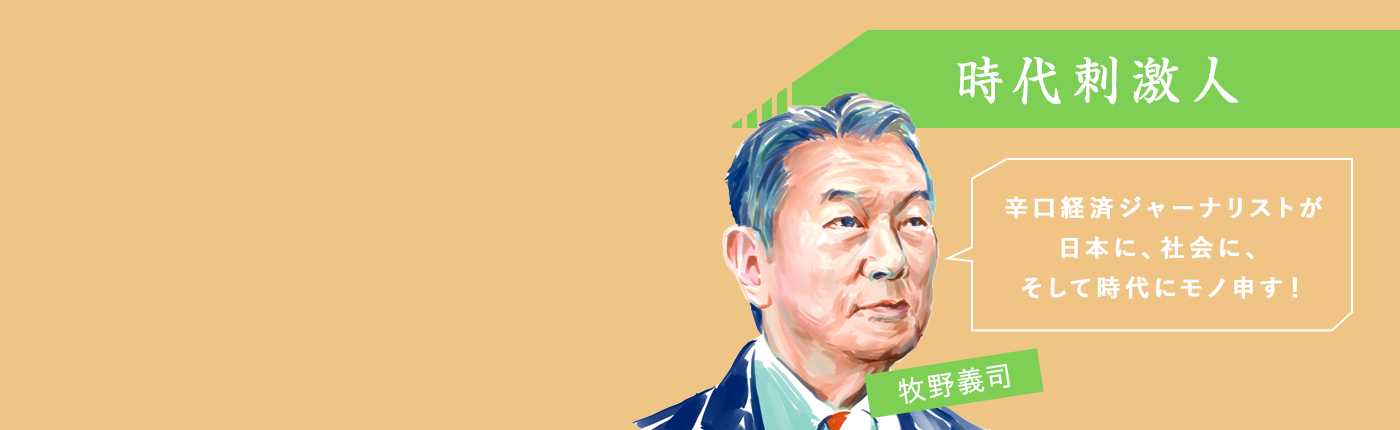
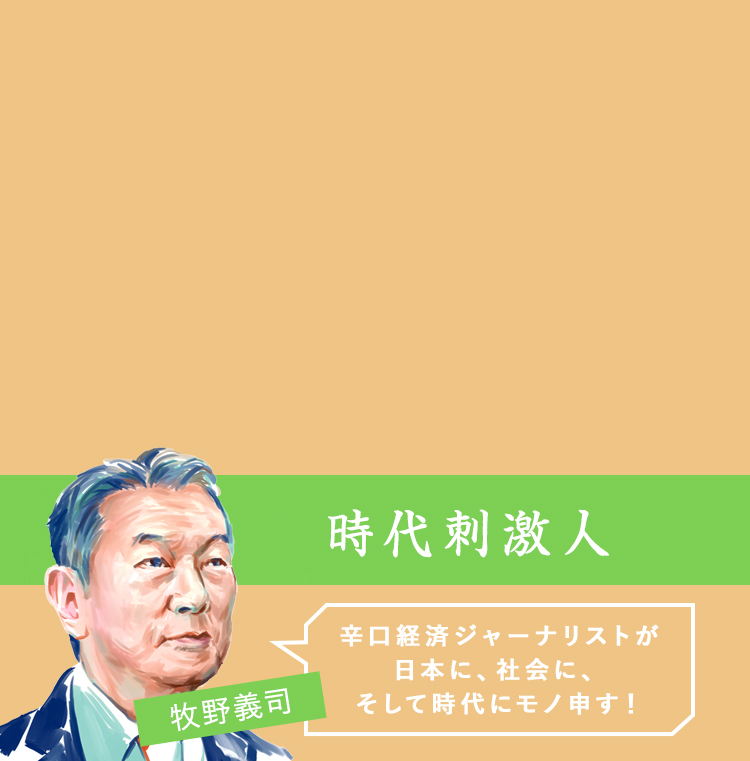

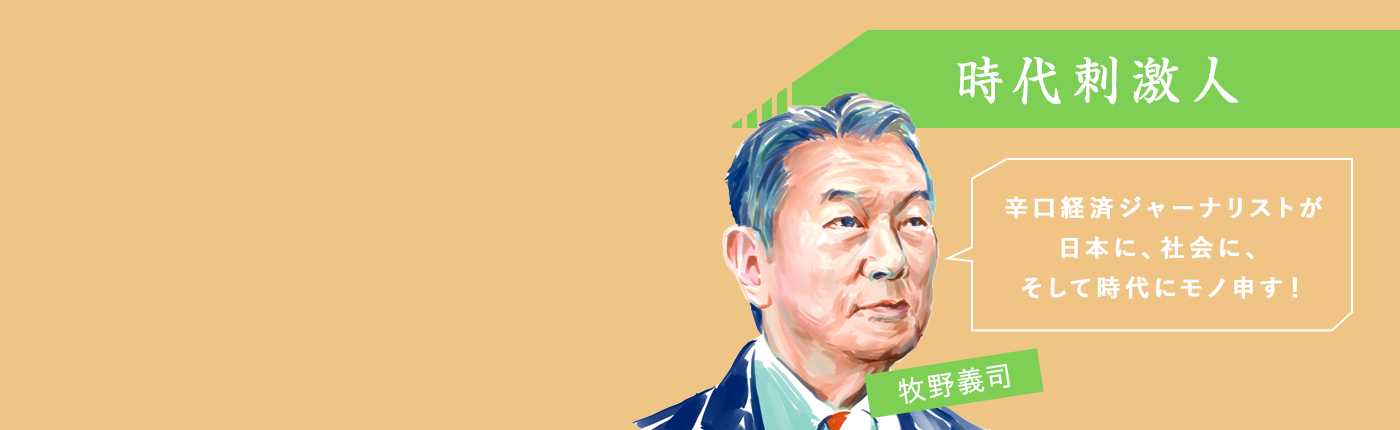
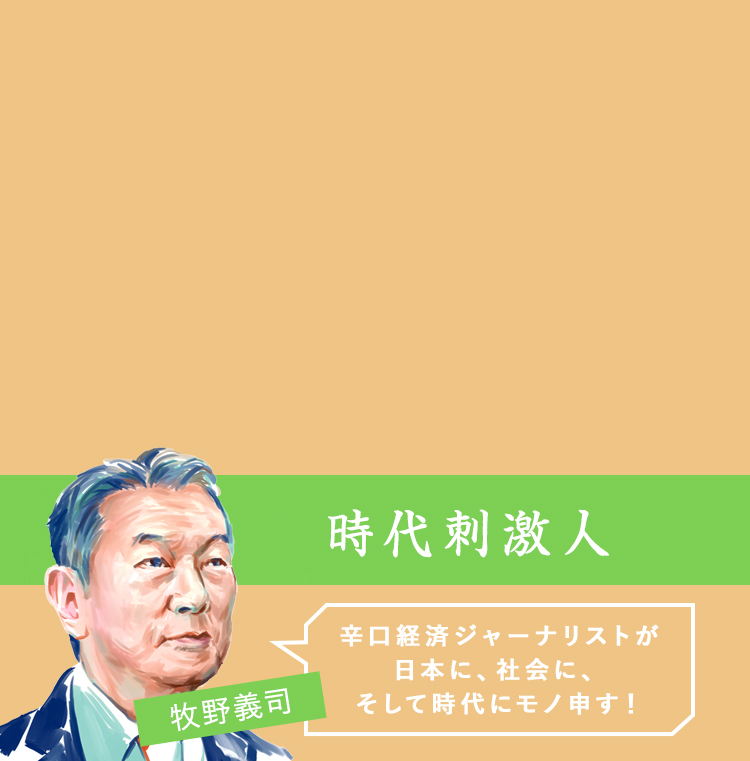

そこへ新たな事態が起きた。ロシアのウクライナ侵攻に伴う戦争の長期化で、原油などエネルギー価格、小麦など食料価格が高騰、各国とも国内インフレ対策が最重要課題になった。主要国の中央銀行は、コロナ禍対応の金融緩和政策から一転、利上げ含みでの金融正常化に踏み出した。しかしここでも日銀だけが、未だに唯一、マイナス金利政策を続けている。
この国際商品高騰と円安がマイナスに働き、日本の輸入物価は上昇、国内物価を押し上げている。この物価高の影響で今年春、企業の一部で起きた賃上げも結果的に実質賃金ベースでマイナスだ。しかし日銀は、景気後退を招きかねない利上げは得策でない、円安是正のために金融政策を変更することはあり得ないーーと、現状の異次元緩和政策を継続中だ。
私から見れば、日銀の政策ジレンマは深刻だ。確かに利上げは難しいにしても、金融政策の正常化、とくに現在の超金融緩和政策の出口政策に関して、政策変更のシグナルを出さないと、異常レベルの円安が続き、国力低下の深みに陥る。率直に言って、2013年からの異次元の超金融緩和政策は政策効果を上げないまま10年になる。日銀はこの際、金融正常化を含め、金融市場に混乱を招かないような出口シナリオを考える重要タイミングに来た、と考える。同時に、政府も金融政策にすべてをゆだねるのでなく、財政政策面で連携が必要だ。
そんな矢先、日米の金融政策ウオッチャーで、野村総研エコノミストの友人、リチャード・クーさんが最近、「マンデー・ミーティング・メモ」というニュースレターで鋭い問題指摘を行っている。「主要中央銀行の中で唯一、日本銀行だけがインフレ対応を拒否してきた結果、円は急落した。円が独歩安になったことで、(中略)ただでさえ力強さに欠ける国内消費をさらに押し下げることになりかねない」「効いているならばともかく、実際は効いていない金融緩和を維持するために、国民生活を直撃する円安を放置している今の日本銀行のスタンスは大きな問題があると言わざるを得ない」「日本銀行はインフレ率がまだ2.1%で、借り手も戻っていない今こそ、金融正常化に向け動き出すべきだ」と。私も同感だ。
日本の国力低下につながる円安という点では、資源価格など国際商品市況高騰による輸入インフレで貿易赤字が大きく膨らみ慢性化するリスクも無視できない。現に、2022年上半期の貿易収支は、半年間としては過去最大の貿易赤字額7兆9241億円になった。ウクライナ問題の長期化が避けられないだけに、貿易赤字の慢性化は避けねばならない。
日本の経常収支は、貿易収支に変動リスクがあっても、日本企業の海外生産や外国企業買収などの対外直接投資、そして外国株式など対外証券投資がプラスに働き、経常収支黒字がベースだった。海外の投資家からは、それが「安全資産通貨」の形で円買いにつながっていた。しかし貿易赤字が慢性化すれば日本円評価が下落し円安を誘発するだけでなく、輸出主導で経済を拡大してきた日本の枠組み自体の見直し、国力低下への対応が課題になる。
関連コンテンツ
カテゴリー別特集
リンク