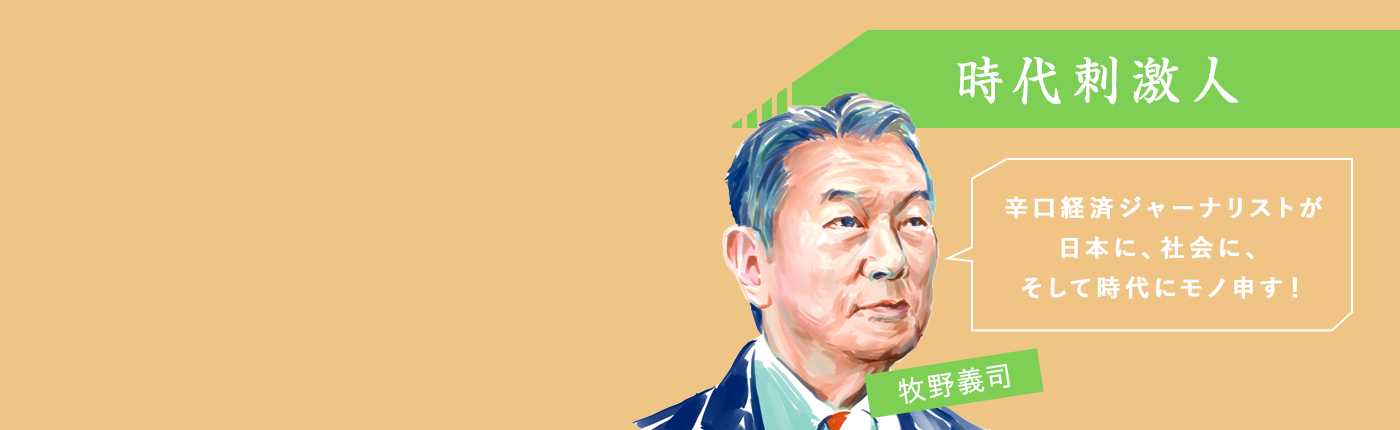
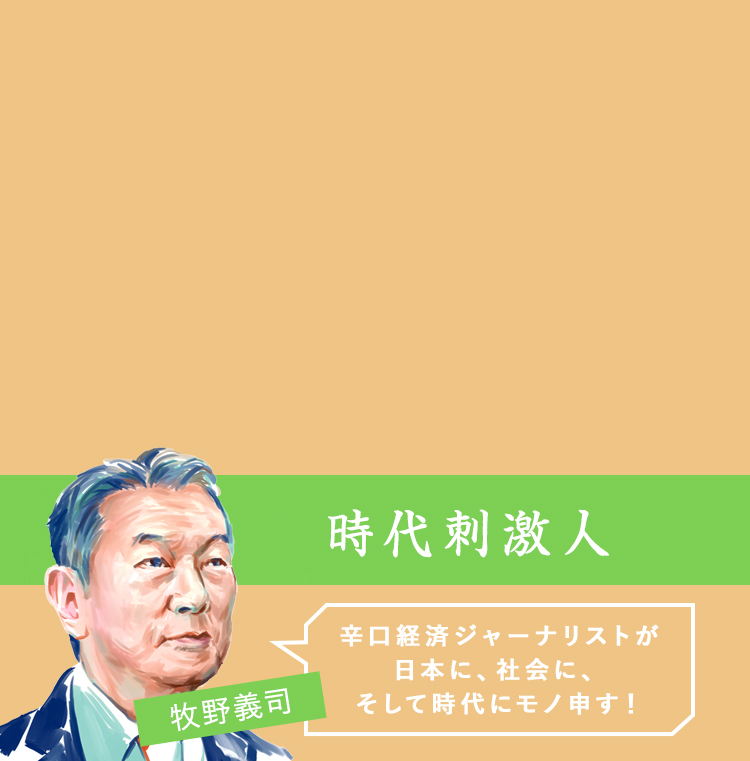

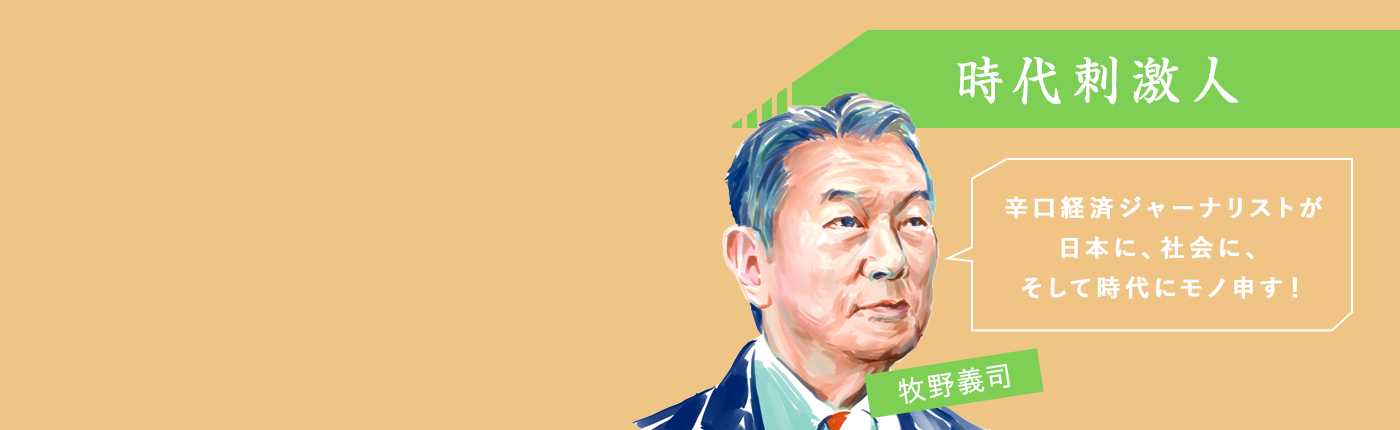
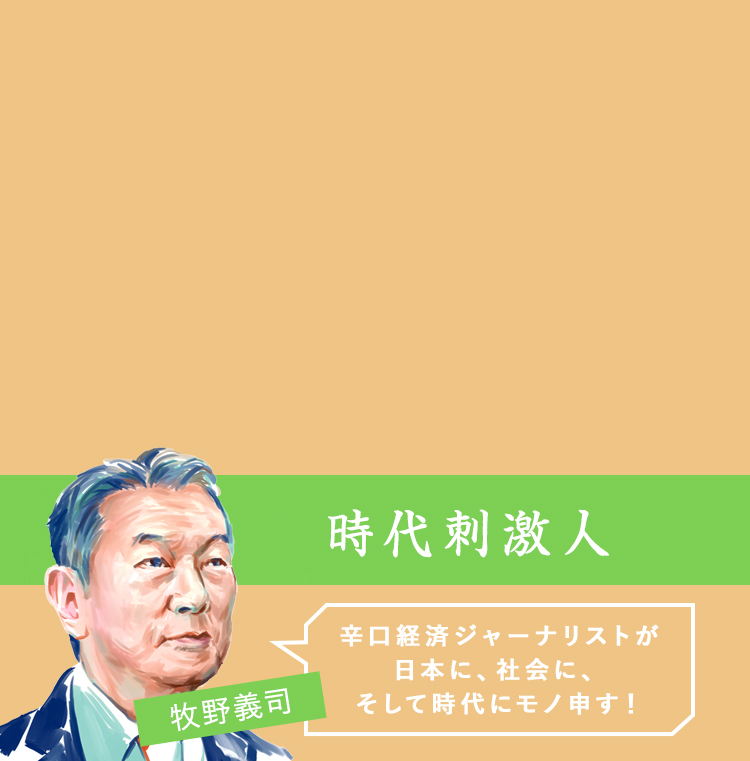

なぜ、こうした取り組みが可能だったのだろうか。先進研究所でR&D(研究開発)を統括する富士フィルム取締役の柳原直人さんの話を聞いていて、「第2の創業」のキーポイントが理解できた。
要は、4象限マトリックス、端的には「既存の技術で既存市場に適用できることがまだ他にないか」「新技術で既存市場に適用できるものはあるか」「既存技術で新市場に適用できることはないか」「新技術で新市場を作り出せるとすれば何があるか」の4分野に分けて徹底的に市場や技術の活用を分析した。その際、既存技術と新技術をヨコ軸に置き、またタテ軸には現在の市場と将来市場を設定し、さまざまな事業可能性を探る分析手法をとった、というのだ。
一見して、当たり前のように見えるが、この分析手法は自身の強み、弱みを見極めながら「第2の創業」の戦略分野を絞り込むには極めて有効だ。
この手法を見て、ふと思い出したのが、大手商社三菱商事の新たな取り組みだ。2018年秋の「中期経営戦略2021」で、多次元分析による事業戦略構築を打ち出した。それによると、事業グループを時代変化に合わせて自動車・モビリティ、複合都市開発、産業インフラ、電力ソリューションなどに再編成すると同時に、それらグループをヨコ軸に、タテ軸には川上・川中・川下を設定してタテ・ヨコから新ビジネスを模索、さらに新設のデジタル戦略部がスタートアップ企業などと提携、商社のビッグデータを活用しデジタルトランスフォーメーションにチャレンジ、そして既存の経営企画部事業構想室とヨコ展開で連携していく、というもの。一方で実力本位の人材掘り起こしの人事改革にも取り組んでいる。タテ割の巨大組織にクサビを打ち込んでの大胆チャレンジだ。
関連コンテンツ
カテゴリー別特集
リンク