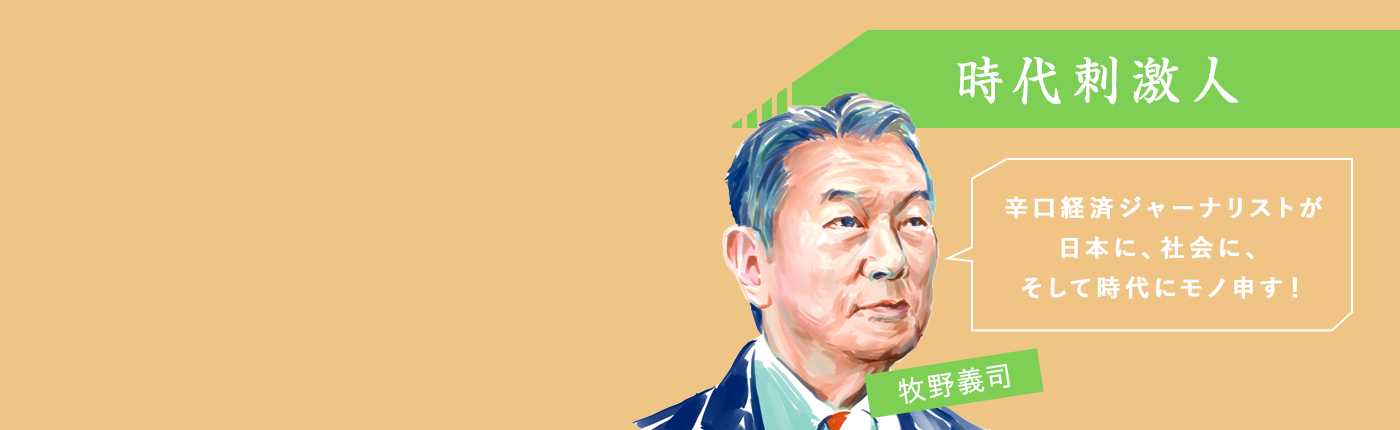

米国でのホンダジェット開発成功にヒント 独創的技術と異文化コミュニケーション力
本田技研工業株式会社

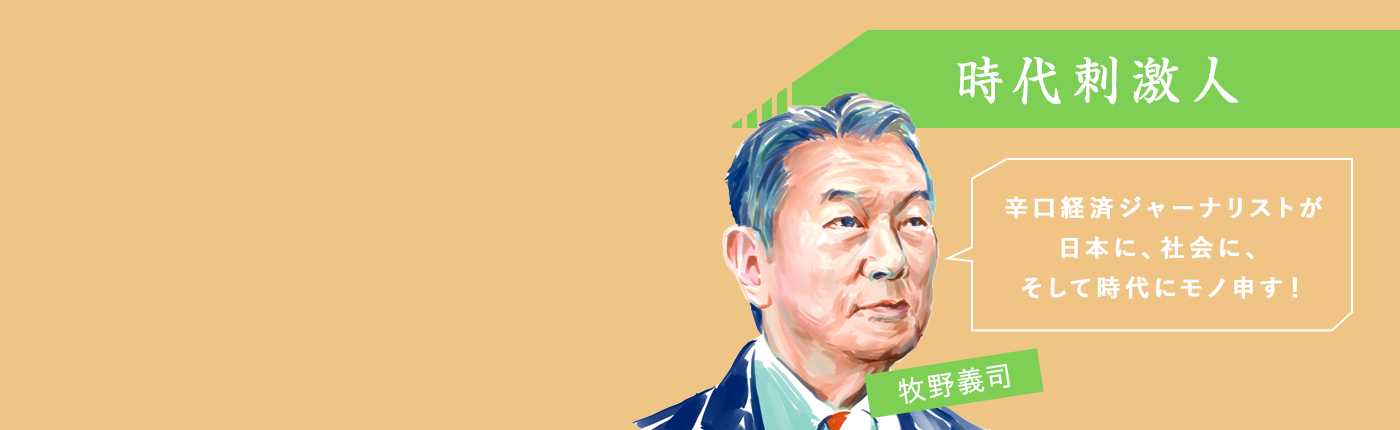


自動車のイノベーションが今、面白い。トヨタ自動車がグループ企業と連携して近未来にチャレンジした「空飛ぶ自動車」開発が話題になったほどだ。しかし私は、同じ自動車メーカーの本田技研工業が航空機開発を手掛けたことに強い関心がある。オートバイから自動車、そして一気に航空機へとチャレンジする点は、モノづくり企業の極みだからだ。
自動車のイノベーションが今、面白い。トヨタ自動車がグループ企業と連携して近未来にチャレンジした「空飛ぶ自動車」開発が話題になったほどだ。しかし私は、同じ自動車メーカーの本田技研工業が航空機開発を手掛けたことに強い関心がある。オートバイから自動車、そして一気に航空機へとチャレンジする点は、モノづくり企業の極みだからだ。
その本田技研の米国法人ホンダエアクラフトが、4年前の2013年、独自開発したビジネスジェット機ホンダジェットをご記憶だろうか。厳しい安全査定で定評ある米FAA(連邦航空局)から航空機として型式認証を得た時には驚嘆した。
安全査定で厳しい米FAAの型式認定得たのはすごい、
三菱MRJとの違い際立つ
とくにFAAは、ホンダが独自開発した航空機について、折り紙付き高評価を与えたという話を聞いて、戦後、日本の航空機メーカーが米国ボーイングなどの航空機下請け生産に終始していただけに、自動車メーカーが全く独自にエンジンを開発、航空機開発につなげたのは快挙、と思った。ホンダジェットは7人乗りのビジネスジェットで、航空機の主力ではないが、スピードや上昇性能、燃費や乗り心地のよさなどが米国を中心にグローバル評価を得て、量産体制に入っているというからすごい。
航空機専業の三菱重工業子会社の三菱航空機は、三菱リージョナルジェット(MRJ)の日本での開発にこだわったが、安全性確保などの面で課題を残し、いまだに型式認証がとれず、「離陸(TAKE OFF)」に至っていないのとは対照的だ。
リーダー藤野さんの来日時講演で苦労話聞き、
グローバル競争勝利の秘訣わかった
実は今回、コラムで取り上げてみようと思ったのは理由がある。最近、そのホンダジェットの開発総責任者でもある藤野道格ホンダエアクラフト社長兼CEOが来日し本田財団で講演した際、開発当時の苦労話を聞くチャンスがありワクワクすることが多かった。それと同時に、藤野さんの話を聞いていて、ジャーナリスト目線で、日本企業がグローバル市場で勝つポイントがあるな、というヒント部分があったため、レポートしようと考えた。
そのポイントは、企業がグローバル競争をする場合、積極的に競争現場の主戦場にあえて臨み、激しくもまれながら競争に勝つための大胆な取り組みを行い、誰もが高い評価を下してくれる実績を示すことが必要、という点だ。要は、日本を拠点に、日本仕様の完成品をつくって世界に打って出る、という発想でなく、最初から主戦場で競争することだ。
オンリーワン技術武器にソフトパワー駆使、
日本でなく米国主戦場での競争が重要
もう少し具体的に申し上げよう。ホンダジェットの場合、航空宇宙工学専門家の藤野さんがすべてのキーパーソンだ。経営のトップに立ち、2つのソフトパワーを駆使した。
1つは、藤野さんが、グローバル市場で勝ち抜くためには、ライバル企業と同じものをつくるのではなく、オンリーワンと言える独創的な技術による新機種開発が必要、としたイノベーション力のすごさ、そして主戦場はビジネスジェットの本場、米国と決めたこと。もう1つは、藤野さんが30か国に及ぶ国々の技術者1800人を巻き込み、異文化コミュニケーション力を駆使して組織を動かしたダイナミックな指導力だ。
藤野さんの話で最もすごいと思ったのは、独創的な技術開発へのチャレンジ、イノベーションに対する執念だ。藤野さんは「ビジネスジェットに新規参入するホンダが他のメーカーと同じようなものをつくって意味があるのか、と自身に問いかけを行った。そして、あえて独自の発想、イノベーションで行くことにした」という。その最大成果が、航空機エンジン開発関係者の「常識」を打破した主翼の上の部分へのエンジン取り付けだ。
ホンダジェット強みは米航空機業界の
「常識」打ち破る主翼へのエンジン取り付け
「現行のビジネスジェットは胴体後部にエンジンを取り付ける設計だが、もし主翼にそれを取り付けることができれば、エンジン支持構造を胴体後部から排除でき、胴体内の客室キャビンなどのスペースの最大化が可能になる。キャビンが小さく騒音も大きい、といった現行設計のディスアドバンテージをアドバンテージに変えることができる。そうすれば評価も高まり、市場ニーズに応えられると考えた」と藤野さんは言うのだ。
航空業界の「常識」に対して、後発の自動車メーカーがその「常識破り」に挑戦したい、というのは、後発だけに、その気持ちがあるのは当然だ。問題は、それを実行に移すことだが、それをやり遂げたのだから、そのイノベーションへのチャレンジには脱帽だ。
本田技研が社内でも極秘に航空機研究チームを立ち上げたのが31年前の1986年。飛行機づくりに強い夢を持っていた創業者本田宗一郎氏(故人)にもチーム立ち上げをいっさい知らせず、藤野さんがたまたま研究所を訪れた本田氏にトイレでばったり出会った際も、守秘を通す徹底ぶりだった、という。
本田技研のイノベーションへのチャレンジが
開発パワーの源泉?藤野さんは実行
本田技研が航空機開発に関して、徹底した秘密主義を貫いたのは、チャレンジして失敗した場合の外部の冷ややかな対応や評価を嫌ったのか、独自技術、言ってみれば「秘伝のタレ」の中身が外部に漏れるのを避けるためだったのか、そのあたり定かでない。
しかし藤野さんは開発に取り組んだ10年後、主翼の上にエンジンを取り付けるコンセプトスケッチを描いた。事業化までの時間はさらに長かった。藤野さんによると、空気力学と空力弾性学の両面から技術的チャレンジにぶつかることはわかっていた。とくに主翼上面へのエンジン配置は、好ましくない空力干渉や強い衝撃波を引き起こし、抵抗発散マッハ数を低下させるため、その克服が課題だった、という。
講演でのチャレンジ話は専門的過ぎて、私にはなかなか理解できない部分が多かったが、数々のコンピューターシミュレーションなど試行錯誤を経て難題を次第に克服していく。米航空宇宙局(NASA)研究施設やボーイングの施設を借りての風洞試験から「ヒョウタンから駒」状態にぐんと近づいていくあたりの話は苦闘ぶりが伝わってきて興味深い。
冷ややかだった米国も次第に技術力を評価、
イノベーションへの好奇心の表れ
だが、藤野さんの話で興味深かったのは、主戦場となった米国での動きだ。「米国の学会は、私の新技術開発に対する関心度が高かった。私が研究論文を出したら、普通ならば論文評価に1年以上かかるのに、何と3週間で回答が来て、専門家の間でも認められるようになった。スピード感がすごい」という。イノベーションに対する米国の好奇心の強さだ。
現に、航空エンジン開発現場から一転、航空機ジャーナリストに転じた前間孝則さんの著書「ホンダジェット――開発リーダーが語る30年の全軌跡」(新潮社刊)によると、藤野さんはボーイングの研究施設を借りて遷音速風洞という音速前後のマッハ数を実現する風洞試験を行った際の時のことを、前間さんにこう語っている。る米国の好奇心の強さだ。
「最初、ボーイングの技術者たちは、われわれのコンセプトを見て馬鹿にしているような様子で、『まあ、やってやるか』といった受け止め方でした。でも試験を進めていく中で、データが出てくるに従い、その態度が変わってきて、彼らも認めざるを得なくなりました」と。この評価態度の変わりぶりは、安全性評価判断を下すFAAも同じだったようだ。
米現法開発現場で30か国1800人の技術者、
人材や組織を自由に動かす指導力
私の見るところ、米国は軍用機、民間航空機を含め技術開発力などで航空機先進国の自負が高い。ところがエンジン取り付けの常識を覆す藤野さんの自然層流翼などの考え方に対し、米国は最初、冷ややかだったが、試験結果を見るうちに、その開発発想や着想のすごさに驚き、次第に畏敬の念となり、最終的に高評価へとなったのは間違いない。その点でも藤野さんが米国のジェット機開発の主戦場で勝負した意味が十分あった、と言える。
もう1つの異文化コミュニケーション力に関しても、講演時に紹介されたビデオ映像が象徴的だった。FAAからの型式認定を得た時の米国現地法人ホンダエアクラフトの開発現場では30か国の多国籍社員が手を取り合って喜び合う姿が映し出された。なかなか感動的だったが、日本企業がグローバル市場で生き残る秘訣はこのあたりだな、と感じた。
藤野さん
「ホンダジェットは安易に海外企業に頼らずホンダ自身でつくった自負」
現に、前間さんの著書の中で、工場で主翼製造の責任者を務めるある米国人エンジニアは藤野さんを「ボスはとっても緻密で、知識も豊富だ。彼のために働くのはとても気持ちがいいよ」と語っている。この動きを見ても、私は、ホンダジェットの成功は、藤野さんの航空機エンジンの常識を打ち破る独創的な技術力が第一義的にあるが、同時に、多国籍の技術人材や組織をダイナミックに動かせた藤野さんのリーダーとしての指導力と思う。
それにしても本田技研工業は面白い会社だ。中でも、創業者本田さんは日本でベンチャー企業が育ちにくいと言われる中で、イノベーションに情熱をもって取り組んだ草分け的な存在だし、その精神が引き継がれて藤野さんのようなリーダーを輩出させた、と言える。
藤野さんは、前間さんの著書で本田技研の社風について、こう述べている。
「研究開発のやり方は、おそらく普通の飛行機会社ではできないでしょう。なぜかというと、開発の途中で万一、新しいアイデアがダメだったとなると、一からやり直しになり、膨大な開発費が無駄になってしまい、最悪、開発を諦めることになるでしょう」
「すべての基本設計は全部、ホンダの中でやってきました。その意味で、ホンダジェットは、安易に海外の専門サプライヤーなどに頼ることなく、文字通りホンダ自身でつくった機体だ、と胸を張って言えます」
東芝はアングロサクソン企業をマネージできなかったが、
独自技術力などで克服可能
ホンダジェットの開発成功にからむ話は、いろいろな切り口がある。端的には第2次世界大戦の敗戦国日本はドイツと同様、連合国、とりわけ米国から航空機開発の開発製造を禁止され、終戦から7年後の講和条約発効後も一種のトラウマ状態でYS11など一部の自主開発機を除き、米航空機メーカーの下請け生産に甘んじてきた。そういった中で三菱飛行機MRJの問題とは別に、ホンダジェットの独自開発は、もっと掘り起こすチャンスだ。
だが、私は今回、藤野さんの講演を聞いていて、オンリーワンの独自技術開発の重要性、それと主戦場で異文化コミュニケーションを発揮してグローバル企業挑戦をすることが日本企業のグローバル戦略のポイントと感じ、メインテーマにした。
その点で、東芝が米原発メーカーのウエスチングハウスを巨額資金で企業買収しながら、肝心なところでコントロールできないどころか、損失をかぶらされて手痛い打撃をこうむったのとは対照的だ。「日本企業はアングロサクソン企業をマネージできないのか」と言われてもやむを得ない事態だが、ホンダジェットの場合、それらを克服した。
藤野さんに講演後、東芝のウエスチングハウス経営の問題点を聞いてみたところ、「他企業の経営をコメントする立場にない」としながらも、「厳しい競争が進行する米国を主戦場にして企業経営を行う場合、最大のポイントは独自技術力、それにイノベーションに裏付けられた長期ビジョン力をしっかりと持つことだ」と語った。確かに、鋭いポイントだ。
関連コンテンツ
カテゴリー別特集
リンク