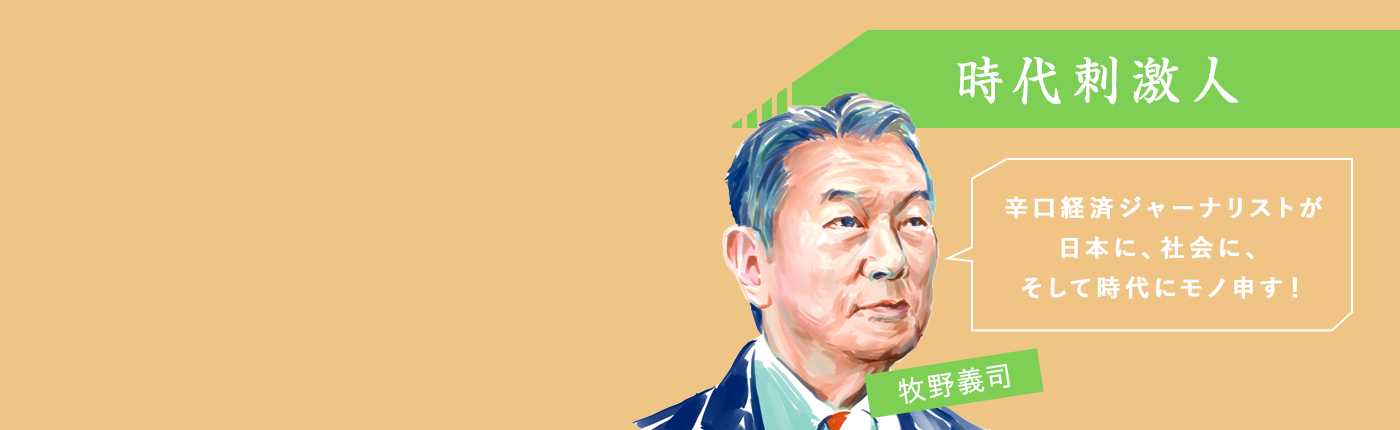


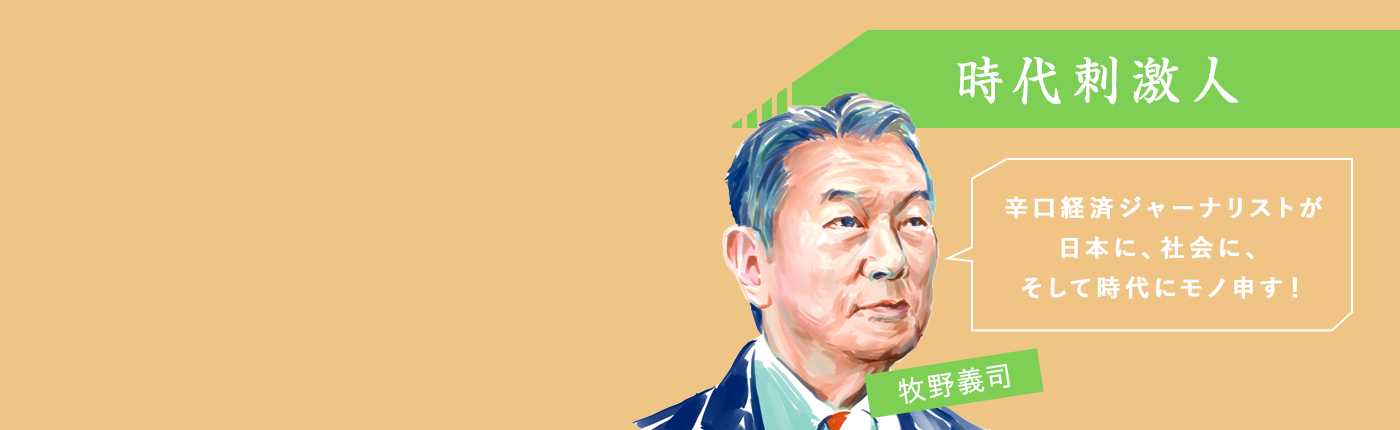


全国展開する大手新聞社を含めて、今や厳しい競争にさらされる新聞、テレビ、雑誌などさまざまなメディアは生き残りをかけ必死だ。そうした中で、地方紙ががんばって、それなりに存在感を見せているので、今回、ぜひ取り上げてみたい。地域に現場を持ち、そこに大きな根っこを張って取材する地方紙が今後、さまざまな地域課題の掘り起こしだけでなく課題解決に向けて地域全体を巻き込んだ取り組み提案を行うなど、ガンバリズム(がんばるということが成果を生みだすという発想)で力を発揮してほしい。
実は、私は農業の現場でさまざまな取り組みをすることによって、日本農業の新たなビジネスモデルになる、言ってみれば先進モデル例となる人たちを毎月、取材している。その関係で日本全国に出かける。それぞれの地方に行くと、元毎日新聞記者だったジャーナリストの好奇心や問題意識もあって、必ず地方紙を手にする。最近訪れた新潟でも地元の新潟日報を読んだが、東京では得られない地域の抱える問題や課題を知って、とても勉強になった。
新潟日報の企画記事、地域の抱える課題などを描きとても勉強になった
その新潟日報記事のうち、1面企画「にいがた着」で、たまたま上越市古川区坪野の集落に首都圏から移住した人たちが、地元の人たちと一緒に「道普請(みちふしん)」という作業に携わる話を取り上げ、よそ者と見られていた人たちが今やすっかり地域集落の人たちと同化、地域再生に向けて互いに協力し合う問題を取り上げていた。
この道普請は、毎年11月末ごろ、集落を流れる水路や側溝にたまった大量のブナの落ち葉をかき出す共同作業だ。放置しておくと、春の雪解けのころに、山から流れ出す水が側溝などであふれ出して道路が水びたしになりかねない。それを防ぐため、雪が本格的に降りだす前に共同で作業するのだが、都会への流出などで人口減少が進む集落に移住してきた都会の人たちの姿を描きながら、地域の抱える課題を取り上げているのだ。
長く東京に住んでいる私にとって、人口減少が進む地域集落の大変さは頭でわかっていても、現場の厳しい現実は把握できていない。それだけに、こうした地元紙の記者が現場に入って、現状をレポートするだけでなく、課題の解決によって地域の再生につなげるには何がポイントかを発信しているのを見て、メディアの役割を自覚して報道する地方紙を心強く思った。
地方紙記事を収録した「日本の現場――地方紙で読む」はなかなか読みごたえ
この新潟日報の企画記事で、私はふと昨年2010年9月に発刊された「日本の現場――地方紙で読む」(株式会社旬報社刊)という本のことを思い出した。この本は、北海道新聞記者の高田昌幸さんと昭和女子大学人間社会学部教員の清水真さんの2人が編集したもので、日本全国の地方紙の連載企画を中心に、鋭く掘り下げたルポ主体の記事、調査報道記事などのうち、優れた内容のものを収録している。ぜひ読まれたらいい。なかなか鋭く、しかし味わいのある記事が多く、それぞれの地域で抱える課題や問題を新聞記者の目線でしっかりと描いている。地方紙の記者もがんばっている、頼もしいなと感じた本だ。
編集者は冒頭の「はじめに」でこう書いている。「地方紙がよくて全国紙はよくないとか、そんな話ではない。『地方紙の優れた記事を全国の人に読んでもらいたい』、『東京発信の記事では見えてこない、地方の実情、すなわち日本の現場を知ってもらいたい』という、極めてシンプルなものだ。『地域』、『地方』は単なる地理的な概念を指しているのではない。東京にも大都市圏にも『地方』はあるが、いろいろな地方紙を読み込んでいくと、各地域の固有の問題が、実は日本のあちこちで起きているのだ、ということがわかる」と。
輪島塗のモノづくり現場がルイ・ヴィトンと連携し地方区から一気に世界区へ
経済ジャーナリストの目線で面白いと思った記事があった。石川県に本社を置く北國新聞で2008年1月に掲載の「能登が揺れた――ルイ・ヴィトンとの出会い」という企画記事だ。輪島塗の桐本木工所と世界的な高級ブランド、フランスのルイ・ヴィトンが連携して共同で仕上げた小物ケース「ボワット・ラケ・ワジマ」が話題になり、200個の限定販売だったのが、思わぬ反響で取扱い数の5倍近い予約殺到となったこと、世界的な高級ブランドが価値評価してくれ、その連携で輪島塗が一気に世界ブランドとなって世界の消費者に注目される可能性が高まったこと、能登地震で一時、壊滅的な影響を受けた輪島塗の現場がまた再生のきっかけになったことなどが克明に描かれている。
私の興味は、日本のモノづくりのこだわりの技術が、ちょっとした国際ブランドとの出会いで一気にブランド価値を高めたという点だ。コラム107回で取り上げた韓国のグローバル企業サムスンの国際的なマーケット戦略の話で気付かれたと思うが、サムスンは日本のエレクトロニクス企業と比べて技術開発力や生産性の低さで弱みがあると判断し、逆に「表の競争力」であるマーケッティング、ブランド売り込みで戦略的なアクションをとり見事に成功した。今回の輪島塗の木工所に限らず、モノづくり技術で突出する力を持つ地方企業でも、戦略次第では十分に日本の地方区から一気に世界区に躍り出ることが可能、ということだ。そんなヒントを得ただけでも、この北國新聞記事はとてもプラスだ。
岩手日報「SOS地域医療」、南日本新聞「故郷かごしま地域再生」など重厚企画
「日本の現場――地方紙で読む」の本のうち、企画記事タイトルだけを取り出しても、たとえば岩手日報の「SOS地域医療」、岐阜新聞の「命をつなぐ――岐阜の医療の現場から」といった地域医療や高齢化社会の介護、福祉の抱える問題から、南日本新聞の「故郷かごしま地域再生――担い手の形」、高知新聞の「500人の村がゆく」といった地域再生などの問題まで、さまざまな現場の実態を知ることが出来る。とても貴重な問題提起集だ。
この本を読んでいて、もう1つ、参考になったのは「ネット時代の地方紙」という関連コラム記事だ。読売新聞記者を辞めて、今はインターネットのポータルサイト「ヤフー・ジャパン」でメディア編集部長の奥村倫弘さんが書いている。
ネット時代に地方紙情報は世界中に、戦時中の供給先行型の伝達情報と大違い
要は「インターネットのすごいところは、都道府県や市町村という枠を越えて世界中を情報が行き交うことです。沖縄県のニュースが北海道にいながらにして読め、ニューヨークで四国4県のニュースが読めるのです。こんなことは、10年前には考えられなかったことです。そこには中央と地方という対立軸で語られる『地方』ではなく、広い地域としての『地方』があります。その地方からの情報発信を追求していきたいです。個人ホームページやブログに代表されるネットメディアから発せられた地域や個人の小さな声がいつの間にか大きなうねりになって全国に届くようになっています」という点だ。
地方紙が1県1紙体制になったのは、太平洋戦争中に軍部・大本営が全国紙とは別に、各県・各地域に軍部の意向を伝え戦争指導するツールとして活用するためだったと聞いている。その地方紙は、戦後の長い間、地域の土着権力化して、つくればモノは売れるという供給先行型成長パターンにならって情報も供給サイドの発想、中央の政治や行政の情報伝達役を担っていたが、今や、そこが大きく変わってきた、ということだろう。
信濃毎日新聞論説主幹・中馬さんの「狩猟型と農耕型」取材の指摘は興味深い
朝日新聞の政治部記者を経て論説主幹まで昇り詰めた中馬清福さんが現在、信濃毎日新聞主筆に転じて新聞の現場にこだわっている。新聞記者OBとして、素晴らしい生き方だと思うが、この中馬さんが、オピニオンリーダー向け「ジャーナリズム」誌2010年4月号の「地方報道の可能性」という特集の中で、「地方報道はどうあるべきか――『狩猟型』と『農耕型』取材を考える」と題して、なかなか興味深い指摘をしている。引用させていただこう。
東京で政治や行政の中枢を取材対象にしている全国紙の新聞記者、地方の現場取材に走り回る地方紙の記者との差をうまく浮き彫りにしている。「東京から現地を訪れて取材するにしても、さっと来てさっと帰る、いわゆる『狩猟型』である。厄介なのは、たまにだが、思いこみ先行、事前に『枠をはめて』取材に乗り込む記者がいることだ。中央での取材や読書で得た知識をもとに『こうあるべきだ』と考え、それに合った方向へ持っていこうとする。これでは正しい姿は描けない」という。
中馬さんの話はさらに続く。「地方紙はそうはいかない。(たとえば)町村合併で、旧町村部は行政と住民の連帯が弱まり、周辺部の衰退が進んでいる。それが地方の記者にはよく見える。それはそのまま暮らしに直結しているから、(全国紙記者が往々にして書くような町村合併歓迎の記事と違って)大合併が一段落したあとも、なお新しい問題(としてフォローアップを続ける問題)なのだ。地方紙は『農耕型』の取材でないと、読者に相手にしてもらえない」と。
中馬さんはいま、信濃毎日新聞をベースに仕事をしておられるので、『農耕型』取材の必要性を強調し、地方紙の存在感はその取材方法で出てくる記事、情報発信だ、ということは言うまでもない。
地方紙、全国紙とも取材力ある人材の戦略的補強を、人材の流動化が重要に
私は、この中馬さんの話に関連して、考えたことがある。地方紙には優秀で問題意識を持って取材にあたる人も多いと思うが、地方紙は今後、鋭い問題意識をもとに取材力や情報発信力がある現役記者やOB記者を全国紙からスカウトや中途採用で陣容を豊富にすればいい。同時に、問題意識、それにいい意味での上昇志向の強い人は全国紙でチャレンジしたらいい。私自身、毎日新聞からロイター通信に転職して、さまざまな勉強をすると同時に、自分の生き方に広がりを感じた経験を踏まえれば、全国紙と地方紙で人材の転職を含めて流動化の道筋をもっと大胆につくればいい。同時に、年俸制で、仕事の評価システムも厳しくして、戦略的に弱い取材分野があれば躊躇なく外部から戦力人材をとるような経営手法をとることで、地方紙はすごい存在感があるイメージを作り上げることだ。信濃毎日新聞はまさにそういった狙いもあって中馬さんを引っ張ったのでないかと思う。
地方紙の若手の優秀な記者をスカウトするというのは、全国紙、とりわけ朝日新聞がかなり以前から行っていることだが、朝日新聞は、そのおかげで、下野新聞から引き抜いた板橋洋佳さんという記者の取材力が功を奏し、2010年度の日本新聞協会賞を受賞している。私に言わせれば、こういった形での人材の流動化は、私がいたロイター通信にとどまらず、外国メディアでは当然のこととなっていた。地方紙、そして全国紙も人材の交流、あるいは中途採用で優秀な人材採用によって、常に組織の活性化、取材力の強化を図ることで、ニュース報道のみならず分析報道、調査報道、さらには政策提言報道まで、戦力活用の成果が及び、存在感が強まって来ると考える。とくに地方紙は地域課題の掘り起こし、課題解決への取り組み提案では今後、重要な役割を担うべき時期に来ている。
関連コンテンツ
カテゴリー別特集
リンク