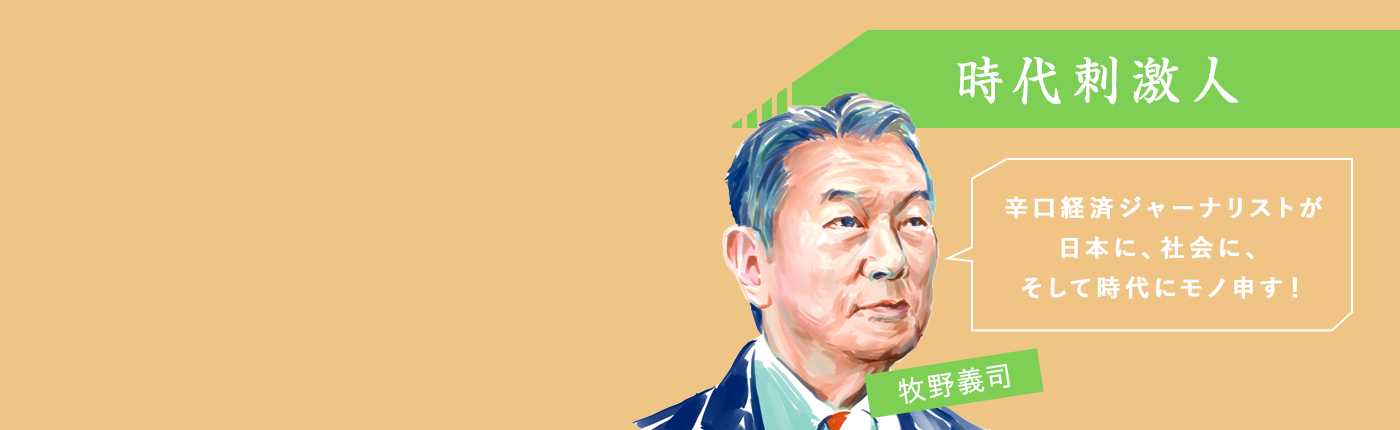


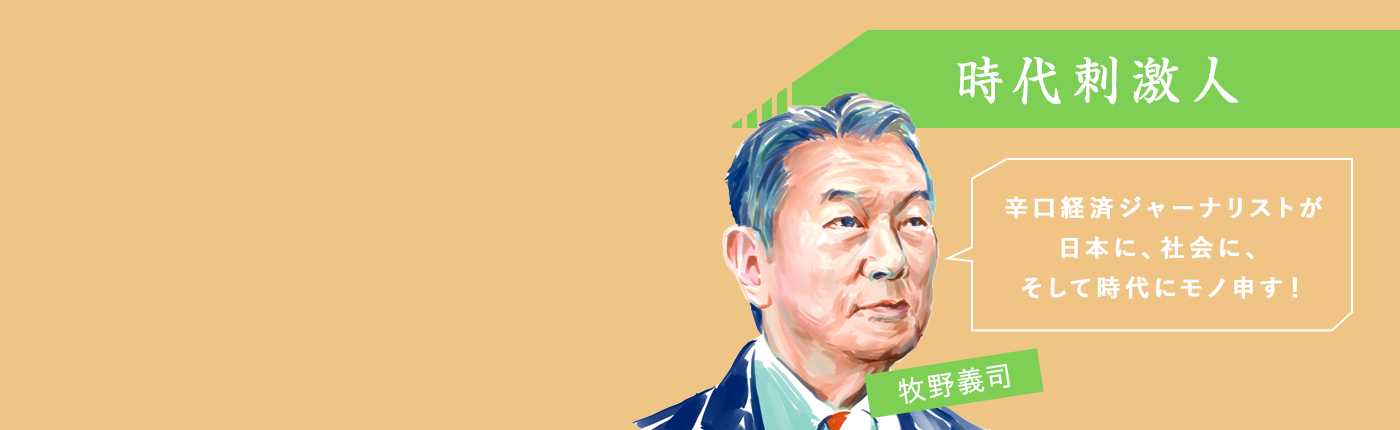


時代の先を見据えて、面白い構想力で小説を書き、しかもその小説の中身が10年後に現実の世界にぴったりとあてはまる、ということがあったとしたら、その作家って、すごいな、と私のみならず、誰もがそう思うだろう。
時代の先を見据えて、面白い構想力で小説を書き、しかもその小説の中身が10年後に現実の世界にぴったりとあてはまる、ということがあったとしたら、その作家って、すごいな、と私のみならず、誰もがそう思うだろう。
それに関連する話が最近の月刊文芸春秋誌7月号にあった。石破茂地方創生担当大臣と作家の楡周平さんが「地方創生の鍵は『高齢者の街』だ」のテーマでの対談がそれだ。その中で、楡さんが10年ほど前に書いた「プラチナタウン」(祥伝社文庫)は今、政府や自治体などで大きな政策テーマとなっている地方創生、高齢者が地方に移住して新たな町づくりにかかわる問題などを予見しており素晴らしい、と石破大臣が高く評価したのだ。
石破地方創生担当大臣も楡さんの小説を
「時代の先を予見している」と高く評価
石破大臣がこの小説を読むきっかけが面白い。伊吹文明元衆院議長からある時、「『プラチナタウンという経済小説を読んだかね』と聞かれ、『いえ、読んでいません』と答えたら『地方創生の担当大臣なのに、そんなことだからダメなのだ。本を送るから読めばいい』と叱られ、あわてて読んでみたら、とても面白くて参考になった」というのだ。
このエピソードがずっと以前、新聞記事に出た時に、記事を読んで思わず笑ってしまった。私自身も実は、その経済小説の存在を知らなかったため、好奇心をかき立てられ読んでみた。楡さんの着想や問題意識がなかなか面白く、一気に読んでしまったが、この「プラチナタウン」の続編ともいえる「和僑」というタイトルの経済小説があることも知り、それも続けて読んだ。私はむしろ、この「和僑」で描かれた着想が日ごろから考えていたことと同じだったので、楡さんという作家に強い興味を覚えた。そして、他の小説「象の墓場」や「レイク・クローバー」などを立て続けに読んだ。着想や構想力だけでなく、現場を歩いてよく取材している点がジャーナリスト的な作家だ、と感心した。
高齢社会を見据えた町づくり、
日本食文化を生かした第1次産業の再生がテーマ
さて、文芸春秋誌対談で問題先取りされてしまったが、私自身も、実はこの経済小説「プラチナタウン」と「和僑」で提起している問題をコラムで一度、取り上げてみたいと思っていたので今回、私なりにテーマに挑戦してみたい。
第1のポイントは、高齢者比率が急速に高まる高齢社会を想定して、アクティブシニアをめざす人たちを含め、高齢者が老後を苦にせず、気持ちの面で豊かに生活できる社会の制度設計をどう構築するかだ。そこには医療や介護など重い課題の山積があり、容易でないが、今回の例でいえば「プラチナタウン」のような町づくりもある、ということだ。
もう1つの議論ポイントは、農畜産業など第1次産業の再生だ。「和僑」で提起した日本食文化とフルリンクさせた農畜産物の輸出が1つの選択肢だ。要は、日本食文化への評価の高まりを背景に、日本の外食企業が海外で店舗展開する。その際、日本でもお客に人気のメンチカツ、タンシチュー、お好み焼き、焼き鳥などB級グルメ食を外国人仕立てにし、マーケッティングに工夫をこらして行列のできる店にする。食材は現地調達せず、日本の独自素材を活用して加工し、日本食の味の魅力を半製品にして輸出するところがポイント。そうすれば第1次産業が腕を振るえる。冷凍加工システムに磨きをかけ安定輸出につなげる。日本の第1次産業にとってグローバル版6次産業化ともなる、という考えだ。
楡さんの小説は現場体験などをもとにした
小説スタイルで面白い!
本題に入る前に、経済小説「プラチナタウン」と「和僑」をまだ読んでおられない人たちのために、簡単に中身を紹介しよう。
「プラチナタウン」は、宮城県のある架空自治体の話だ。総合商社の部長が、社内での人事レースに敗れ屈折した気持でいた時に、郷里の友人から次期町長に推される。弾みで引き受けたものの、無駄な公共投資のツケで赤字を抱え込み財政再建団体寸前、工場誘致で開発した巨大な団地も手つかずのまま放置などでカベにぶつかる。しかし自然などの地域経営資源を前に、老後不安を抱える高齢者を対象に、豊かな老後を過ごせる永住型住宅タウンも一案と、かつて勤めた商社を巻き込む。結果的に東京などから高齢者が移住し人口増で町が勢いを取り戻して活性化、介護などで雇用も創出され税収が上がり、町再生に成功する話だ。楡さんの筆致はなかなか巧みで、読ませるので、ぜひご覧になればいい。
続編ともいえる「和僑」は、町出身の若者Uターンなどで活性化したプラチナタウンの将来リスクをテーマにする。移住してきた高齢の居住者がいずれ超高齢化に伴って死去したりすると人口減少でリスクを迎えるためだ。商社OBの町長が苦悩していた時に、米国に帰化して外食企業で成功した町出身の企業経営者が帰郷する。その経営者が米国籍の娘ともども、町の畜産現場の和牛肉やメンチカツなどB級グルメ食品に舌づつみを打ったのを見て、町長ら町の関係者が企業経営者との連携を思いつく。具体的には、町でレストラン経営の若者とその経営者が一緒に米国で日本食文化の店を展開する。華僑と同様、日本人が海外でビジネスを立ち上げる和僑だ。その際、町の第1次産業の再生につながるようにさまざまな食材を調合して冷凍加工し切れ目なく供給する体制をつくるといった話だ。
政府も今、日本版CCRCで高齢者が地方に移住して
居住する町づくりを構想
そこで本題だ。石破地方創生担当大臣が冒頭対談で語ったところでは、政府は今、米国で定着しているCCRC(CONTINUING CARE RETIREMENT COMMUNITY)の日本版CCRCを構想中だという。要は、都会の高齢者が地方に移り住み、健康状態に応じた継続的なケア、つまり医療や介護を含めたケア環境のもとで自立した社会生活を送れるような地域共同体のことだ。先進事例がある米国では現在、2000か所にそれがある、という。楡さんが小説で描いた「プラチナタウン」も、それと同じものだ。
私も、自然という豊かな地域経営資源がありながら人口減少で疲弊していく地方の経済社会の再生には、「プラチナタウン」や日本版CCRCを構築するのはいいアイディアだと考える。それに合わせて地域で新たな雇用創出となるばかりか、若者を中心に都市に流出していた、その土地の出身者がUターンで戻ってきて地域の立て直しに頑張る構図が見えてくれば、その人たちが中核になって地域おこし、地域再生に弾みがつくと思う。
問題は移住してきた高齢者と地域住民の融合など
新地域社会システムがつくれるか
問題は、都市から移住してきた高齢者らと地域住民がうまく融和し、互いにその地域に誇りを持てるような枠組みがつくれるかどうか、「プラチナタウン」で楡さんは過剰な公共投資でつくった病院などの社会インフラが結果的に再活用される、というプラス面が出ると指摘したのは事実ながら、それら医療や介護施設を軸に新たな地域医療ネットワークシステムにつなげることが可能かどうか、端的には地域内の遠隔地に住む高齢者との間でICT(情報通信技術)を駆使して早期発見・早期治療のシステムづくりに持ち込めるようにすることが必要だ、さらに、「プラチナタウン」の高齢者がアクティブシニアとして地域貢献できるシステムづくりが可能かどうかなどだ。単に高齢者の町をつくるだけでは地域の活性化にはつながらないからだ。
その点で、今年2月にオンエアされたNHKの旧「クローズアップ現代」で「高齢者の“大移動”始まる!――検証・日本版CCRC」を思い出した。当時、CCRCという存在を知らなかったので、興味を持ってみてみた。現在、構想の具体化に向けて取り組んでいる新潟県南魚沼市のケース、また20年前に全国に先駆けて開発された福岡県朝倉市のケースなどだった。
福岡県朝倉市の失敗事例をどう生かすか、
新潟県南魚沼市チャレンジは興味深い
このうち朝倉市のケースは失敗事例だ。当初、300億円の総事業費で一戸建て住宅街、住民交流のコミュニティセンター、フィットネスクラブ、ゴルフ場など、豊かな老後を過ごせるようなタウンづくりが計画された。ところが目標とした1000人の移住が実際には200人にとどまり、民間の開発業者の経営が悪化して住民交流の場であるフィットネスクラブなど施設が建設中止に、また介護を必要とする人たちをサポートするヘルパーさんらがうまく集まらず安心して老後が送れないと他地域に転出してしまった、という。今後、日本版CCRCを具体化するにあたっても、この朝倉市の失敗の研究をしっかり行って、何を教訓にしてプラスに切り替えていくかが重要だ。
南魚沼市のケースは、今度、チャンスを見つけて現場に行ってみたいと思ったが、興味深いのは、アクティブシニアという形で活躍できる場をどんどん提供することで、結果的に介護保険や医療費の負担問題が解消される方向にもっていくこと、さらに南魚沼CCRCビジネス研究会を通じてIT関連企業との連携を図り、新たなビジネス創出につなげていくこと、新潟県内に立地する国際大学とも連携したり、独自にインド、スリランカからIT企業誘致も検討することなど、取り組みが「医療や介護を必要とする高齢者の町」ではなく「アクティブシニアの力を借りて町の再生を」という発想が面白い。
農産物輸出は売り切りではダメ、
グローバル版6次産業化の発想で行くべきだ
2つ目の農畜産業など第1次産業の再生の話に関しては、楡さんが「和僑」で描いた海外で日本食文化の評価の高まりをうまく活用する点は大賛成だ。着想が極めていい。これまでの農産物輸出の発想は、いわゆる売り切りの輸出でしかない。つまり際限なく日本産農産物などにリピートの声がかかるような仕掛けができていない、また競合する農産物が出てきたら、たとえば値段が割安、味も改良されて日本産とそん色ないものとなれば、そちらに代替されてしまうリスクが大きい。
そうしたことを根本から変えるのが、「和僑」で描いた農産物輸出方式だ。つまり、海外で日本食文化への評価の高まりなどを背景に、独自の日本食B級グルメ食品をアピールして存在感を高める、その食材を日本で独自に味付け加工して冷凍で輸出するようにしてグローバル版6次産業化をすれば、第1次産業の再生にも間違いなくつながる。
その点で行くと、農林水産省や経済産業省が考える「攻めの日本農業」のための農産物輸出戦略は、課題や問題がいっぱいなのだ。私はかねてから、オランダ農業の現場を見た経験から、日本農業はオランダ農業に学べと考えている。九州の広さしかないオランダ農業は、日本と同様、農地が少なく、人件費上昇リスクなどを抱えているのに、今や米国に次いで世界第2位の農業輸出国になっている。
日本は戦略的なオランダ農業に学ぶこと多い、
世界第2位の農業輸出国は見事
その最大のポイントは、農産物輸出に戦略を持っていることだ。別の機会に、コラムでレポートするが、輸出先市場を徹底して研究すると同時に、それら市場でオランダ産農産物がシェアを確保できるものは何かを絞り込み、ガラス張りの巨大な施設でICTなどを活用して生産性向上によってコストも削減して競争力維持に努めること、さらにゴールデン・トライアングルとオランダが自ら名づける産官学の連携による優れた新品種開発体制づくり、それと日本の地域産ブランド、端的には和牛の松阪牛、佐賀牛、滋賀牛などのような地域ブランドとは対照的に「オランダ産」1本で統一して輸出に取り組むなどだ。
日本農業は生産力も、品質管理力も十分にあり、海外で勝てる力をもっているが、これまで「守りの農業」で終始してきたため、オランダのような輸出戦略に欠けているだけだ。
関連コンテンツ
カテゴリー別特集
リンク