
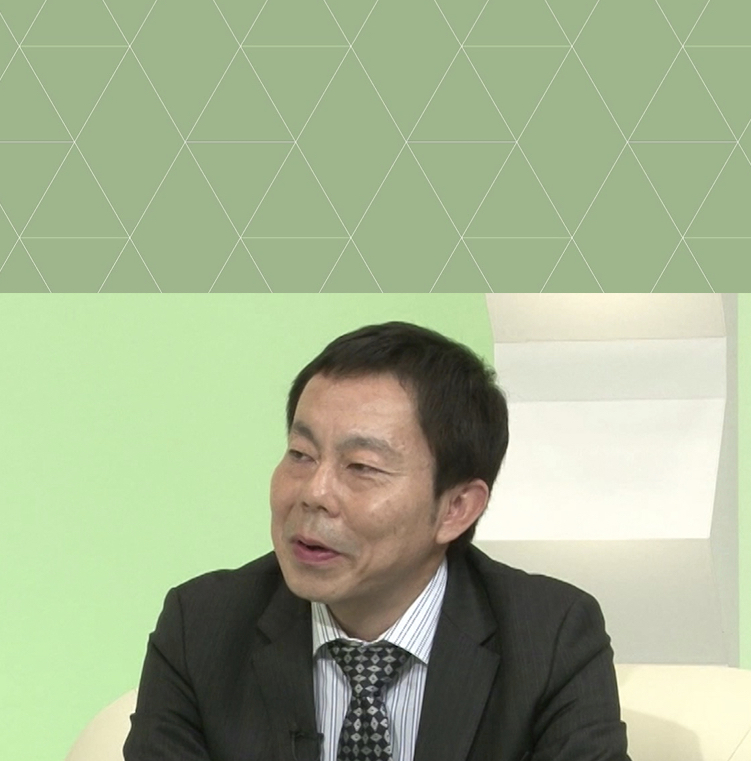
2%台という平均空室率を叩き出した不動産投資の新しいビジネスモデルとは?!
株式会社ボルテックス
代表取締役社長兼最高経営責任者
宮沢 文彦


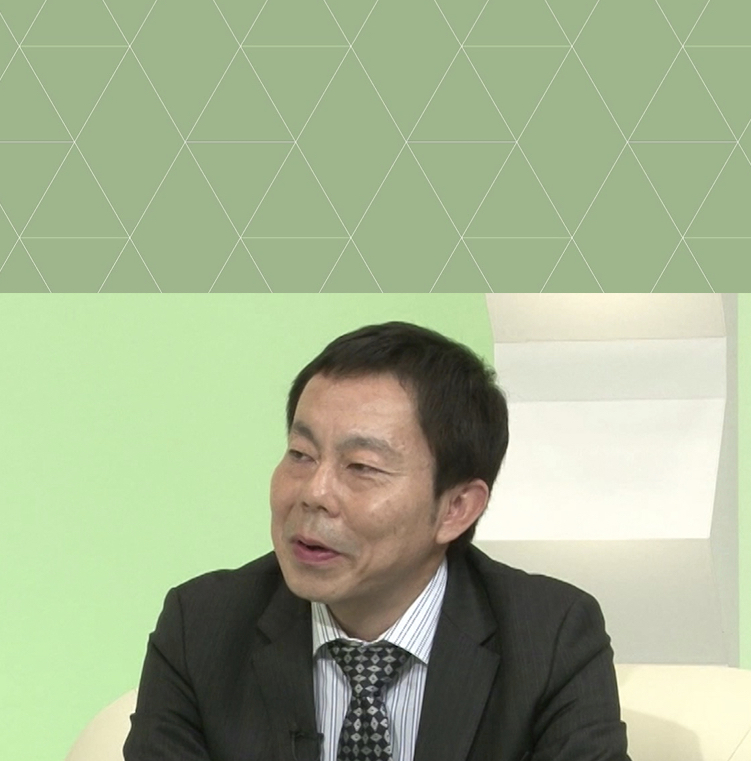
中小企業が圧倒的に多い日本の企業は、今までオフィスとして借りるという選択肢しかなかった。そんなオフィスビルに区分所有という新しい不動産投資のビジネスモデルを持ち込み、急成長を遂げる企業がある。株式会社ボルテックス。新しい不動産所有の形を提案し、不動産投資イノベーションを掲げるリーダー、宮沢文彦の成長戦略に迫る!
こうして1999年、宮沢の理念のもと株式会社ボルテックスが誕生した。
宮川その事業の方は順調に進んだのでしょうか。
宮沢仕入れに関してっていうのが当時はやっぱり非常に悪かったですから、ほとんど競売で物件を買っていたのですけれども。当時は特に私共がやっているような事業系の区分所有というのは、ほとんど入札する人がいなかったですから。競売というのは期間入札という、まずその期間に入札される時期があって、ただここで一本も入札する人がいなかったですから、大概翌日に特別売却という形になって一番下で買えたのですよ。ですから、仕入れの部分っていうのは、逆に商材と時期が悪かったが故に非常にやりやすかったですね。誰一人競合しないという状況が長く続きました。
宮川しかし競売で落ちなかったものというのは、物件として心配じゃないですか?
宮沢心配だからこそ安くなっている。収益性が悪くテナントもついてないビルっていうのは、満室稼働しているビルに比べるといかにも収益性悪く見えますよね。でも実はそこのついてる・ついてないっていうのは、値段設定、プライシングの問題で。これって皆さんわりと誤解しやすいのは、場所がいいからテナントってつくように感じますよね。場所が悪かったり建物が古かったりするとつかないんじゃないかなという風なイメージを持ちますよね。だから事実そういう物件で、そのテナントのついていないビルなんかっていうのは、より入札が少なくなったりするわけなんですけど、私共は積極的にそういう物件を狙いに行きました。で、結局のところ、やや場所が悪くても値段さえ下げれば、賃貸っていうのは必ずつくわけなんですよ。
宮沢逆にどんないい物件でも、どんないい場所でも、値段が合ってなかったら、それはつかないんですね。
宮沢プライシングの問題であって、立地っていう絶対的な問題ではないので、私共としては、そういう場所とかいったものに惑わされずに、もちろん場所が良くて割安に買えれば、なおいいわけなんですけど、場所が悪かったとしても適正なプライスのものを競売で取得できていた時期ですね、初期の頃というのは。
グレードの高い物件の方が適切なプライシングがされないまま空室期間が長引く傾向にあると宮沢は言う。都心5区のオフィスビルにおける平均空室率は7パーセント台。しかし、ボルテックスの管理物件の平均空室率は2パーセント台だという。
宮沢どうやってもテナントが入らないようなものにテナントを入れたり、もしくは適正プライスにすることによって、きちっとついたりっていうのを一個ずつ証明していくというのは、わりと楽しいんですよ。元々キャリアがあったわけでもないですから、仮説を立てて、こうであるはずだということを一個一個実務で証明していく。
宮沢ということが私共のノウハウになって、それで今日があるわけなので。
白石でも、その空室を埋めるために価格を下げますよね? そうすると、元々そこを買ったお客さんとの格差というのが生じると思うのですけれども。
宮沢そういう質問というか、危惧も、昔からよく言われていたんですけれども、実際やってみたらほぼないですから。そういうのも、やはり先に聞いていたものと、実際にやってみた結果というのは、だいぶ乖離がありますね。売上がやっぱり日々変動するように、不動産の売上たる賃料というのも、非常に長いスパンでの勝負ですから、結局たまたまそのテナントがいた時期は、例えば100万円の賃料が取れ、次のテナントが入った時は50万の時もあれば、150万になる時もあるので、それは変動して当たり前だと思います。変動しないものというのは、この世の中にないはずなので、人の給料もキャベツの値段もガソリン代も、みんなやっぱり変動していくものなので。
それを、変わると嫌だという人間側の勝手な欲求が、その適正なプライスからずれていっちゃう。これが空室という状況を長引かせちゃうので。
宮沢そこをもう少し柔軟に捉えて、そういうこともあると、下がる時は下がる。その代わり、上げる時はきっちり上げる。前についていたプライスに惑わされずにやっていくとうまくいくと思いますね。
白石では、続いてのキーワードは何でしょうか。
宮沢「区分所有の優位性」です。
リスクを先読みしながら逆説的思考で独自のビジネスを展開する株式会社ボルテックスのリーダー、宮沢文彦。次なるキーワードは「区分所有の優位性」。その核心に迫る!
宮川今キーワードとして「区分所有の優位性」ということが出てきました。これはどういうことでしょうか。
宮沢弊社で取り扱っている事業系オフィスビルの区分所有ですね。これが一般的にはあまり馴染みがなく人気もないと言われている商材ですけれども、実は非常に有利なポイントがたくさんありまして。まず、通常不動産買いますと、いろんな部分の修繕ですね、特に共用部、外壁ですとか、大きな設備、昇降機ですとか、こういったものに関してっていうのは、かなり多額の資金負担が得てして、購入直後とかにかかるケースというのが多いんですけれども。
私共の商材はそれらが長期修繕計画に基づいて組合側が負担することになっていますので、所有者というのはあまり大きな支出をするケースというのがないんですね。あともう一つは、不動産というのは老朽化した時に最終的には、そこを壊して建て替えをするんですね。その建て替えをする時に、特に商業地の規模の大きな土地っていうのは、開発メリットが非常に大きく出るんですよ。
ですから、単純に言うと、20坪の敷地に建っている小さなビルを買うよりも、200坪の敷地に建っている大きなビルの10分の1の権利を持っている方が、将来例えばボロボロになって土地だけの権利になった時に、だいぶその価値が違うんですね。そういう、いろんな意味で、実は区分所有の方が有利であるという部分が多いですね。
白石なるほど。そういった物件はどうやってお客様は購入されるのですか?
宮沢主に中小企業の経営者さんが法人として。特に冒頭で申しましたように、本業にプラスして、本業の利益プラス賃貸事業からの利益を作るというような、そういう本業と連動しない資産ですね。通常の企業であれば、本業に関連のある自社ビルとか本業で使う工場を持ちますけど、その本業で使う工場ですと、それを換金しようとした時に本業に影響が出ちゃいます。私共の商材は本業と関係なく、手のかからない、長期間マーケットの中で通用しやすいもの。これを売却可能資産として保有していただくというようなケースが多いですね。
こちらはボルテックスが購入し、区分所有権で販売したオフィスビル。ボルテックスが販売した区分所有権を購入した大手電気給湯器メーカーの伊藤代表取締役にお話をお伺いしました。
出演者情報
企業情報
関連コンテンツ
カテゴリー別特集
リンク