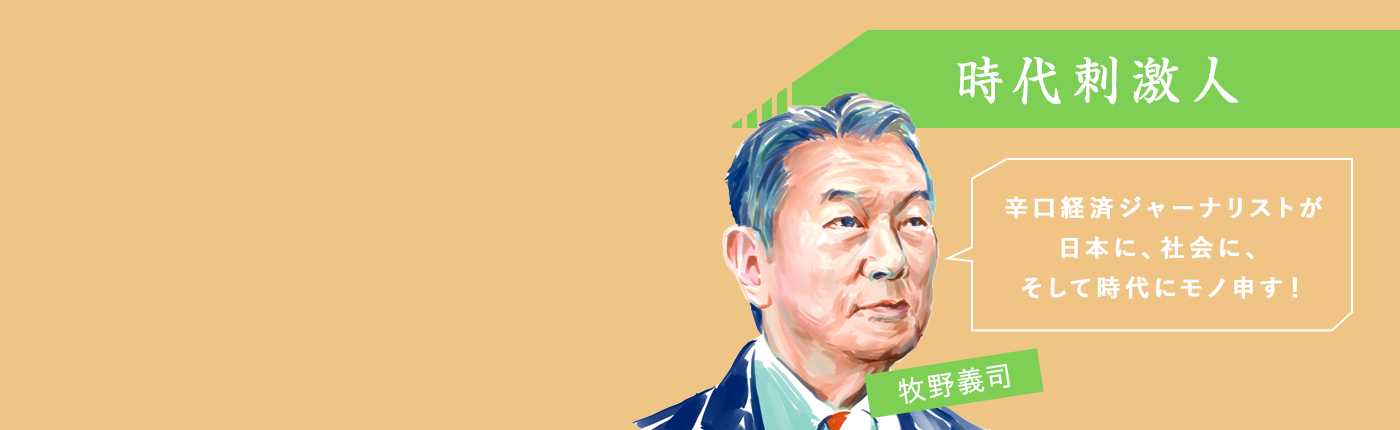


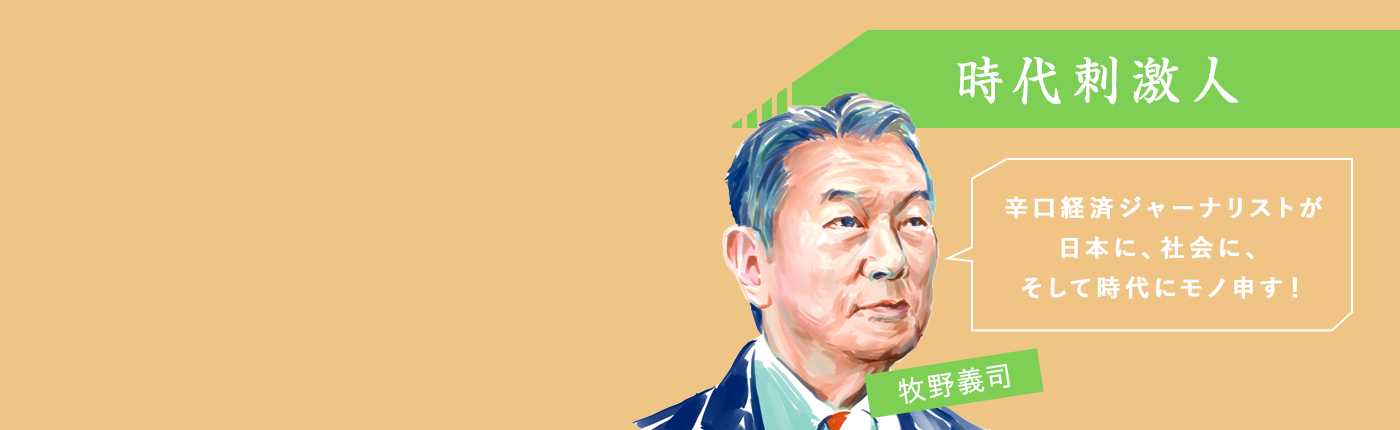


コダック写真フィルムの名前で一時代を画した米イーストマン・コダックが2012年1月19日に経営破たんした、というニュースを見て、本当に驚いた。ビッグ・サプライズだった。デジタルカメラや携帯電話カメラの登場で、フィルム自体の需要が急速に落ち込んでいるのははっきりしていたし、かなり以前から予測もできていたはずなのに、なぜなのだろか、というのが最大の関心事だ。
経済ジャーナリストの好奇心で、いろいろ調べてみると、これまたサプライズ。これほどの名門企業で、130年超という長い歳月を乗り切ってきた企業だというのに、過去の成功体験にこだわり、思い切った事業転換を図れなかったのが最大の破たん原因というのだ。日本のライバル企業、富士フィルムがいち早くカメラの写真フィルムに見切りをつけ、業種転換を図って新たな成長軌道を走っているのとは対照的だ。
英エコノミスト誌
「コダックは完璧な製品つくることにこだわり変化を拒んだ」
たまたま読んでいた「予測できた危機をなぜ防げなかったのか?――組織・リーダーが克服すべき3つの障壁」(東洋経済新報社刊)という本が、このコダック経営破たんにぴったり合致しそうな感じだ。そこで、今回は、このコダックというグローバル巨大企業の経営破たん問題を取り上げてみよう。
英エコノミスト誌はさすが専門誌だけに分析が鋭い。コダック破たん直前の1月14日号で、この名門企業の特集記事を出している。なかなか読みごたえがあり、いくつかヒントがある。参考になる部分を少し活用させていただこう。
エコノミスト誌は、ハーバード大経営大学院のロザベス・モスカンター教授の「コダックはモノをつくり、売り出し、常に修正するというハイテク世界の考え方ではなく、完璧な製品をつくるというメンタリティにとらわれていたことが問題だった」という分析を引用し、コダックの技術完璧主義、フィルムへのこだわりが新しいトレンドや変化の動きを拒む結果になり、富士フィルムとは対照的に墓穴を掘る結果になった、とみている。
「富士フィルムは新収益源を探し出したのにコダックはそれができず」とも分析
記事の最後の部分が面白い。エコノミスト誌は、「富士フィルムは新たな技術を習得して生き延びた。2000年には利益の60%を稼ぎ出していたフィルム部門がほとんどゼロになってしまった。しかし新たな収益源を探し出している。コダックはそれができなかった。古い写真のように、コダックは色あせた」と述べている。
そして「人間と違って、企業は理論的には永遠に生きることができる。しかし一般社会と違って、現実の企業社会は死闘である。(その厳しい競争に勝ち抜くチャレンジを続けなければ)ほとんどの企業は若くして死んでしまう」と、辛らつだ。
いち早くデジカメを開発する技術力あったのに
商用化で日本メーカーに立ち遅れ
要は、コダックは、米国を軸に世界的にトップシェアの企業の座を長い間、維持してきたが、さまざまな写真フィルムの独自開発など、過去の成功モデルにこだわった結果、エコノミスト誌が指摘するように、急激な変化に対応しきれず、むしろ既得権益を守ることに傾斜し保守的になりすぎたことがアダになった、ということのようだ。
しかしコダックの研究開発力や技術力はすごかった。何と1975年にデジタルカメラの開発に成功しているのだ。時代の先を見据えた技術開発力はさすが、という感じがするが、いろいろ調べてみると、技術が経営とリンクしなかった。端的には商品化、製品化、さらにはマーケッティングによって一気にコダックブランドのデジタルカメラという形にすることができないまま、後発の日本のカメラメーカーに、エレクトロニクス技術を駆使され、あっという間に市場シェアを確保されてしまった、という。何とも、もったいない話だが、不思議なのは、コダックの経営陣がそれでも、ただ指をくわえてライバルの動きをみているだけだったのか、ということだ。
世界の4大フィルムのトップ、
しかも低価格カメラでは断然優位の時代も
余談だが、私の毎日新聞駆け出し記者時代の山形県での取材には必ずカメラが必携で、取材すると同時にカメラマン役も兼ねて仕事するのが当たり前だった。ところがフラッシュをたいて写真撮影するのが、どちらかといえば苦手というか面倒だったので、当時、少し薄暗い室内でもきれいに撮れるコダックの高感度フィルムを愛用した。
今でこそ見る影もない写真フィルムだが、かつては世界で米コダック、日本の富士フィルム、小西六(現在のコニカミノルタ)、そしてドイツのAGFAが4大フィルムだったそうだ。中でもコダックは断然トップの強さだった。そのコダックは、意外にもフィルムだけに安住せず、いわゆる川上から川下まで、しっかりとシェアを抑え、フィルムが一体で活用されるようにと、カメラも同時開発する巧みさが創業当初からあったというのだ。
デジタルカメラではつまずいたものの、カメラに関しては1900年に「ブローニー」という低価格カメラ、また1963年には一眼レフカメラ全盛のころ、「インスタマティックカメラ」という簡単操作で撮影でき、しかも低価格のものをいち早く売り出している。
富士フィルム社長
「コアビジネス失った時に事業多角化で危機を乗り越えた」
そんな華やかな歴史を持ちながら、なぜ破たんしたのか、という疑問に戻ってしまう。そこで対比されるのが同じフィルムメーカーだったライバル企業、富士フィルムの経営姿勢だ。英エコノミスト誌が指摘したとおり、需要が激減したフィルムに見切りをつけて素早く新たな収益源を探し、経営資源を特化した経営の切り替え判断に尽きる。
富士フィルムホールディングスがコダック経営破たん時にメディア向けに公表した古森重隆社長のコメントでは「時代が流れる中で、コアビジネスを失ったとき、乗り越えられる会社と乗り越えられない会社がある。当社(富士フィルム)は事業を多角化することで乗り越えてきた」と。なかなか説得力のあるメッセージだが、現に、液晶テレビ用保護フィルムで高いシェアを上げると同時に、医療分野、化粧品分野に事業展開している。コニカミノルタホールディングスは2006年に写真フィルム事業から撤退し、DVDなど光ディスク用レンズで成果を上げている。
「予測できた危機をなぜ防げなかったのか?」という本は
コダックにあてはまる
さて、冒頭に紹介した「予測できた危機をなぜ防げなかったのか?」という本のことも少し述べよう。タイトルからすると、コダックの経営に対する問題意識が当てはまりそうだ。この本は、ハーバード大ビジネススクールのマックス・ベイザーマン教授、それに同じビジネススクールで教授歴任のマイケル・ワトキンスさんが書いたものだ。 やや学術的な専門書で、しかも難しい言い回しが多くて、読みにくいのだが、米国で起きた9.11同時多発テロやエネルギー・ベンチャー企業のエンロン破たん問題など、いくつかの事例を検証しながら問題提起している。
要は、リーダーが克服すべき3つの障壁を心理要因、組織要因、政治要因だとし、それをもとに、教授らは、「脅威や危機があるかどうかの問題の認識、対処すべき課題の適切な優先順位づけ、そして問題や課題の解決のために経営資源や組織を動員し、それらが効果的だったかどうかの見極めの3つが重要」という。
その際、「危機防止の要件は、組織の指導層がフォーカスを示し、組織を活性化させ、判断力を行使し、不人気なことも実行する勇気を持つことだ。だが、それだけでは足りない。組織本体を対応力と弾性力のあるものにしなければならない」とも述べている。
コダックは需要激減の危機に対応したが、経営ミスかすべてが裏目に
この本で興味深かったのは、危機の予測部分だ。往々にして、リーダーは楽観幻想があってアクションをとるほどでないとなりがち、また出来事を自己中心的に都合よく解釈してしまう、将来を過度に軽視し、たとえば災害が起こるのは、はるか先だと思い込むなどのバイアスがあることだ、という指摘だ。また、「起こりつつある脅威に関する情報の収集に必要な資源を投入しない」「情報を周知したがらない」「組織に散在する知識を統合しない」「学習した教訓を保存しない」なども組織面での問題だ、という。
コダックの場合、写真フィルム需要が激減したのに対して、経営が全く手を打っていなかったわけでないものの、その時々の経営陣の新規事業分野への投資判断、あるいは選択と集中という表現で使われる経営多角化分野の整理淘汰の方向付けなどがことごとくうまくいかないうちに、売上高も利益も急減し、その一方で退職者向けの年金などのコスト負担増がボディブローとなったことだけは厳然たる事実だ。
コダックは古い20世紀型経営、
先端分野へのあくなきチャレンジに欠けた
リーマンショック後の2009年に、米ゼネラル・モーターズ(GM)がコダックと同じ米連邦破産法11条の適用申請を行ったが、コダックが裁判所に駆け込んだ同じ1月19日に、何とGMは再生努力の結果、自動車世界販売トップの座に帰り咲いたという話がニュースになっていた。
コダックに再生の道があるのかどうか、はっきりしないが、コダックがフィルムなどの特許料収入に依存した経営を続けていた、といった話を聞くと、20世紀型の経営に終始していたようで、インターネットの活用や先端技術分野へのあくなきチャレンジといった時代先取りの取り組み、早い話が21世紀型経営モデルでないところが致命傷だったという気がする。
元IBM会長の「現状に満足せず、進んで経営目標のハードル上げる」はすごい
元IBM会長のルイス・ガースナー氏が以前、日経ビジネス誌の「会社の寿命」企画のインタビューで、思わずウ~ンとうならせる発言部分があるのを引っ張り出したくなった。そこを最後に紹介しよう。
「常に1つところにとどまらず、エクセレンスをめざす。絶えず刷新しライバルの挑戦を受けて立ち、これを楽しむ。市場シェアの拡大をめざし、決して現状に満足しない。ボスが求める前に、進んでハードルを引き上げ、次々に難しい目標をめざす。こうした企業文化が、企業を何十年にもわたって存続するのを可能にします」と。IBMはタフな企業だ。
関連コンテンツ
カテゴリー別特集
リンク