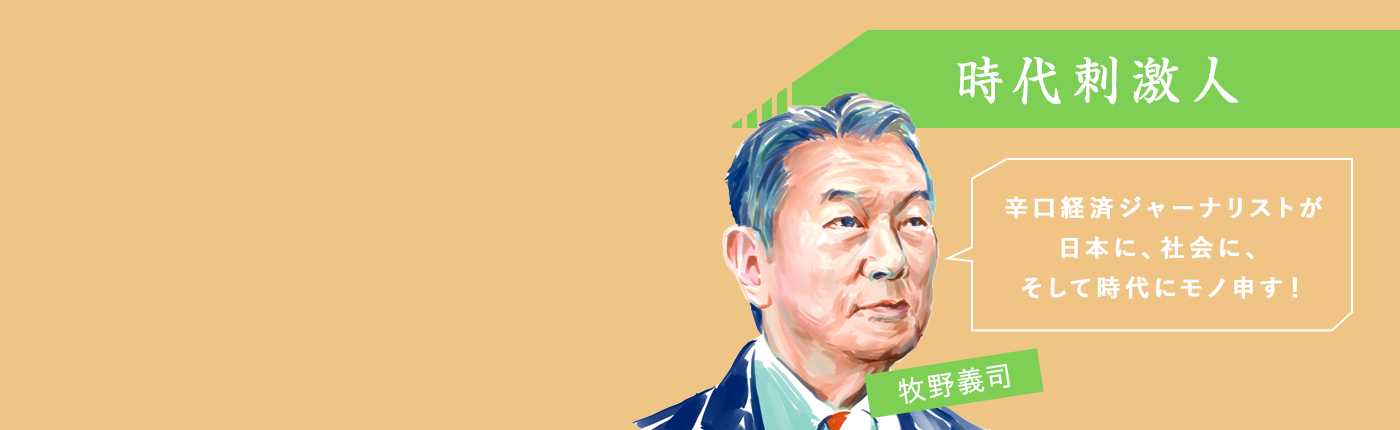
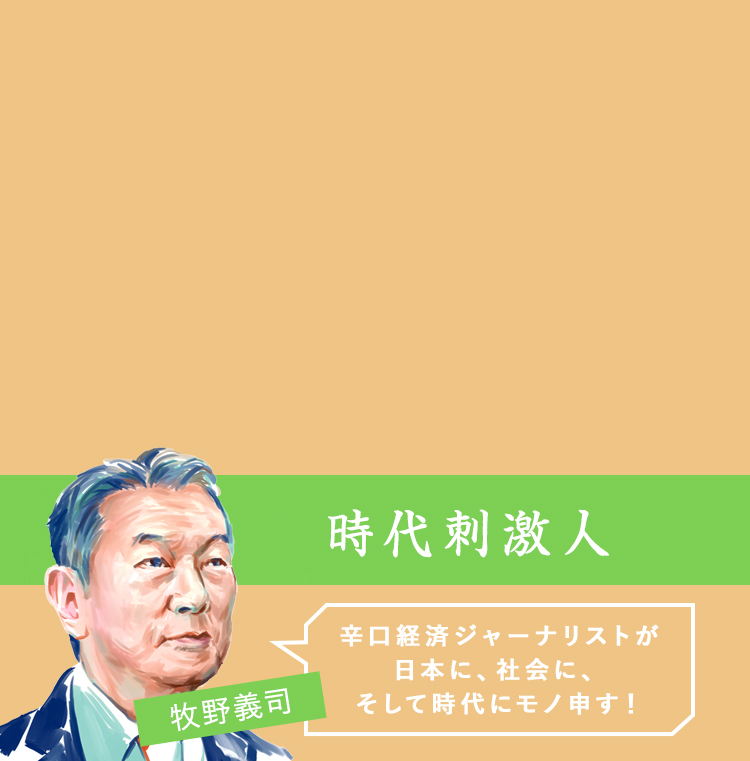

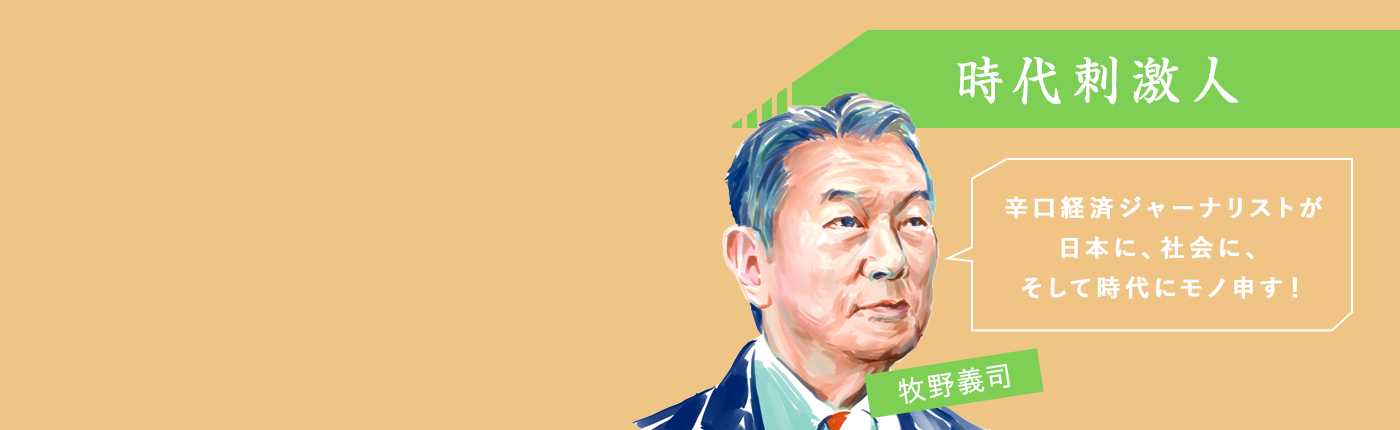
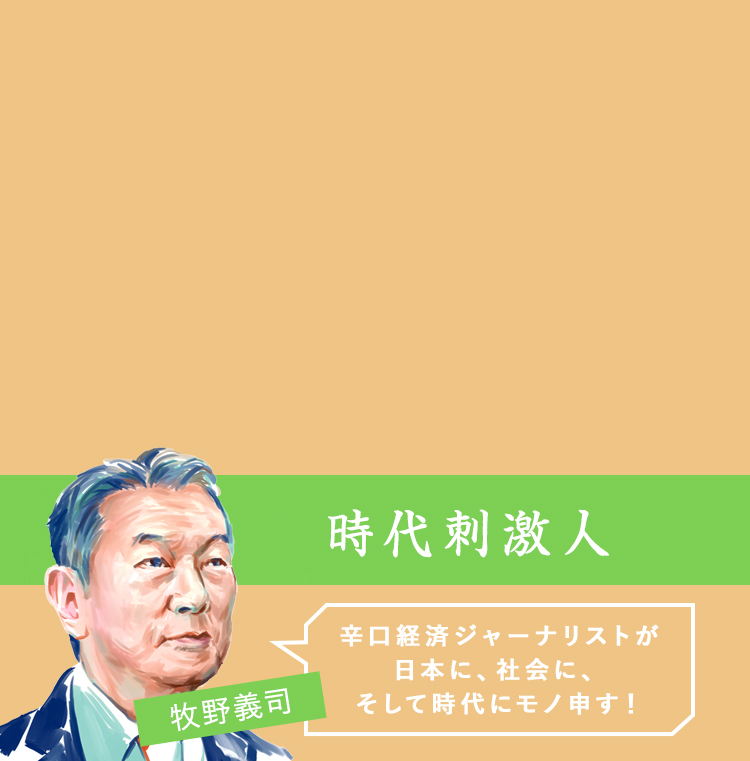

これに対し、日本企業の側にも言い分がある。日本の会社法では企業の代表権を持つCEOといえども、代表権の濫用に歯止めがかけられており、取締役会の決議を経ることを義務付けている企業が多い。だから、責任あるCEOとして、アジアの現場から日本本社に持ち帰り経営会議で決めたいと考えるのは当然、との反論となる。だが、スピード対応を求めるアジア企業には通じず、日本企業が経営判断を先延ばししているとしか映らないようだ。
最近、タイの現地法人から日本に一時帰国した日本企業の幹部と意見交換した際、その企業幹部は「スマホ決済のEコマース(電子取引)などでシェアを誇るシンガポール拠点のグラブはじめ現地企業との競争は激しさを増す。日本企業はデジタル対応に遅れがあり、彼らのスピード対応には苦戦する。日本企業が過去の成功体験をもとに、アジア企業に対して上から目線で経営を発想していては間違いなく負ける」と述べていたのが印象的だ。
経済に勢いがついたアジアの国や地域は、内部に経済社会インフラや経済構造に問題や課題を抱えていても、臆することなくアクティブな行動をとる。それがうまく経済成長に弾みをつける結果になっている。ASEAN(東南アジア諸国連合)10か国のうちシンガポール、タイ、マレーシア、ベトナムの最近の動きはまさにそれだ。しかも急速な都市化に伴って膨れ上がった都市部の中間所得層の旺盛な消費購買力などが成長を押し上げている。
中でもシンガポールは際立っている。人口が少なく移民労働力に頼る一方で、目立った資源がないのに、加工貿易や3国間貿易をベースに、海外から呼び込んだ高度人材、投資マネーを積極活用してイノベーション・プロジェクトにつなげる凄さがある。
さきほど名前の出た配車・配送サービス大手グラブも急成長企業の典型だ。米ハーバード大卒業の2人の共同創業者が、同じ業種の米ウーバーテクノロジンーのアジア事業法人を買収して傘下に収め、小が大を食う形で急成長した。そのグラブに加えネット通販のシー、インドネシア拠点の配車大手ゴジェックと通販大手トコペディアが経営統合したゴーツー(GoTo)3社が今やASEANでプラットフォーマーとなっている。彼らは競合しながら事業展開でしのぎを削り、市場を拡大させている。日本企業とは明らかに勢いが違う。
国際協力銀行OBの友人、邉見伸弘さんは著書「チャイナ・アセアンの衝撃」で、経済成長が進むASEANのダイナミックな変化を描いている。それによると、人口100万人以上のメガ都市が40を超え巨大な市場経済圏をつくっている、中国メガ都市群270には及ばないものの、東南アジア諸国・地域の市場経済圏の厚みが凄い、これら地域を昔のように新興国として見続けていると、日本は、そこで起きているイノベーションやビジネスチャンスを見逃してしまう、という。私もアジアの現場を見ていて、その指摘を実感する。
関連コンテンツ
カテゴリー別特集
リンク