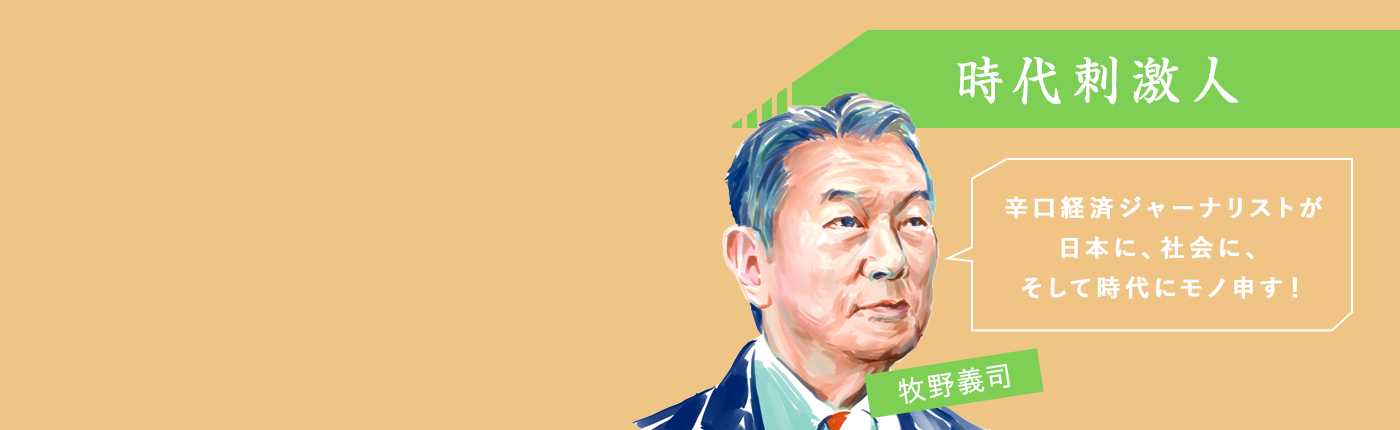


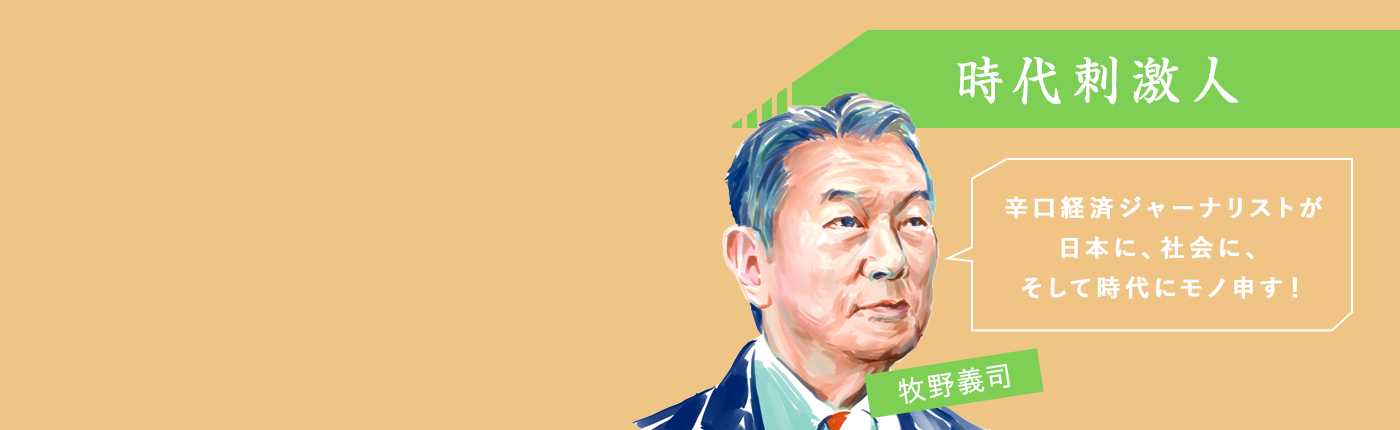


メディアの取材現場に長く携わった私自身の経験から言って「これは素晴らしい。よくやったな」と思ったのは、朝日新聞が今年9月21日付の朝刊1面トップで「郵便不正事件で大阪地検の主任検事、押収資料改ざんか」と報じたことだ。「検察、それも特捜部が裁判を検察のシナリオどおりに有利に運ぶため、故意にデータ改ざんしたというのは前代未聞。朝日新聞は『改ざんか』と見出しで疑問符をつけているが、ここまで報じる限りウラをとってのことだろう。すご~い」と当時、報道の持つ意味の重要さに驚いた。
報道の波紋は大きかった。事態は予想外に急進展し、最高検察庁が異例のスピードで報道されたその日の夜に主任検事を緊急逮捕、さらに当時の大阪地検特捜部の部長と副部長についても犯人隠匿容疑で逮捕した。そればかりでない。これをきっかけに、検察庁の中でも特捜部という検察エリート集団に鋭いメスが入った。朝日新聞の調査報道が地検、高検、最高検という検察の中枢を直撃したのだ。他のメディアも徹底的に検察特捜部の実体に迫る分析追及の報道に走った。
巨悪を暴くはずの特捜検察の捜査手法に今や赤信号、「国策捜査」にも問題
特捜検察といえば、戦後のさまざまな巨悪の追及や摘発したことで有名。端的にはロッキード事件での田中角栄元首相逮捕に及んだ時のように、国家の最高権力をモノともしない特捜検察の正義感に、国民は拍手喝采したものだ。ところが、最近は「国策捜査」といった形で、国家の権力サイドにおもねるような検察捜査が問題になったのをはじめ、栃木県足利市での女児殺害事件で無期懲役の確定していた菅家利和さんがDNA鑑定の結果、検事の取り調べに無理があったことが判明し、一転無罪判決となる冤罪(えんざい)事件もあった。今回の大阪地検特捜部が立件した郵便制度不正利用事件の検察捜査も同じで、厚生労働省の現役局長で逮捕された村木厚子さんの無罪が決まるなど、検察の捜査手法に疑問符がついていた。
記者クラブ制度に安住の発表ジャーナリズムよりも分析や調査報道で存在感を
そこで、今回は、メディアの調査報道の問題をぜひ取り上げたい。私は、かねてから新聞などのメディアが記者クラブ制度に安住して、記者クラブで発表されたものを速報によってスピーディーに、かつわかりやすく報じるといった発表ジャーナリズムに関しては、ジャーナリズム本来のものではないこと、むしろ、メディアは今後ますます分析報道、それに調査報道、さらには一種の政策シンクタンク的な形での政策提案報道によって、その存在感をアピールすべきだと思っている。とくに調査報道に関しては、その丹念な取材手法によって、隠されていた問題をえぐり出して真実に迫るということが必要になる。言ってみれば掘り起こしジャーナリズムだ。メディアの生き残りはこれしかないと思っている。
そういった意味で、今回の朝日新聞のスクープ報道はまさに調査報道の成果であり、拍手を送りたい。この朝日新聞のスクープ記事が今年の日本新聞協会賞(編集部門)の追加受賞者に決まったのは、ある面で当然のことだ。実は2010年度の新聞協会賞は今年9月にすでに受賞者が決まっていたが、新聞協会関係者の間でも、追加表彰に値するとの声が高まり、異例の追加受賞となったようだ。
スクープしたのは下野新聞から朝日新聞への転職記者、取材力が評価される?
朝日新聞が10月15日付の新聞週間特集紙面で、この取材にあたった板橋洋佳さんという34歳の記者のレポートが掲載されていたので、私自身、好奇心も手伝って、思わず読んでしまった。板橋さんは、もともとは栃木県の地方紙、下野新聞の記者だった。入社して8年後に朝日新聞に転職し、神戸総局を経て大阪本社社会グループに移り、スクープをものにしたのだ。その取材力が朝日新聞に評価され、ヘッドハンティングの形で引き抜かれたのだろう。日本のメディアも、今後は人材の流動性が高まり、プロ野球のスカウト人事のように、力があればライバル他球団へ移籍する形で、競争力強化を図る時代になってくるべきだと思う。
さて、板橋さんがどういった端緒でスクープをものにしたか、どういった調査報道の手法だったのかという点に関心が集まる。そこで、レポート記事の一部を引用させていただきながら時代刺激人ジャーナリストの立場で、何がポイントだったか取り上げてみよう。 板橋さんによると、取材応援で郵便不正事件の裁判の法廷でメモをとっていて、被告の上村勉・元厚生労働省係長が「1人でやりました。(上司で当時の担当課長だった)村木さんとの共謀はありません」と一貫して発言が変わらないため、検察捜査の際の供述調書と公判証言のどちらが本当なのだろうか、と疑問がわいたのが独自に取材することになったきっかけという。
「検事が捜査の見立てに合うようデータ改ざん」との検察内部証言がきっかけ
「一連の問題の端緒となる話を検察関係者から聞いたのは、7月のある夜だった。『上村元係長の自宅から押収されたフロッピーディスク(FD)のデータを、捜査の主任である前田恒彦検事(当時、10月11日付で懲戒免職)が改ざんし、偽の証明書の最終更新日時を、捜査の見立てに合うように変えた』と。疑惑は検察内の一部で今年1月に把握されたが、公表が抑えられていた疑いもあった」「取材で得た証言を検察側にぶつけても、証拠がなければ否定される可能性もある。司法担当キャップの村上英樹記者と話し合い、FDの入手を最優先とし、改ざんの痕跡を見つけるために専門機関に鑑定依頼する方向で動くことにした。鑑定結果があれば、検察が否定しても記事に出来ると判断したためだ」という。
板橋さんは上村元係長の弁護人のもとにFDが返却されているのをつきとめた。しかし弁護士の側のガードも堅く、数週間の取材を通じてやっと理解を得てFDを借り受けた。そして独自に専門の鑑定機関に持ち込み、改ざんの痕跡を見つけて検察関係者の証言が間違っていなかったことを確認した後、検察幹部に事実を伝え、独自に内部調査に踏み切るかチェックしたあと、記事化する決断に至った、という。
検察のメディアリークというよりも取材の熱意と問題意識の勝利と見るべき
ここで、奇異に思われる方も出てこよう。つまり検察の取材というのは、常に「捜査妨害」をタテにガードされ、夜討ち朝駆けというさまざまな取材を試みても難しい、という話なのに、どうして検察関係者から、主任検事による押収資料データの改ざんという、検察に100%不利な情報がとれたのか、と。確かに、そのとおり。朝日新聞は取材ソースに関しては、いっさい明かさないが、私が推測するに、ニュースソースは同僚検事か、その周辺の検察関係者であることは間違いない。これを検察関係者がリークという形で板橋さんに書かせたとみるか、あるいは板橋さんの取材の熱意が検察の良心を動かしたとみるかどちらかだ。でも、私に言わせれば、調査報道に際しての問題意識の勝利だと思う。
板橋さんはレポートの末尾で、こう述べている。「埋もれた話を聞きだし、証言を裏付ける取材を徹底的にしたことが記事につながった。自分が感じた疑問を出発点に、日常の取材から一歩踏み出す。それが記者としての基本動作であることを、改めて実感している」と。これこそが調査報道の原点だろう。
毎日新聞では2年連続の調査報道スクープで新聞協会賞受賞の女性も
この調査報道でのスクープという点では、過去には同じ朝日新聞の川崎支局による有名なリクルート事件報道もあるが、特筆すべきは、私がかつて所属した毎日新聞で2003年、そして翌年2004年に連続して、大治(おおじ)朋子さんという記者の調査報道で防衛庁のスキャンダル2件を明るみにして、見事に日本新聞協会賞(編集部門賞)を2度続けて受賞していることだ。
また同じ毎日新聞で、ご記憶かどうか、わからないが、2000年に北海道報道部の取材グループが、東北旧石器文化研究所の副理事長(当時)の旧石器ねつ造事件、具体的には発掘調査の前にわざと地面の中に旧石器を埋めて、さも大発見というふうにねつ造した「神の手」事件とも言われている現場を綿密な調査報道で突き止め、ビデオ撮影して報じた。これも素晴らしい調査報道だった。
大治記者「記者が掘り起こさなければ永遠に公表されないニュースに迫る必要」
この大治さんが「ジャーナリズムの条件シリーズ (1)職業としてのジャーナリスト」(岩波書店刊)で「防衛庁リスト報道の軌跡」と題して、調査報道の課題にも言及しているので、少しご紹介したい。以下がそのポイント部分だ。これを締めくくりにしたい。
「『社会正義』『義憤に駆られて』『スクープを書きたい』――記者の動機はさまざまだ。『調査報道に必要な記者の資質は何か』ということもよく聞かれるが、何であれ。長丁場で証拠を集める作業には、気力と体力が必要であることは間違いない。(専門家に調査報道でつかんだ事柄の法律違反の度合いの判断を聞くと、違反とは言えない、シロだ、と言われてしまう)『専門家の壁』に打ちのめされ、袋小路をさまよっていた時期、私を支えてくれたのは『シロウト感覚』だった。(中略)法律がどうであれ、専門家が何を言おうと、常識的に考えておかしいと思う時は、その問題意識はむやみに『シロウト感覚』として片付けるべきでない。そう思いなおして、私は再び取材を続けた」と。
「調査報道は、従来からメディアの重要な役割の1つとされてきた。それだけに、今ことさらに、調査報道の重要性を訴える必要があるのか疑問に思う人がいるかもしれない。しかし、私は、インターネットの時代であるからこそ、調査報道の重要性が一層増していると思う。(中略)ネットで読める情報と同じ情報をそのまま報道していては、メディアの存在意義は薄れて行く。どこでも得られる一般的なニュースとは別に、記者が着目して掘り起こさなければ永遠に公表されることがないであろうニュース――調査報道こそ、改めて必要とされるのでないだろうか」と。
関連コンテンツ
カテゴリー別特集
リンク