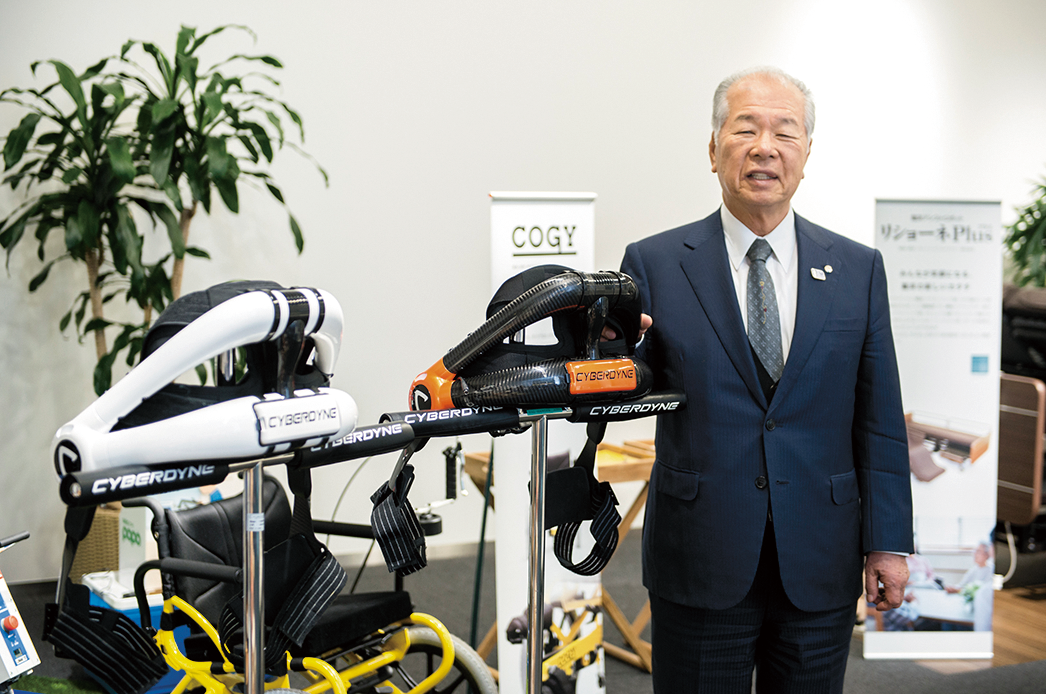2011年はどんな年になるのだろう。日本は政治のおびただしい劣化で、デフレ脱却どころか閉そく状況に歯止めがかからない不安がある。しかし、ネガティブにモノを見ていても仕方ない。ここは、前回コラムで申し上げた日本のフルモデルチェンジに取り組んでいくべきだ。キーワード的には、さまざまな制度的課題を克服して先進モデル事例をつくって世界中に胸を張れるようにする「課題克服先進国」をめざすことが大事だ。それと同時に、日本の戦略的な強みを見極め、その強みに磨きをかけて世界の成長センター、新興アジアへのアタックをかけることだろう。
そんなことを考えていたら1月1日夜、NHKスペシャルが「新たな日本ブランドを売れ」「中小企業のスピードが時代を開く」などをテーマに、日本はプラス思考で経済活性化に取り組め、という好企画を放送した。2時間に及ぶものだったが、重厚な内容で、私自身が活力をもらった。そこで、登場した5人の専門家のメッセージを、経済ジャーナリストの立場で少し補強しながら再録の形で、お届けしよう。
コマツ会長の坂根さん「日本の強みを生かせ」「傍観者から当事者になれ」
まず登場したのが建機メーカーとして、世界で米キャタピラーに次ぐ高いシェアを誇るコマツの会長、坂根正弘さんだ。冒頭、日本経済の置かれた閉そく状況を打破するために「日本の強みを生かせ」、「傍観者から当事者になれ」を力説した。さらに「日本は技術で勝ちながらビジネスで負けるケースが多いが、それはマネージメントの責任。経営者がトップダウンで経営判断しないとビジネスは成功しない」と述べた。なかなか鋭い。コマツが1990年代ごろの業績低迷期を脱し経営に弾みがついたのは中国など新興経済国への積極展開だ。企業に勢いがあると、不思議に、トップリーダーの発言にも重みがある。
坂根さんの話で、コマツが円高をモノともせずに海外での競争力を維持し高収益を上げるすごさが見えた。その理由の1つが、現経営陣の執行役員32人のうち、約80%の24人が海外営業現場経験を持っていることだ。坂根さんによると、グローバル展開するコマツ経営にとって、海外での現場経験は経営に携わる者の必要条件で、それなくして昇進もあり得ないのが暗黙のルールだという。
グローバル対応には独自事業モデルが重要、IT駆使して建設機械にGPS搭載
コマツはIT(情報技術)を駆使して独自の事業モデルを積極展開したのも、経営のひらめきがきっかけ、という。坂根さんによると、日本国内で銀行の無人ATM(自動現金引き出し機)施設がトラック突入で壊されATMを持ち去られる事件が相次いだ際、盗難防止をヒントに、コマツは世界中に販売する20万台の油圧ショベルなどの建設機械にGPS(グローバル測位システム)をとりつけ、経営に活用することを考え出した。
このGPS装備はすごい経営判断だ。今では、コマツは世界中の建設機械の稼働状況にとどまらず、機械の故障状況まで把握可能で、部品の補充などアフターサービスにもつなげている。最大手市場の中国では、現地に出回る粗悪な模造部品が取り付けられるリスクがあり、機械の品質機能にまで影響しコマツブランドのイメージダウンになりかねない。そこで、GPSだけでなく電装品から消耗品にまでICタグもつけることで、日本から、すべてがお見通しとなる。坂根さんがいう「日本は技術で勝ちながらビジネスで負けるケースが多い。トップダウンでの経営判断がなければビジネス成功はない」ことを実践したのだ。
アイディア技術で活躍の中小企業コミー、少量・多品種・高品質・高利潤が強み
日本のモノづくりの現場、とくに中小企業で、日本の強みである技術力、とりわけすり合わせの技術を武器に、世界でオンリーワン企業となる事例もNHKスペシャルで取り上げているので、紹介しよう。真田幸光さんが紹介役だが、旧東京銀行の銀行マンから愛知淑徳大学ビジネス学部教授に転身され、先端的な中小企業経営の現場を歩いて成果研究という点では素晴らしいものを持っておられる人だ。
紹介事例ですごいなと感じたのは、埼玉県川口市にあるコミー株式会社。もともとは看板製造会社だったそうだが、小宮山栄社長の経営才覚で、ミラー(鏡)メーカーに転進し技術力を武器にアイディアをめぐらし需要掘り起こしを図ったら急成長した。中小企業のビジネスモデルとなるのは、大企業の系列や下請けから離れて独自の技術力で世界的なレベルにまで行く技術企業になったこと、しかも少量・多品種・高品質・高利潤を経営の基軸に置いた点が素晴らしいことだ、という。
コンビニの万引きなどチェックのため、特殊な凸面鏡で広角度に見ることが可能なミラー技術では80%のシェアを持つ。それだけでない。ボーイング航空機からの引き合いで客室乗務員がボックス棚のお客の忘れものチェックを簡単にできる広角ミラーを開発し独自シェアを持つ。社員わずか20人で、今や年間売上高が5億円という高収益企業だ。
強度抜群のシリコン合金でオンリーワン技術企業イスマンジェイ、真田さんは絶賛
真田さんが紹介したもう1つの事例、神奈川県川崎市の株式会社イスマンジェイも素晴らしい。大手鉄鋼メーカーを辞めて起業した渡辺敏幸社長の技術力で一気に経営が開花した中小企業だが、独自の燃焼合成技術とセラミックスの材料比率によって、鉄鋼の2倍強の強度を持つシリコン合金の新素材の量産に成功した。その燃料合成技術は電力をほとんど使わずに、安全でクリーンな地球環境に優しい素材で、いずれは鉄に代わる次世代素材としても脚光を浴びる可能性もある逸材だ。
ここでの真田さんの指摘ポイントは、「中小企業が大企業の下請けから離れて、直接に優れた技術開発を行い、日本だけなく世界各国に対して製品提案していくすごさだ。日本に居ながら外貨を稼ぎだす強さを持っている。その取引先開拓では、その中小企業がすべてリスクを負う必要はなく、市場開拓力のあるエージェントを探し出して双方ハッピーのWIN・WIN連携をつくりだせばいい」という点だ。
「大紅栄」リンゴは中国向け輸出、藻谷さんは高品質「日本ブランド」勝負を主張
次にNHKスペシャルに登場したのが、前回コラムで取り上げた日本政策投資銀行の藻谷浩介さんだ。著書「デフレの正体――経済は『人口の波』で動く」(角川書店)が評価の対象になったのだが、藻谷さんは今回、青森県弘前市の工藤清一さんというリンゴ生産農家が、「大紅栄」というブランド名の真っ赤な大玉(おおだま)のリンゴを開発し、中国の富裕層をターゲットに輸出販売している事例を紹介した。
藻谷さんによると、一種の戦略的な生産、そして販売の手法をとるリンゴで、具体的には他のフジや国光の大量生産・大量消費に照準を当てたものと違い、生産を抑えて少量・高品質によって市場でのブランド価値を高めるやり方だ。わっと過当生産競争になって品質を落とさないため弘前の農業協同組合もバックアップする念のいれようだという。
この「大紅栄」が中国上海などで1個148元、日本円換算2000円で売られ、それでもニューリッチと言われる新興富裕層に人気がある。高成長に酔いしれる中国ならではの話だが、テレビでは「味がいいし、しかも高価だから一種のステータスシンボルになる。高くても買いたくなる」という中国の富裕な消費者の声を紹介していた。
藻谷さんは「愛媛のタオル、新潟・燕の爪切りなど、新たな日本ブランドで売っていけばいい。少量生産・売りを貫きながら高利潤確保は、中小企業のみならず日本産業の今後のキーワードだ」という。そして、持論の「日本経済は、個人消費が生産年齢人口の減少によって下ぶれてしまい、企業業績が悪化して、さらに勤労者の所得が減って個人消費が減るという悪循環を何とか断ち切るべきだ」と述べると同時に「景気が悪いなどと景気のせいにする前に、もっと売れるような自助努力をすれば道は開ける」という。
米倉教授は「新興国の追い上げに対応し、日本は産業フルセット装備必要なし」
次は一橋大学教授の米倉誠一郎さんだ。米倉さんも魅力的な学者で、研究室に閉じこもるタイプではなく現場重視の研究だ。自ら「日本元気塾」というビジネス塾を主宰するほどだ。米倉さんが番組で指摘した点のうち、今後の日本産業や企業の在り方を考える際のポイントだと思ったのは「日本の産業はあらゆる業種をフルセットで抱え込み、何でもつくる必要はない。戦略的に強みのあるものに特化してつくればいい」という点だ。
そして、米倉さんは「世界が何を求めているかニーズの把握を常に考えていないと遅れをとる。それに、日本がどんなに優れた、いい技術を保有していても、使い方が下手であれば同じく遅れをとるだけ。それよりも世界の消費市場にチャレンジすべきだ」と述べた。要は、玄人好みのこだわりの技術でいく日本の携帯電話が標準化モデルに立ち遅れて世界市場では通用しないガラパゴス化現象に陥った事態を回避すべきで、むしろ世界の市場をとるマーケット戦略などが必要だ、という考えだ。
その点に関連して、米倉さんは、いま日本にとって大きな産業戦略課題になっているインフラ産業開発向け輸出にあたって、新幹線の運行システムなどシステム輸出の方が圧倒的な強み部分だという。JR東日本の事例研究を行った結果、新幹線総合指令室の運行管理システムが効果をあげ、新幹線の遅れは平均18秒なのだという。もちろん大雪や地震などを想定して対応する安全運行管理システムで、米倉さんによれば、これこそ日本のソフトパワーで、こういったシステムを売りにするのも一案だという。
ノーベル賞受賞の根岸さんは人工光合成でCO2分解技術が出来つつあると披露
最後に登場したノーベル賞受賞の根岸英一米パデュー大学特別教授の話も刺激的だった。要は、現場の科学技術研究が進み、原子力発電所の燃料となるウランをめぐる争奪戦が世界で起きている中で、何と特殊加工のポリエチレンを使って黒潮の海流が運んでくるウランのうち、原発200年稼働分のウランを回収することが可能な技術もできつつある、という話をされた。また、光合成を人工的に行える光触媒という粉末の開発も進んでいること、これによって環境汚染や地球温暖化の原因とも言えるCO2(二酸化炭素)を効率よく分解させることが可能になるというのだ。
根岸さんは、「発見の10項目」というのを紹介し、発見に至るまでにはニーズ、知識、アイディア、判断、不屈の行動力、意志力などとともに幸運な発見ということもあるが、しかし同時に競争が原動力になることも間違いない、競争しての刺激が大きな発見を生みだす、と述べた。
以上、いずれも興味深い話ばかりだが、みなさんはどう受け止められるだろうか。