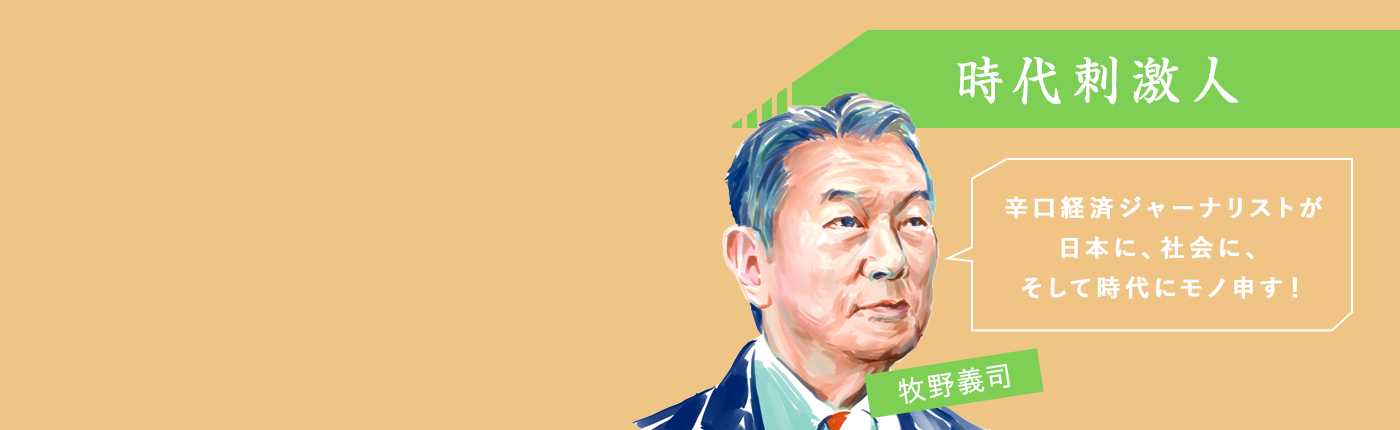
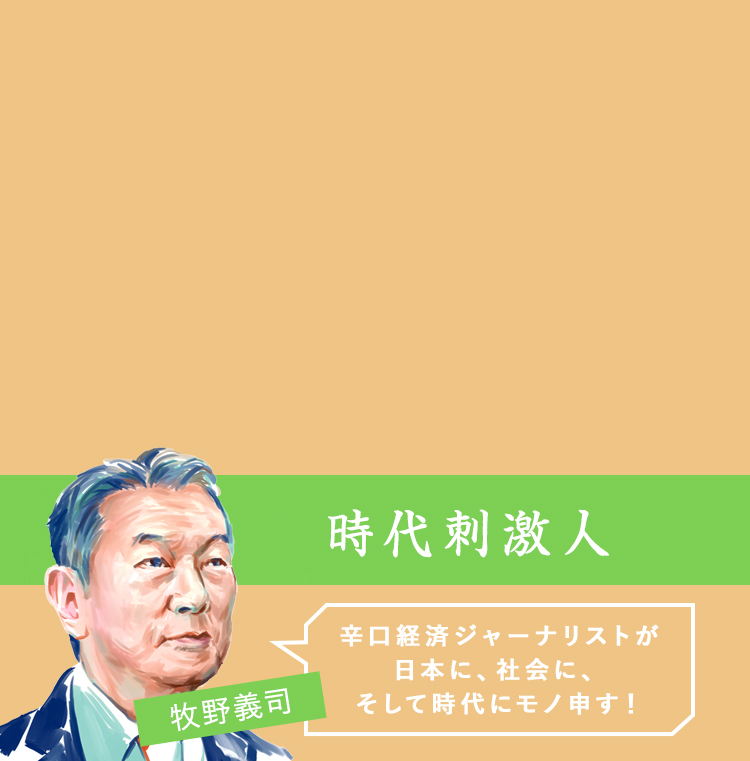

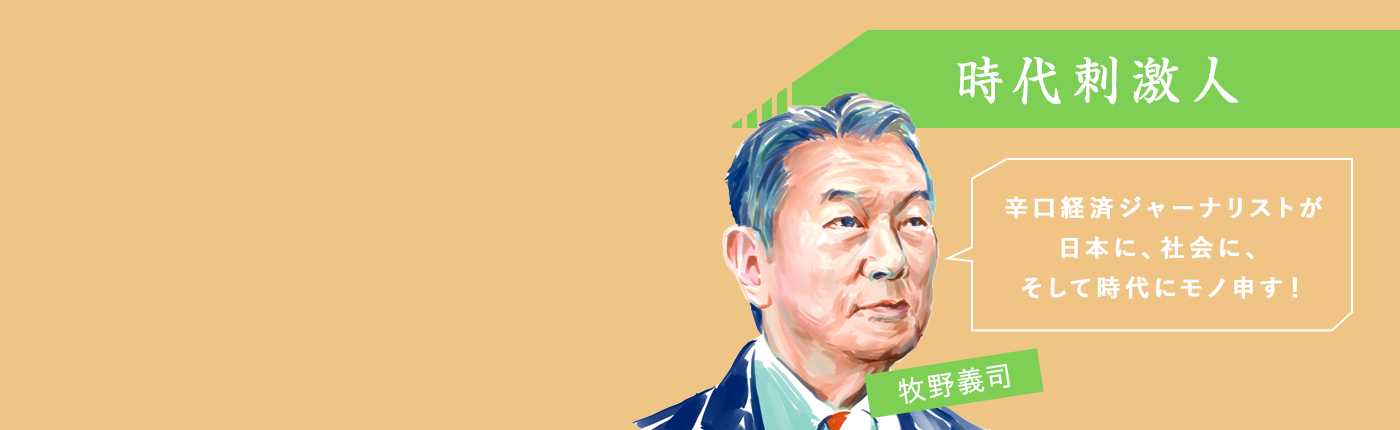
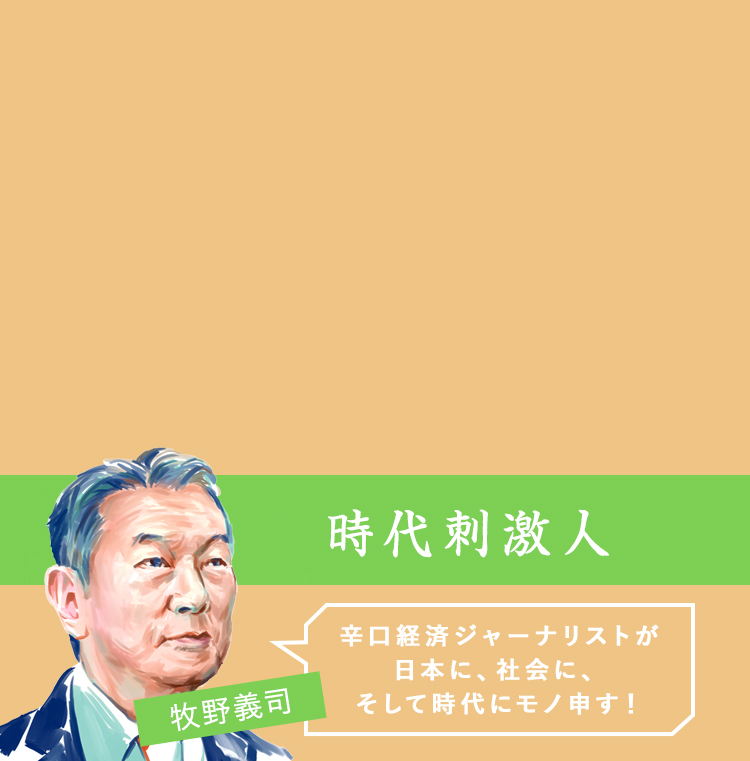

そこで、新たに考えられるのが外国人の活用だ。東京のタクシー準大手日の丸交通が、日本在住経験の長い27か国70人の外国人の人たちをタクシー運転手として採用し現場活用しているのを最近、知った。この取り組みは外国人観光客対策だけでなく、長期的な運転手不足への布石ともなる。時代先取りの面白いチャレンジだ。
「2024年問題」を取り上げたあるTVで、この日の丸交通でタクシー運転するガーナ出身のハッサンさんを事例紹介した。日本で16年間生活するハッサンさんは、「外国人のお客から、英語でいろいろ会話が出来てよかった、と感謝された」とニッコリ。ところが、同じTVで京都の都タクシーを取り上げていた。こちらはタクシー運転手不足のあおりで車庫には稼働できないタクシー50台を前に頭を抱える社長の姿を映し出した。外国人観光客が多い京都でこそ、タクシー会社は日本在住の外国人を活用すべきで、経営の問題だ。
外食産業の現場でも人手不足が影を落としている。私が驚いたのは、牛丼チェーン大手吉野家の東京・西新宿8丁目店で、今年4月下旬から5月ゴールデンウイークにかけ「人手不足のため、一時休業」の張り紙を出したことだ。吉野家広報関係者は当時「時給引き上げでスタッフ募集をかけても人手が確保できないための一時的な措置。一部の店での出来事とはいえ、サービス業なので辛い」と述べていた。人手確保ができないのは切実な問題だ。
しかし同じ外食産業すかいらーくグループは主要店で人手不足対策のため、配膳ロボットを積極導入している。外食現場にとって、ロボット活用は重要なヒントだ。ロボットは、まだ試行錯誤領域だが、老人介護の現場、物流現場での運搬補助や配送センターでの在庫管理、医療現場での手術でロボット活用が進み始め、人手不足対策になるのは間違いない。
ハンバーガー・チェーンのモスフードサービスでは、人手不足対策から、シニア男性を積極採用して顧客へのサービス対応を行っている。フルタイム就労ではないが、これらシニアの人たちは無断欠勤がなく、真面目で接客姿勢もよく、好評だ、という。
企業が、シニアの人たちに生きがい就労という形で、高齢者雇用の場を提供するのは極めて重要だ。身体を使って働くことで、医療や介護が不要になれば、アクティブシニアが生まれる。それは、超高齢社会時代の新社会システムづくりの布石ともなるので、賛成だ。
関連コンテンツ
カテゴリー別特集
リンク