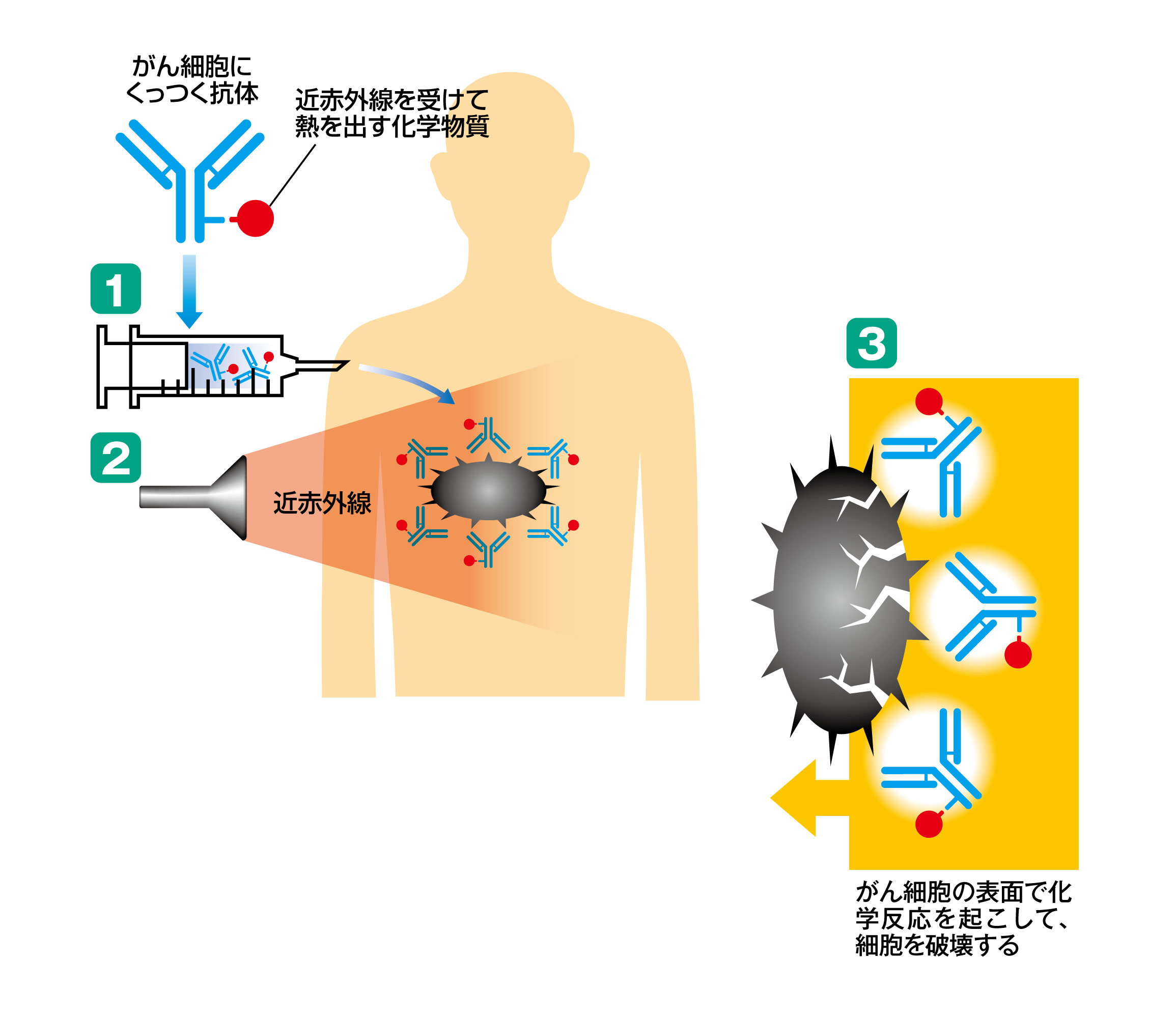放送15周年の特別インタビューとして、これまでに「賢者の選択」にご出演いただいた方々に、時代や環境変化への対応や展望についてお話しを伺いました。
(株式会社学研ホールディングス 代表取締役社長 宮原 博昭:賢者の選択ご出演 2012年12月放送)

単に日本発ではなく、世界に通用するものをアジアへ
ロボットプログラミングなどSTEAMの分野が大きな伸び
教育のICT化が求められて久しい。放送当時、子どもたちが伸びていくためには、教育のデジタル化、コミュニケーションの伸長が大切だと語っていた。
「当時と違うのはビッグデータ処理やCBT、AIなどICTを超えるステージに上がってきたことです。こうなると、もう世界レベルでしか戦えないものですが、日本は残念なことに立ち後れています。ひとつの企業だけではなく、他社や海外の企業と組んで、もう一度、教育の国際化を図っていかなければ難しいと考えています」

同社の海外展開もエリアが変わってきた。
「現在はタイとミャンマーでの展開に力を入れています。既に成功と言えるレベルに達しており、今後も大きな伸びが期待できます。また、インドネシアでも課外授業で当社の教材が使われています。学力の向上だけでなく、あいさつや子供が勉強する姿勢、生活習慣の向上にもつながることから、教育関係者から高い評価をいただいています」
特に注力しているのは、STEAMの分野だ。
「STEAMの中でも、今はロボットプログラミングは世界的に流行っています。日本はもちろんアジアでも人気です。かつては科学でしたが、これが今、STEAMに変わってきています。これからの時代は、日本の良いものをアジアに輸出していくのではなく、世界で通用するものを日本で作り、それをアジアに送り出さなければなりません。そうしなければ、取り残されてしまうのだと思います」
少子化、高齢化が進む日本の社会にありながら、マーケットは必ずしも縮小傾向ではないのだという。
「少子高齢化は確かに大きな打撃となります。出生数は第1次ベビーブーム期には約270万人、第2次ベビーブーム期には約210万人でしたが、2017年にはでは約95万人までに減っています。しかし、一方では通塾率が上がっています。これは大学進学率と正比例する傾向にあります。現在の大学進学率は52.1%ですが、通塾率は約55%です。人口は減るのですがマーケットは現状維持か伸びる傾向にあります。さらに、学校で対応できない部分も増えていきます」
アジア圏では今後の成長に期待がかかる。
「海外ではアジアで塾ビジネスに成長が期待できます。この背景にあるのは都市化により都市部に人口が集中するためです。かつての日本がそうでしたが、日本以上に速いスピードで動いています。都市化によって、所得差と地域差が生じ、教育にも差が生まれます。所得のある人は塾や家庭教師をつけるなど教育へのニーズが高まります」
事業は教育サービスにとどまらない
福祉分野は成長戦略の大きな柱になる
教育サービス以外の分野ではどのような展開が進んでいるのだろうか。

「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を約5500居室、保育園・学童施設合わせて50の子育て支援施設を運営しています。医療福祉サービス事業は、拠点の拡大やサービスの拡充により、今後に向けた大きな柱として成長してきています。特にサ高住は、公的年金の受給範囲で住める高齢者のお住まいとして高い評価をいただいており、今後全国の中核都市を中心に、更に広げていきたいと考えています。」
出版も続けていかなくてはならない重要な事業分野だという。
「出版は0を1にする仕事です。無から有を作るという仕事はこれからもなくしてはいけないと思います。これまで紙に表していたのを、液晶やデジタル化、映像になるという進化はやっていかなければいけません。今後も紙媒体が築いてきたものづくりのノウハウを守っていきます。正確なコンテンツをしっかり作るのはやはり出版。途絶えさせてはいけないと思います」
地域差・所得差からくる「学力差」や高齢者の生活格差など課題は山積している。同社は、民間企業としてその一つひとつの解消にまじめに取り組んでいく考えだ。