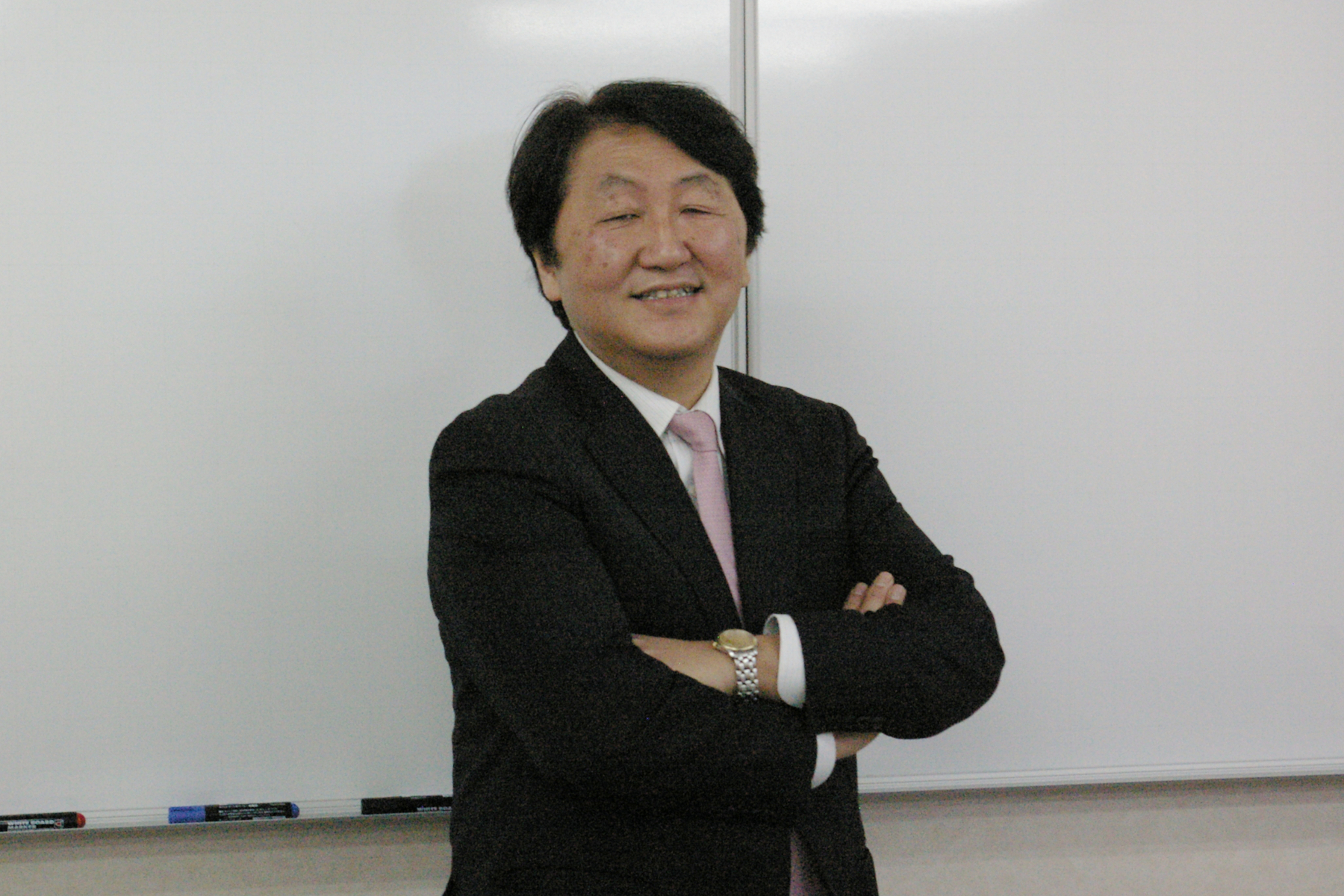開塾以来、40 年以上の実績を誇る革新的教育メソッド
昨今の急速なテクノロジーの進化に伴い、知識力が問われる時代から問題解決力が問われる時代へ変化しつつある教育の在り方。2013 年放送当時、すでに「やる気アップメソッドが重要」と仰っていた清水代表率いる誉田進学塾のめざましい躍進。自らの力で問題を解決するためのトレーニングを行なうという教育メソッドで地域ナンバーワンの合格実績を誇る。
「基本は、本人がやる気の高い状態で自ら勉強することによって成果が生まれるという原点に近い教育に根ざしている。成績が伸びなければ、本人にやる気がないからだと判断されがちな教育界において、私たちはそうではなく、やる気を引き出し、高く持続させるにはどうすればよいかという考え方で教育プログラムを組み、実践している」
脳科学や教育科学のエビデンスを踏まえた指導法を現場で活かしつつ、クリエイティブな思考をトレーニングする技術の開発にも余念がない。
「2013 年当時と比較すると、現在は中学受験部門は 2 拠点、高校受験部門は 9 拠点、大学受験部門は 6 拠点と、おかげさまで規模は飛躍的に拡大しており、職員も増えた。しかし、少子化の波が押し寄せ、業界では差別化が求められる中、今年のコロナによっていよいよ業界再編成の地殻変動が起きるかも知れないとまで言われている。我々はコロナ禍において、かなり早い段階で配信型授業教材と双方向型映像授業の体制づくりに着手し、オンライン化に素早く対応した。整備済みだった社内間オンラインのインフラを活用し、塾や予備校の閉鎖が相次ぐ中でも、私たちは生徒指導を継続することができた」
同社のオンライン化と AI による学習システムの開発・導入において、どの部分がモチベーションの維持に有効なのか、どの部分が学習効果に繋がるのかがはっきり見えてきたという。
「この経験が次へのステップの足がかりになると思う。来年度は本格的に AI(ディープ・ラーニング)を使った学習システムの開発・導入へと進んでいく。単純な知識を得るだけなら AI のほうが効果的。塾としてやるべきは、子どもたちの思考力を鍛え、クリエイティブな思考を生み出すトレーニング。より深化させていく技術開発に力を入れていきたい」
人間力が問われる時代に「本物の力」を養う
少子化やコロナの影響により、ますます生き残りをかけた熾烈な差別化競争の学習塾業界。同社では今現在も変わらず、本当の教育のあるべき姿を追求し続けている。未来を担う子どもたちに、学ぶことの楽しさ、理解できた時の感動、勉強そのものの面白さを伝えていくことこそ本当の教育だという。
「受験勉強は、苦しい試練を我慢し、その苦しみを乗り越えて結果を掴むものだと思われがちだ。確かにその経験も大切だが、基本的には勉強そのものが面白く、学び続けることや理解すること、そして、思考し何かを生み出すことの素晴らしさを体験しないと、社会に出てクリエイティブな活躍はできないと思う。一歩社会に出れば、与えられた環境の中で自ら思考し、自分の意見をまとめる能力が問われる。その意味では、私たちは業界の中でも先行して取り組んできた」
さらに同社は、かねてから働きやすい職場づくりにも取り組んでいる。規模拡大とスタッフ増員に伴い、育休・産休も取れるような女性にも働きやすい制度やフレキシブルな勤務体系の導入など、労働環境の拡充に努めてきた。そのことが、これからの教育を担う志高きスタッフのやる気を引き出し、共に切磋琢磨し、共に成長していく。
「働きやすい環境づくりは以前から取り組んできた。増員によって育休・産休の代替スタッフが可能になり(放送で取り上げられた当時新人だった一人は、今 2 回目の育休中)、より働きやすい環境を整備することで、ES(Employee Satisfaction)を高める。そのことによってCS(Customer Satisfaction)が高まるというサイクルは学習塾業界では珍しい。全国で 1000校舎以上ある東進衛星予備校のフランチャイズに弊社が加盟して 11 年経つ。受講者が翌年度継続して契約更新するかどうかの鍵が教務スタッフに対する信頼だ。ここ 4 年、弊社は加盟母体単位でその継続率が全国トップクラスそれは顧客満足度の指数だと思っている」
同社のプロフェッショナルな講師を生み出す力の源泉は科学的なエビデンスをもとにしたシステムと、その人のやる気や心を活かす指導研修にある。同社の指導理念を理解し、実践しながら 3 年から 5 年かけて徐々にステップアップしていく。
放送時の新人社員もテレビ生放送高校入試解説で活躍するまで成長 「2013 年当時は週に 1 回、模擬授業研修を行ないスキルアップを図っていたが、その後、規模拡大に伴い、何回かシステム変更をして順調に育成し続けている。例えば、同じく放送で取り上げられた別の当時新人は、その後テレビ生放送の入試解説でも活躍、現在は校舎長を務めている。週に 2~3 回、地域別の各拠点に 2~3 教室のスタッフが集まってそれぞれが研修を行なう(現在はオンライン化)形に変更。また、当時は新卒採用が多かったが、現在は中途のキャリア採用も増加し、私が直接行なう研修ではスキルアップというより、やる気を引き出す指導法など、誉田進学塾の『考え方』の研修に軸足を置いている」
2014 年に発表されたオックスフォード大学マイケル・オズボーン准教授の論文「雇用の未来」によると、AI などテクノロジーの進化によって 20 年後には 47%の職業がなくなるという発表が世界に衝撃を与えた。文部科学省も「対話的で深い学び」教育指針を示し、2021 年から大学入試は共通テストで記述式が導入される。知識力よりも問題解決力が問われる社会へ。まさに同社が開塾以来、指導し続けてきた教育の核心部分こそ、近い将来、劇的に変容するであろう社会を子どもたちが生きていくために必要な能力を鍛えていくメソッドと言えるのではないだろうか。