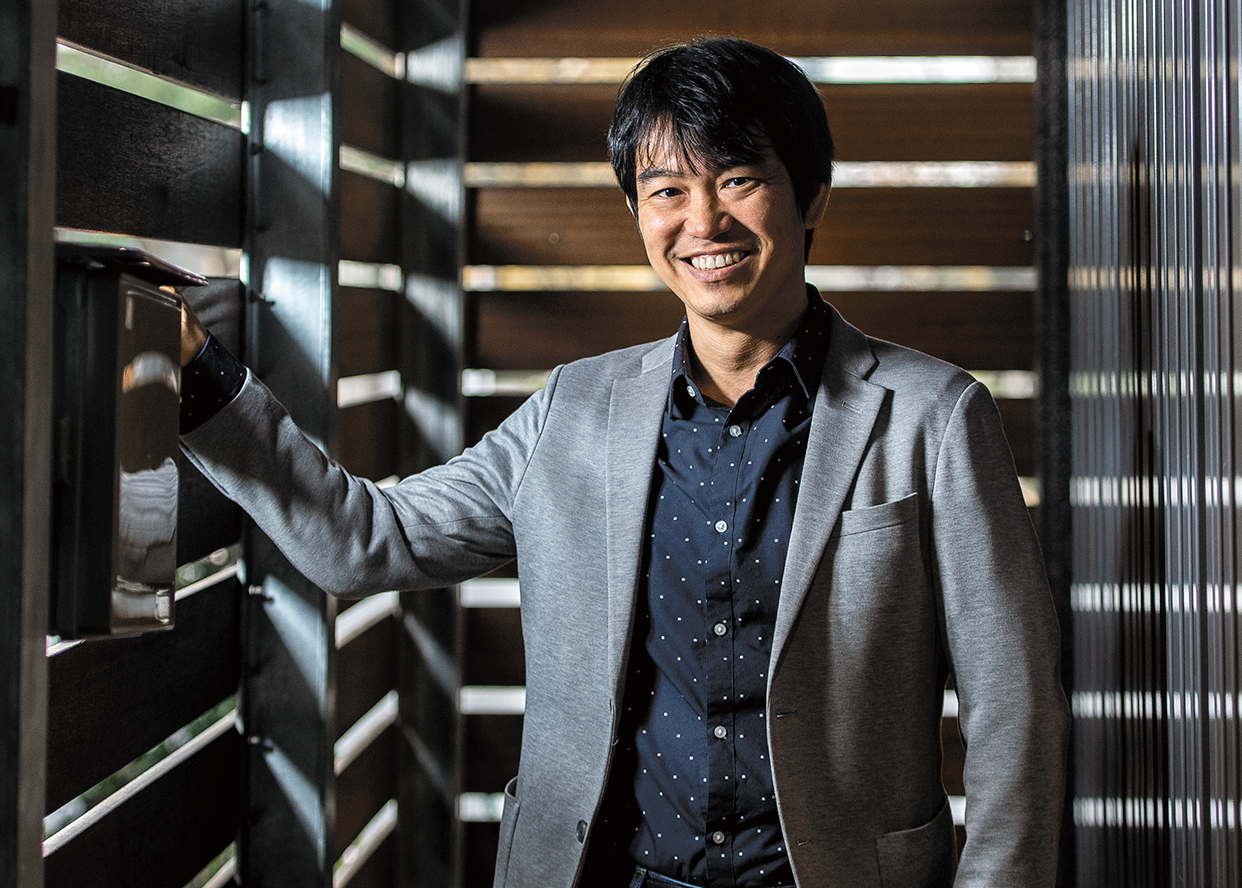小型化・コスト減で拡大見込める宇宙ビジネス
宇宙から地球を眺めればいろんな情報が得られる。例えば気象のきめ細かい変化を捉えれば、より正確な天気予報ができる。災害を予知し、人命を救うこともできる。一方、人工衛星の小型化で1基あたりの製造・打ち上げコストはかつての数百億円からその100分の1にまで下がってきた。宇宙ビジネスのニーズとシーズかが重なり合い、一気に拡大しそうな雲行きだ。
米国の起業家、イーロン・マスク氏、日本でも元ライフドア社長の堀江貴文氏らが宇宙ビジネスに多額の投資を始めている。人工衛星や打ち上げロボットの開発が熱を帯びる。
宇宙ビジネスのベンチャー企業、インフォステラ(本社・東京)も拡大する市場に参入しようとしている企業だ。だがインフォステラが目指すのは、多くの企業が開発に鎬を削っている人工衛星や打ち上げロケットの開発分野ではない。インフォステラ代表取締役の倉原直美氏はインフォステラのメインサービス「Stellar Station」(ステラステーション)は、「地上で宇宙産業を支える分野です」と言う。

宇宙ビジネスには人工衛星、それを打ち上げるロケット、そして地上側で衛星がとらえる情報を受け取る衛星運用ビジネスの三つがある。どちらかと言うと派手な分野が人工衛星づくりやロケットの打ち上げ。それに対し、地上での運用ビジネスは地味でプレイヤーも少ない。倉原氏が大学の研究者だったころやりたかったのはやはり「衛星」だった。
だが、今後、宇宙空間に数多くの人工衛星を打ち上げてもそこで得られた情報が地上に伝えられない、あるいは伝えるにはコストがかかる、という事態が予想されるという。
赤道上空3万6千kmを飛ぶ静止衛星ならば地球上の同じ地点からいつでも見ることができる。しかし静止衛星は大型で打ち上げコストが巨額になる。一方、今後成長が見込める小型衛星は高度400〜1000kmの低軌道を飛ぶ周回衛星だ。地球上をぐるぐる回っているから同じ地点からは常時、捕捉はできない。
人工衛星からの情報は地上のアンテナが受け取る。衛星がアンテナ上空を飛んでいる間しか通信はできず、その時間は約10分。一日に4回ほど地球を回るので通信可能なのは1日に約40分だけだ。
人工衛星を打ち上げた会社(あるいは大学や研究組織)がアンテナを地上に1基しか持っていないとすれば、衛星から得られる情報は40分
で通信できる分。それでは人工衛星もアンテナも不稼働な時間が多く効率が悪い。地球上に40〜50基のアンテナを設置すれば常時、通信はできるが、コストがかかりすぎる。1基数百万円〜数億円程度のアンテナを世界各国の法律や規制をクリアしながら建てるのは至難の業だ。

地上との通信コスト 宇宙ビジネスの制約要因
倉原氏は「宇宙ビジネスにとって、地上との通信が制約要因なのです。この課題を解決しなければ宇宙ビジネスのサービス価格は高いままで、利用は広がりません。私たちはこの課題を『アンテナのシェアリング』という考え方を取り入れて解決しようとしているのです」と話す。
世界の人工衛星運用会社が持っているアンテナをシェアすれば、宇宙と地上との間で効率的に通信をするプラットフォームができるというアイデアだ。一つのアンテナは1日に40分しか稼働していない。残りの23時間20分を他の多数の人工衛星との通信に使い、その時間をそれぞれの人工衛星運用会社に提供すれば、人工衛星運用会社も、アンテナ保有会社も効率的な運営が可能になり、サービス価格を下げることができる。
倉原氏は目指す世界をこう説明する。
「インターネットが登場し、いつでもどこでも情報がやり取りできる世の中になりました。その結果、様々なサービスが生まれ発展した。比喩的に言うなら、宇宙ビジネスに『インターネット』のようなプラットフォームをつくり、ユーザーの裾野を広げたいのです」
その昔、インターネットにつなぐには一回ごとにダイヤルアップ接続をしていたが、常時接続が可能になり、一気にサービスが広がった。宇宙ビジネスでもいつでもどこでも人工衛星から情報が得られる仕組みができれば、飛躍的な利用拡大につながると倉原氏は見ているのだ。
倉原氏が「アンテナをシェアする」というアイデアを思いついたのは、10年ほど前。九州工業大学大学院で人工衛星の研究をしていたころだった。欧州宇宙機関(ESA)が主導したプロジェクトに参加した。各国の大学生が連携して人工衛星のための地上局ネットワークをつくプロジェクトだった。それぞれの大学が持っているアンテナをシェアしてお互いに助け合おうという狙いだった。
「当時からアンテナ問題を解決しないと宇宙利用は広がらないという問題意識は共有されていました」と倉原氏は振り返る。
その後、博士号を取り、東京大学特任研究員となった。小型衛星開発プロジェクトの地上システム開発マネージャーを務め、地上運用システムの構築を担当した。「地上派」として活躍し始め、13〜16年まで衛星管制システムで世界最大手のインテグラルシステムズの日本法人に就職。ここでも放送衛星、通信衛星を地上で支える役回りを演じた。
この間もずっと「アンテナをシェアする」事業の可能性に思いを巡らせていた。世界最大手の衛星管制システム会社にいたが、収益が確実に見込めると保証できない事業の立ち上げは難しそうにみえた。

すごく面倒くさい だから誰もやらない
ロケットや衛星の黎明期はすぐ目の前なのに、宇宙ビジネスの地上側の課題は未解決のままだった。だが世界各国の多くのプレーヤーたちに「アンテナをシェアしませんか」と声をかけ、それを運営する仕組みを作り上げるという事業には誰も踏み出せずにいた。また学生時代に関わった国際プロジェクトはボランティアべースの取り組みで、プラットフォームを長期的に維持するための組織には発展していなかった。
「すごく面倒くさい仕事なのです。だから誰もやらない。でも必要な仕事です。実現するには自分で起業するしかないと覚悟を決めました」
2015年の春ごろだった。倉原氏は知人の紹介でベンチャーキャピタルの専門家に相談したり、宇宙関係の知り合いに「一緒にやりませんか」と声をかけたりし始めた。
CEO(最高経営責任者)の倉原氏に加えて、共同創業者になる石亀一郎・COO(最高執行責任者)と社外取締役の戸塚敏夫さんが自己資金で会社を設立したのが16年1月だった。
「起業は未知の世界だった」(倉原氏)。石亀さんには起業経験があり、戸塚さんは会社経営者だった。事業計画づくりなどでは助けてもらったが、「何から何まで大変だった」と言う。
外部から合計8億6000万円の資金調達をし、今では17人の陣容に。国内外から優秀で英語が堪能な技術者たちが集まった。
「グーグルを辞めたソフトウエア技術者らが来てくれました。最小限の人数ですが、横断的なコミュニケーションを取って、助け合いながら仕事をこなす態勢をつくりました」。倉原氏は、最少人数で大きな夢を実現しようと知恵を絞る日々だ。
倉原氏の宇宙への憧れは、小学生のころから。1990年にソビエト製の宇宙船に乗り込んだ秋山豊寛さんをテレビで見て、宇宙飛行士になりたいと思った。航空宇宙工学科を目指したが、第一志望に落ちて、九州工業大学へと進む。だが「ラッキーでした。九州工大で人工衛星の研究室に入り、今につながりましたから」。大学進学で思い通りにいかなくても、倉原氏は夢を追い続けた。
17年末、東京・渋谷のインフォステラ社内は熱気を帯びていた。年早々のサービス開始に向けてシステムづくりが佳境を迎えていた。倉原氏も海外の客との折衝で世界を飛び回る。米国でも同じようなサービス提供を目指す会社が生まれた。急がねばならない。
「できるだけ早くサービスを立ち上げ世界で一番手になります。3年ぐらいのうちに宇宙ビジネスを手掛ける会社はみんなインフォステラをプラットフォームとして使っているという立場になりたい。みんな使っているけれどもインフォステラの名前は知らないというような黒衣になるのが夢です」。あくまでも縁の下の力持ちを目指す倉原氏である。