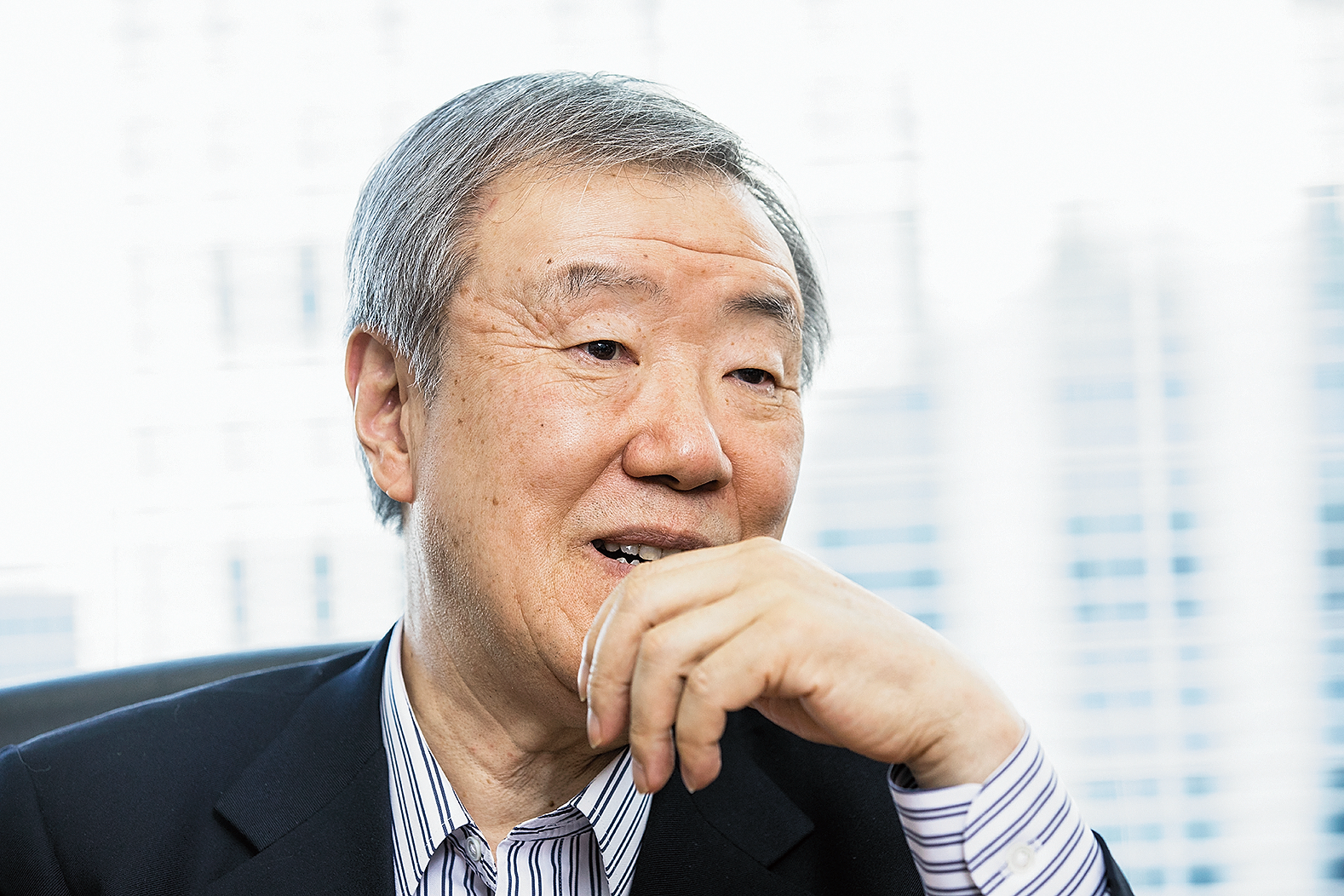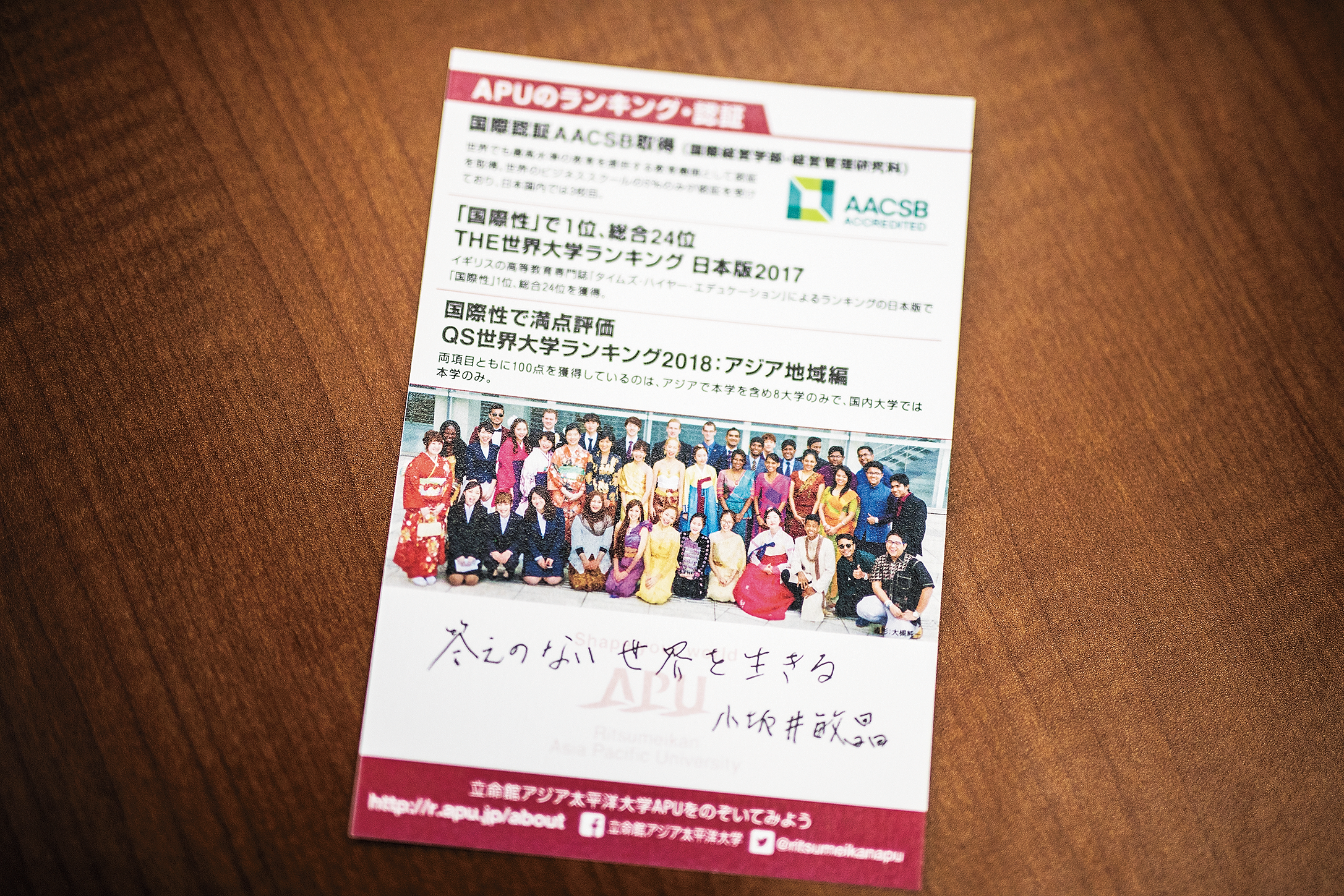元LINE社長は新たな挑戦になぜ踏み切った?
日本では少ないSerialEntrepreneur(連続起業家)の一人である。人生の中で一つの事業を起こし、社長となれば大仕事を終えたように思い、たいていの人はそこで満足するものだろう。元LINE社長の森川亮氏は、何しろ世界的なコミュニケーション・アプリを作り上げた人物である。そこで君臨し続けてもよさそうなものだ。
なぜ新たな挑戦に踏み出したのか。
「日本を元気にしたかったのです」
森川氏は2015年3月にLINE社長を退任し、翌月の4月にスマホ向けの動画メディアを運営する「C CHANNEL」を立ち上げた。「日本」にこだわりたかったからだ。
LINEの前身は韓国のインターネットゲーム会社。そこから事業を拡大し、LINEとなり、多くの国籍の人たちが働くグローバル企業に育った。グローバル企業のトップが「日本」にこだわるわけにはいかなかった。森川氏の「日本を元気に」という思いを実現するには、まず新しい会社をつくる必要があった。
「ビジネスでいろんな国の人々と話をすると、やはり自分は日本人だと思いました。『日本』が自分のアイデンティティであることを再確認したのです」
1980年代まではジャパン・アズ・NO.1と言われた時代もあった。東西の冷戦構造とバブル経済が崩壊した90年代からは世界の中で、日本が輝く瞬間は少なくなった。またメディアを賑わすのは経済界や政界の不祥事が目についた。
LINE社長になったころから講演などで若者たちと話をするようになった。そこで気付いたのが、若者たちにとって日本には尊敬できる政治家や経営者が少ないことだった。そんな状況を放置したままでは、日本の若者は夢を持てないにちがいない。
「日本発の新しい事業を起こすことで、若者たちに日本にも夢がある、未来があると思ってもらえるようになれば、日本は元気になると思います」
LINEを辞めて何をやればいいのかを考えた。超高齢化社会に向けた新しい医療サービス、ITを使ったeラーニング、エネルギー産業や農業ビジネス……。いずれも法律や規制に左右される事業でスピード感ある立ち上げが難しい事業だった。結局、たどり着いたのがメディア事業だった。
若い女性市場で目指すボリュームゾーン
最初から世界へスマホのMTV、CNNになりたい
「日本のメディアをみると政治や経済の揚げ足取りが多い。このようなニュースを見たり聞いたりしていては自信もなくなり、夢は持てない。もっとポジティブなメッセージを出し、日本を元気にすることが大事です。しかも日本発で世界ブランドになったメディアはまだない。世界に通用するメディア、つまりスマホのMTVやCNNを目指します」
最初から「世界」を意識しているのが森川氏のビジネスモデルである。それはLINEでも同じだった。
そのためには最初から大きな市場を狙う。小さな市場から徐々に大きくするという考え方は取らない。「日本発」を目指しているが、日本でまず始めて、大きくしてから世界へ、という戦略ではない。あくまでも「まず世界」なのだ。
「最初に日本の市場を狙おうとすると、国内では人口が多く、お金を使ってくれる中高年向けのビジネスになります。そこで成功してから世界に打って出ても、世界には日本と同じような市場はありません。世界、特にアジアなど成長市場に存在しているのは人口が急増する若者市場です」
森川氏が取り組むメディア事業のターゲットは若者だ。伝えるデバイスは「スマホ」。当然、紙ではないし、パソコンでもない。
当初からコンテンツを「動画」に絞ったが、「動画を見るのはもうテレビではない。スマホの時代だ」とターゲットを決めたからだ。
森川氏のビジネスモデルづくりの流儀は次のような思考を積み重ねる。
コンセプトは動画のファッションマガジン
動画で何を流せばいいか?→ニュース?→ニュースの収益化は難しい!→オタク向け動画は?→儲かるがやりたくはない→そもそもターゲットは男性か女性か?→男性は動画より文字、写真を好むらしい→ならば女性をターゲットにしよう!→今も売れている女性ファッション雑誌の内容を動画にする!
こうしてたどり着いたのが売れている若者向けの女性雑誌の内容をスマホに動画で流す、というビジネスだった。コンセプトは「動画のファッションマガジン」である。
コンテンツは、クリッパーと呼ばれる出演者がファッションやヘアメイク、恋愛、料理といったテーマを、自分でスマホを使って動画を撮影し、アップする。当初は自撮り中心だったが、コンテンツの質を上げるためにプロの撮影に変わってきた。
ファッションや化粧のメーカー、旅行会社とコラボしてコンテンツを作るという広告メディアとしての機能もある。
しかし、女性雑誌といっても、『ヴォーグ』のような高級女性誌ではない。あるいは女子高生を対象にした儲かりやすい分野でもない。「それでは市場が小さすぎる」と森川氏。どこの国にも一定数存在するおしゃれに関心のある若い女性をターゲットにした。あくまでも最初からボリュームゾーンを攻めてきた。
ユニーバーサルでも日本的でもない「現地化」コンテンツを
海外での事業は基本的には現地企業との合弁で進めている。すでにアジアを中心に10カ国で事業を展開。森川氏は「親日感情のある国では日本への憧れがあり、受け入れられやすい。中国は大きな市場だが、外資への規制などが強く、敷居は高いが、新たなチャレンジをするところ」と語り、中国を含めたアジアでの市場開拓に余念がない。
合弁での海外展開は、国ごとに好むコンテンツが異なり、現地での判断が重要になる。日本的なファッションやヘアメイクに対する憧れはアジアには一定程度あるが、欧米ではあまりない。
「コンテンツはユニバーサルでも日本らしいものばかりではなく、現地化を進めていく」。森川氏は「日本発」という夢にこだわるが、現実主義者でもある。現地法人のトップは現地のパートナー企業に任せている。
海外で日本のカルチャーを発信したいとしても、日本びいきの視聴者が少なくては事業が成り立たない。進出先でまずシェアを取ろうとしたら、その国のローカルのコンテンツを充実させるのが重要だ。米国の音楽専門放送局MTVは洋楽専門チャンネルだったが、今では日本でたくさんの邦楽も流すメディアに変わりつつある。
C CHANNELの場合、日本で制作したコンテンツが7割、現地で制作したものが3割の割合にして編成し、国ごとに内容を変えているという。
創業から3年が経ち、月間の動画再生回数は6億回を超えるようになった。SNSフォロワー数も2500万人を突破した。
「アジア市場の開拓はまだまだ」という森川氏だが、すでに南米やアフリカの市場開拓が視野に入っている。

女性による女性のための女性市場開拓
男は応援団になった
男性スタッフがつくった男目線の動画女性に受けず伸び悩む
2015年に50歳を前にして女性向け動画を運営するC Channelの社長になった森川亮氏。大卒後、森川氏が携わってきた日本テレビ放送網、ソニー、ハンゲームジャパン、LINEでの仕事はいずれも女性市場に特化した事業ではなかった。
男性も女性も相手にする事業だったので、むしろ森川氏は「男性と女性は同じように考え、対応しないといけないものだと思っていた」という。
その森川氏がC Channelの創業直後、何度も苦戦した。
創業当時のメンバーは男性が中心だった。日本テレビ時代の同期で、取締役として加わった三枝孝臣氏は歌番組やバラエティ番組などで活躍したプロデューサー。そのほかWEBメディアの編集長らが創業メンバーだった。
創業時の男性メンバーらがつくった動画は、女性たちの評判があまり芳しくなかったようだ。
動画に出てくる女性のブラウスの胸が少し開いていると、動画を見た女性は「男を誘っているみたい」とチクリという。グルメを紹介する動画に出演した女性が「久兵衛(東京・銀座の高級寿司店)で寿司を食べたことがあるの」と言おうものなら、「お金持ちのパパがいるのね」と嫌味を吐かれる。
数字は正直だった。動画の再生回数は伸び悩んだ。「出演する女性たちが男性受けする女性ばかりだったようです。男性目線でつくった動画は女性には受けませんでした」。森川氏は素直に反省し、女性のメンバーを徐々に増やしていった。
創業から半年ぐらいで動画の作り方はずいぶん変わった。
当初はクリッパーと言われる動画投稿者に自由に動画をアップしてもらうという考え方だったので自撮り動画が中心だった。だがそれではユーザーに役立ち、面白い動画とは言えないものまでもアップされ、再生回数は伸びなかった。その反省から動画のプロを使って編集作業をするという仕組みを入れて、見やすくした。
女性に受けたのはHowTo動画だった
内容のテーストも当初とは変わった。事業を始めたころはグルメ情報ならお店の紹介、化粧品なら商品の紹介といった店や商品を紹介するコンテンツが多かった。商品・店舗情報を雑誌のような文字コンテンツから動画に代えただけで、動画の付加価値はあまり高くなかったのかもしれない。再生回数は期待ほど増えなかったという。
ところが米国の料理メディア「テイストメイド」と提携し制作した動画がバカ受けした。日本人のマッチョなシェフがポーズを決めて筋肉をみせながら肉を焼くという動画だった。1300万回の再生を記録し、話題になった。当時の月間再生回数の目標は1000万回で、一本の動画で目標をクリアしてしまった。
それが切っ掛けで、誰かが何かをつくったり、ヘアメイクや化粧をしたりする動画を流すようになり、再生回数が増え始めた。世界最大の動画サイト「YouTube」でも人気のある動画は、人を笑わす「オモシロ動画」やHowTo動画らしい。
「動画はHowToならよく見られることが分かった。女性はHowToが好きなのです。自分らしい生き方を常に探しているのでしょう」と森川氏。
動画を参考に自分でも試し、美味しい料理をつくったり、化粧がうまくなったりすればうれしい。そんな女心をくすぐった。
料理やヘアメイクなどのHowTo動画を増やした結果、改善後半年余り経った2016年7月には月間再生回数が2億回を突破した。

「C CHANNEL」で見られるコンテンツは?
スマホのアプリを立ち上げるとトップ画面には「ビューティー」、「恋愛」、「料理」、「スポーツ」、「ショッピング」などのテーマが並ぶ。ビューティーならさらに「メイク」、「ファッション」、「ヘア」、「ネイル」などに小分けされていく。毎日80ほどアップされるコンテンツはすべて1分程度の動画。「メイク」なら「第一印象がグッと良くなる、綺麗め眉の作り方!」といった技が並ぶ。
試行錯誤の女性マネジメント
ダメだった「死ぬまで頑張れ」
過去に様々な事業で成功してきた森川氏だったが、これまでは女性に受ける商品をつくり、成功したわけではない。ならばコンテンツ作りは女性に任せた方が良いとなり、今では社員の男女比率は男性4割、女性6割と女性が男性を上回った。
社員に対するマネジメント手法も変わっていった。
森川氏は多くの起業家のようにハードワーカーである。自宅での仕事も含めて「1日15時間ほどは働いているだろうか」と言う。土日も自宅で働くことが多いという。
「人はストレッチで成長する」と思っていた。非常に高いハードルを必死で越えてこそ、ビジネスパーソンは成長すると信じていた。
LINEでも高い目標を掲げ、「死ぬ気で頑張れ」と社員を叱咤激励し、成功に導くことができた。
C Channelでも「厳しいやり方をすればうまくいく」と考えた。だが今では「厳しくするとだめでした」と笑う。
「女性は多くの男性のように会社のために働いてはくれません。C CHANNELのような女性が喜ぶコンテンツをつくりたい、という思いを持って働いている女性は『会社のために働く』という意識は少ないかもしれません」
森川氏はそう気づいたという。
C Channelで「死ぬ気で頑張れ」と言うとなぜ実績が上がらなかったのだろうか。こんな理屈らしい。
女性の多くは、ファッション、化粧もきれいにしたいという思いが強い。それなのに仕事で頑張りすぎて肌が荒れ、食事も不規則になり、ファッションやメイクを手抜きするようになると、自分が嫌になる。
ESを上げてCSを!面白いコンテンツつくれぬ疲れた社員
「C CHANNELは最先端のおしゃれを紹介していることが強みです。コンテンツをつくる女性がダサくなってはいいものはつくれません。仕事をしすぎてアウトプットの質が下がっては困ります」
要は働く女性の満足度、ES(Employee Satisfaction 従業員満足度)を上げないと、CS(Customer Satisfaction顧客満足度)も上がらないということだ。
すべての女性が同じようには考えているわけではなかろうが、女性は必ずしも会社のために働き、業績が上がれば満足するわけではない。女性の場合、自分のプライベートの生活を大切にしながら働けないようでは満足できない人が男性に比べて多いということだろうか。
若い女性を元気にするコンテンツを提供し、収益を上げようとするのがC Channel。「女性がやる気になり、元気じゃないと会社が成長しないというのが、実はこの会社のビジネスモデルなのです」。創業後3年たった森川氏の述懐である。
男性社員にも創業からの3年間でいろんな学びがあった。頭ごなしにあれこれ指示を出す男性幹部の部署からは女性は「異動させてほしい」と言ったり、辞めたりしたという。
「そんな状況では仕事は成り立ちませんから、男性幹部も学び、変わらざるを得なかった。男性は女性の応援団に徹しました」と笑う森川氏だ。